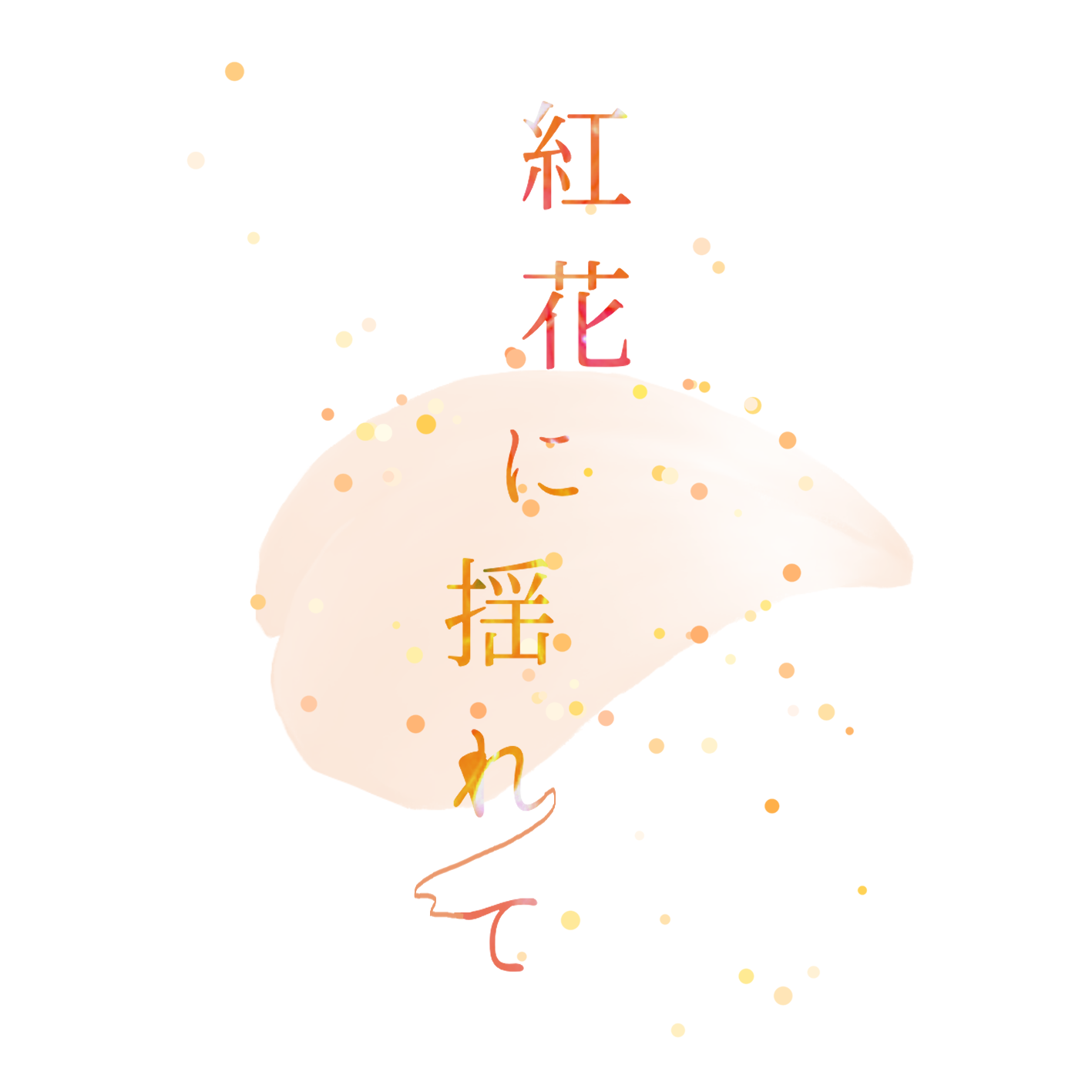杏寿郎が柱となって初めて迎えた皐月。その日は惜春というには少々遅いと思うほどに日差しが強かった。杏寿郎が生まれた日もこんなふうに晴れていたのだろうか。大きな産声が快晴の空へ広がる様は、まさしく彼の人そのもののように思う。袖に忍ばせたそれもきっと似合うことだろう。
「いつお渡ししよう……」
一度出したものの、もう一度しまい込む。そうしていると人影が炊事場を覗いていた。気づかないふりをして器を拭っていたが、一向にこちらに来る気配がない。
「杏寿郎さん?」
「む、気づかれてしまった」
残念だな!と杏寿郎は少年のように茶目っ気をみせた。それにはふふっと笑みを返す。
「あんなに見てたら誰だってわかるよ」
思わず全身に目を配る。薬品の匂いはしない。足や腹を庇う様子もない。怪我のないことに心底ほっとした。するとくるりとした緋色の目がを捉えた。
「俺は君の勘が鋭くなっているような気がするのだが!」
「そんな事ないよ。杏寿郎さんおにぎり食べるよね? ちょっとまっててね」
明け方、久しぶりに杏寿郎が生家へ戻った。が来たときすでに杏寿郎は就寝していたので、もしかすると今日も会わないままだと思っていた。でも、もしかしたら。そんな気がして遅い時間にお昼ご飯を炊いたのは正解だった。こういうとき、許婚の務めを果たせたような気がして嬉しくなる。具は特別に大きな梅干しを一つ。それから少しの塩と焼海苔を巻く。はい、と出したそれがあっという間になくなってしまうのも、すっかり慣れた。杏寿郎との間にはそれだけの付き合いがあった。
「今日、時間はあるだろうか? 実は出かけたいところがあって君にも来てもらいたいのだが……急いでいないので支度はゆっくりで構わない」
「わかりました。お出かけに……いっ、今、支度します!」
割烹着を脱ごうした。しかし着物の袖まで引っ張ったらしく、前へ転げそうになる。濡れた土間に下駄先が突っかかりぐるりと反転する間際、たくましい腕がそれを阻止した。
「存外、君はそそっかしいのだな」
杏寿郎は珍しく目を丸くしてこちらを見る。
「いつもは違います……」
「違うのか、それは失敬!」
杏寿郎は軽やかに笑ったが、後に草履を履くにも随分もたついたので信じていたかはわからない。
もう十年。されど十年。いくら付き合いが長くとも、にはまだまだ知り得ないことがあった。
それは赤子を撫でるような手つきでいて、また母の背を撫でているようにも見えた。杏寿郎は手慣れたもので、丁寧に、そして優しく墓石を拭う。
がここに来るのは初めてではない。命日は必ず、盆と正月も同じく手を合わせる。嵐が吹けば様子を見にくることもある。雪が積もれば払うことも。それでも杏寿郎と二人だけでここへ来たことはない。千寿郎がいたり、または実母と共に。気安く立ち入る場所ではないので当然かもしれない。なので……いや、単に知らなかったのだ、杏寿郎にそのような習慣があることを。今日は特別な日。
五月十日、大切な人が生まれた日。
「毎年そうしているの?」
「そうだ、と言いたいところだが、近頃はなかなかできていなかった」
仕方がないことだ、と杏寿郎はこぼす。鍛錬に明け暮れ、任務に赴く。ひと月などあっという間に過ぎていく。
「……杏寿郎さんは案外、秘密が多いのね」
「うーん。そのつもりはないが、いつの間にかそうなってしまう」
「それも杏寿郎さんらしいけど」
「らしい、とは?」
「杏寿郎さんらしいって言うのは、その……いいなって思うってこと」
彼は優しいのだ。優しいから秘密ができる。あのことは黙っていよう。このことは言わないでおこう。そんなふうに思っていたら、たくさんの秘密でいっぱいになってしまう。
「でも、たまにはこうして話してくれると嬉しいな。でないと、杏寿郎さんの宝箱がすぐにいっぱいになっちゃうから」
「宝箱……なるほど、君らしい考えだな」
「わたしらしい?」
「君は鬼殺隊には見かけない種をしている」
「それって、ん……わからない」
「平たく言えば、面白いということだ」
なぜ杏寿郎がこの日にここへ来るようになったのか。その理由もまた彼らしい理由だった。「父上と母上が居なければ俺はここに居ない。なので礼を伝えに来ている」と、杏寿郎は軽やかに言った。
「そして君も。母上のおかげで君にも逢うことができた」
突然、杏寿郎の髪がふわりと舞った。地面に何かがぽとりと落ちる。
「髪紐?」
「切れたのか」
―― 瑠火さんだ。きっと。
は墓石の後ろを覗く。何も見えないのに、もしかしてすぐそこで見ているのではないか。そう思わずにはいられなかった。
「予備は、買いに行かねばな」
「あのっ……よかったらこれを」
店の包はくしゃくしゃになってしまったので入れ替えた。しかし赤い和紙に包んだせいで中身が見えなかった。見るからに女物と見紛うようなそれに、杏寿郎は礼を言った。
「それは君のものだろう。俺のことは気にしないでくれ、家に帰れば何とかなる。」
「そうじゃないの、これは杏寿郎さんに渡したいと思っていて、嘘だと思うかもしれないけど本当なの」
この頃はまだ女性が男性に贈り物をする習慣がなかった。ひとつ違えば相手の機嫌を損ないかねない。その上、先日の一騒動。杏寿郎に迷惑をかけてしまったこともあり、言い出せないまま今日が来てしまった。
「外国はお誕生日を祝う習慣があるって聞いて。それであの日……これを買いに行っていたらあんなことになって、いつ渡したらいいのかわからくなってしまって……だから。杏寿郎さん、お誕生日おめでとうございます」
「俺の、……そうか。うむ、ありがとう! ありがたく頂戴する。今開けても?」
「もちろん」
カサカサと袋の音に緊張した。鮮やかな紅花の色が杏寿郎の瞳に映り込む。
「……大切にする。とても、大切に」
いとおしく思う。今一時が、奇跡の連なりだと思う。
は精悍な横顔を見上げた。
今日という日に、祝福と感謝をこめて。