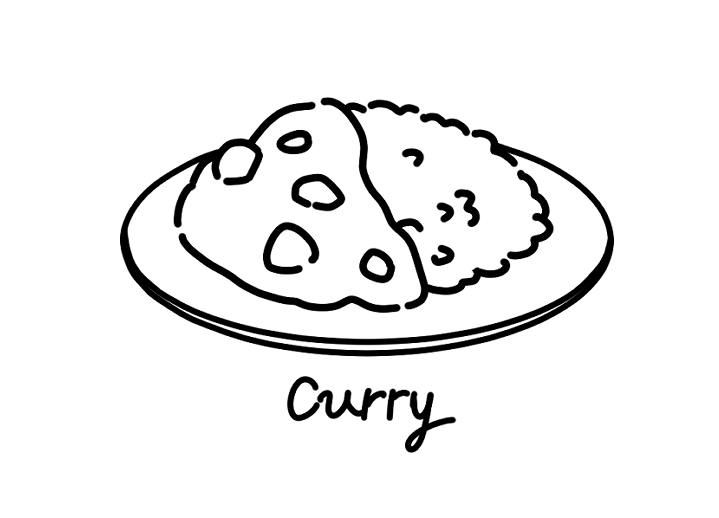あれは中学二年のできごと。その日、私の中でとある概念が覆る。
私が通う学校では新学期早々、野外学習の一環としてキャンプが行われる。クラス替えで馴染んでいない生徒たちが自然にふれあいながら親睦を深める目的もある。30人のクラスメイトは男女混合6班に分かれた。昼食は定番のカレーライス。そこでちょっとした問題が発生する。
「オレ、今度柔道の試合があるんだ」
「わたしもヴァイオリンあるんだよね」
「オレも野球のピッチャーしてるからさぁ」
5人中、3人が指先を理由に包丁を握ることを拒否したのだ。みんなでカレーを作って楽しい思い出も作る――というミッションが危ぶまれる事態が勃発した。残ったのは私と煉獄くんのみ。作るのはフレンチでもイタリアンでもない、ごく一般的なカレーライスなのだから、おそらく問題はないと思う。それに、たかが中学のキャンプのカレーで未来のオリンピック選手やヴァイオリニスト、日本を代表するメジャーリーガーかもしれない3人を潰すわけにはいかない。それだけならまだ良かったのだけれど、
「先生ー、3班のピーラーがありませーん!」
私は包丁でじゃがいもを剥けない。人参も剥けない。ピーラーが無い私はたちまちポンコツに成り果てる。さすがにお米とぎに4人も必要ない、付け合せのゆで卵を監視すると言っても多くて二人、事足りる。圧倒的な人員不足はまな板の上にある。つまり、煉獄くんが頼みの綱だった。私は彼をちらりと横目で見て、包丁を手にした。
じゃがいもと包丁を手にした私の手は小刻みに震える。だけど副班長である私ががんばる他ない。そうしなければ私達、3班のお昼は塩なしおにぎりになってしまう。さすがにそれは気まずい。親睦どころか谷底より深い溝ができそうに思えた。
「じゃあ、私が……」
「僕も切りますよ、さん、それ貸してください」
黙って様子を見ていた煉獄くんは、さっと包丁を手に取った。
煉獄くんのお兄さんは高等部で歴史の先生をしている。顔もそっくりなので入学するなり学年中で噂になった。なので、それはみんなが知っていることなので、特に問題はない。だけどそれが今のクラスでは少々難を作っているのも否めなかった。煉獄くんは休み時間にいつも教室で本を読んでいる。お調子者の男子たちと騒がしく廊下を走って冨岡先生から叱られるのも無縁。誰が見てもとても静かな男子という印象だろう。なのでなんとなく、ちょっと話しかけづらくて。心なし、私が彼を避けていたのは否定できなかった。きっと煉獄くんも気づいていたと思うけれど、そういうことをおくびにもださず、快く包丁を握っている。
スルスル剥けていくじゃがいもと人参、綺麗に皮が剥がれた玉ねぎ。それらを私が切った。煉獄くんはただ黙々と簡単にやってのける。私はこの時の煉獄くんはこの3班で、いや、クラスで一番輝いていたように思う。いち早くテントを張った男子よりもなによりも。
「煉獄くんってさ、料理上手だね。いつもご飯作ってるの?」
「時々母を手伝っているだけです」
「どうして敬語で話すの?」
「あっ、これはクセで……」
兄の友達がよく家に遊びに来るので。と、控えめに言った。それから「確かにちょっとヘンだな」と、煉獄くんは笑う。それにしても煉獄先生のお友達って……。
「えっ、も、もしかして、宇髄先生とか不死川先生とか家にくるの?!」
「まあ。あ、これ秘密ですけど」
「え〜〜っ!! でもそっか、そうだよね、うんうん」
衝撃を飲み込みながら、プライベートを楽しむ先生たちについて興味が湧く。いつもアレコレ厳しい先生たちが笑いながら話題のドラマの話や美味しいお菓子の話をしている姿は想像できない。それを煉獄くんは知ってるんだ。
「よかったら、今度の土曜うちに遊びに来ませんか? たこ焼きパーティーするって言ってましたよ」
「えーっ! いやいやいや、そんなっ、でも」
と言いつつ、好奇心には抗えない。
「本当にいいの?」
「ええ、特別に」
煉獄くんはそう言った。特別。私だけ特別。
「あ、でも家に来たらみんな煉獄なので……」
「あっそっか、じゃあ千寿郎くんって呼ばなきゃ!」
「そうですね」
ほかにも千寿郎くんは私に色々教えてくれた。カレーの初めは強火が美味しいらしい。
このキャンプの醍醐味を存分に発揮したのは私達だったのかもしれない。この日以降、私の好きなタイプは「スポーツができる人」から「料理ができる人」へ変わった。後日「千寿郎が女の子連れてきたぞ?!」なんて、先生たちがお騒ぎするとはつゆ知らず。私は呑気に土曜日を待ち遠しく思っていた。そしてこの経緯を遠慮もせず根掘り葉掘り尋問する先生たちへ、千寿郎くんは平然と述べたのだ。
「キャンプで親睦を深めました」
すっかり大人しくなった先生たちを、私は初めて目にした。