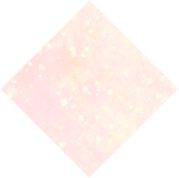第一話
「嫌です……」
こらえた雫がぽろぽろとの頬を伝った。娘の顔を見て、の母、晴子は怪訝な顔をする。
「何が、嫌なのですか」
答えらずはうつむく。実母の無愛想な物言いに、握られた手を振りほどかれはしないかと心配になった。
どれくらい歩いただろうか。路面電車はおろか自転車すら見当たらない。見えるのは、つい今しがた後にした大きな屋敷と知らない建物ばかりだ。めそめそと泣き始めた我が子を見て、晴子は続ける。
「」
「はい」
「今朝、あんなにはしゃいでいたのを忘れたのですか?」
「……いいえ」
仕立てたばかりの洋服を着せてもらい、靴を履いた。手土産にと滅多に立ち寄らない洋菓子屋へ足を運び、シュークリームを買った。自動車に乗るのも久しぶりだった。まだ家を出て間もないというのに「どれくらいで着きますか?」「どのようなお屋敷でしょうか」とはきょろきょろと辺りを見回した。あまりにもしつこく聞くものだから「お止めなさい、はしたないですよ」と静かに晴子の雷が落ちる。それでも、の足取りは軽かった。気分は落ち込むどころか最高潮だった。
ただ、あの時は知らなかったのだ。
それを訴えたところでどうしようもない。しかし、一度溢れた涙を止めることもできない。
「私はお返事をしたのを聞きました」
「……はい」
は唇を噛みしめる。
『さん、よろしくお願いいたします』
母親とはまた違う、凛とした声に背筋が伸びた。は学校でも出さない大きな声で返事をした。「良いお返事ですね」とくすりと微笑む女性。は母以外にあのような眼差しを向ける者を見たことがなかった。「お手を」と差し伸べられた手をにぎり、何かがすとんと落ちた。
それが、門を出た途端にこの有様だ。
幼子のように母にハンカチで顔を拭われながら、は自分の置かれた身を感じていた。

あれはが七歳の頃。その言葉は突然だった。
「あなたに会わせたい方がおります。」
時は明治後半。長きに渡り続いた戦国の世が終わり、新しい文化が根付き数十年の月日が過ぎようとしていた。婚姻というものに自由が認められて日は浅い。大恋愛の末に想いの人と添い遂げるのは創作物が主であり、願いは叶うもの、叶えるものと言われてもそう上手く運ばない。この世に生を受け、産声をあげ、初めて母の腕に抱かれるよりも早く婚家が決まるというのは珍しいことではなかった。そうでなくとも本人の意を反し、いつの間にか縁談が決まっているというのもよくある話だった。
つまりそれは、今年から学校へ通いだしたの身にも起こり得ることだったのだ。
「くれぐれも失礼のないように。いいですね?」
「はい、お母さま」
路面電車と自動車を乗り継ぎ、が晴子に連れられ屋敷へ向かうと、すでに外で出迎える人の姿があった。柔らかな風がその者の黒髪をさらう。
「ようこそいらっしゃいました」
「お出迎えいただき、ありがとうございます」
大きな屋敷を目の前には密かに胸を高鳴らせた。母に習い、も深くお辞儀をした。
部屋に通され、行儀よく座り、前を向いた。
の隣には晴子が、そしてテーブルを隔てた先に、先程出迎えた人物が座った。香の匂いがする。藤のように、そして、ほのかに甘い。
「はじめまして、さん。杏寿郎の母、瑠火と申します」
「はっ……はじめまして」
この時のの心境といえば、学校で教師に当てられる前と同じだった。どんな質問がとんでくるのだろうと随分警戒したものだ。だか、蓋を開けてみればそれが不要な心配であったと知る。
これといって取り立てて言うほどのことはない。好きな食べ物は何か。得意なことはあるか。学校は楽しく過ごせているか。そのようなことを聞かれ、は正直に答えた。
しかし、ショートケーキが現れてからというもの、の意識はそれに釘付けとなっていた。母たちの談笑も秋風と一緒に流れていく。
「では、さんより一つ上になりますね」
「そうですね。ご立派でいらっしゃるのでもっと離れているものかと思っておりました」
畳の香る一室。そこにぽつんと現れたそれは特別に際立っていた。真っ赤な苺とこんがりと狐色に焼けたクッキー生地がたまらなく魅惑的に見える。
「どうぞ、お召し上がりください」
の手がひくりと動く。しかし、
―― 卑しい子だと思われるかもしれない。
その思いがを止めた。なかなか手を付けようとしないを瑠火は不思議そうに見る。晴子も同じくを見ていた。
「もしかして、甘いものは苦手だったかしら?」
「だ、大好きです、いただきます」
フォークを持つ手が震えた。カチカチと皿が鳴らないように気を配る、一口、ぱくりと頬張った。ザクザクとした食感、苺のジャムが口いっぱいに広がる。
「おいしいです」
ショートケーキは思いの外手こずった。食べ終えるのに必死になっていたは、突然の「お入りなさい」という声に心底驚いた。前を見たはさらに驚く。
その声に呼応し襖の奥から現れたのは、燃えるような髪と凛々しい眉、今にも吸い込まれそうな大きな瞳の少年だった。その瞳に捕らえられ、は密かに息を呑む。
「煉獄杏寿郎と申します!」
こちらが名乗るより先に、杏寿郎はハキハキとした声で自己紹介を始める。勢いに押され、はすっかり話す頃合いを失った。思わず母の顔を見上げ助けを乞うが、晴子は知らぬ存ぜぬと言ったところで全く気に留める様子もない。そうこうしているうちに、
「杏寿郎、母たちは話がございます。外で遊んでいらっしゃい」
と、半ば強制的に中庭に飛び出すことになった。
「行こう、こっちだ!」
杏寿郎に手を引かれ、は庭へと駆け出した。
庭は紅葉が茂り、銀杏の葉がひらりと空を舞った。けれども、時季らしからぬ陽気が春を思わせ、白昼の空想に居るようだった。
「君は何がいい、好きな遊びはあるか?」
しかし、遊ぶといっても初めて会った少年と何をしていいのかわからない。というのも、は年の離れた姉が居るが、男兄弟はいなかった。学校でもこのような男子は見たことがない。男子の遊びに女子が加わることは許されないことだった。男は活発に、女はしおらしく、というのが校風である。
戸惑いながらもの頭の中は忙しく動いていた。
男の子が好きな遊びは何だろう。かくれんぼは二人ではつまらないし、得意のおはじきも今は手持ちがない。玉砂利のない広い庭、石蹴りや駒回し、メンコをするのはさぞ楽しいことだろう。
―― 杏寿郎さんは何がお好きだろう。
だんまりとなったを見て、杏寿郎は何を思ったのか別室から一本の竹刀を持ってきた。と距離をとり、一振りする。素早く振り下ろされ、空を切り裂く音がする。目の前で様々な型を披露されるが、どれもの知らないものばかりだ。
「次がイチの型になるものにございます!」
が学校で得たのは、御歌、琴、縫い物だけではない。年の離れた姉、早熟な学友たちによって知らず識らずに刷り込まれた『紳士』という者。ツイードの背広を身に付け、牛革の鞄を手にした、彼の人。
煉獄杏寿郎という少年が想像とは大きくかけ離れていたのは言うまでもなく、は立ち尽くし唖然とした顔で見続けていた。もはや自分がなんのために煉獄家の門を叩いたのか忘れかけていた。その時だった。
「あっ!」
素っ頓狂な声がし、くるくると竹刀が舞い上がった。気づいた時にはの足元に転がっていた。
「すまない!」
慌てて杏寿郎が駆け寄るが、一足遅かった。カランと転がった竹刀の音は障子を通り越し、しっかりと母たちの元まで届いていた。
「まあ!」
事態を悟った母たちが駆け寄ってくる。「申し訳ありません」「大丈夫です」と双方のやり取りを聞いていただったが、「お母さま、違うのです」その一言が出てこない。さっきからずっとだ。まるで自分の体が別のものになったように変だった。
「杏寿郎」
瑠火の声だ。先程のまろやかな声と打って変わった重たい声に、はどきりとした。そして、杏寿郎を見たは同情した。申し訳なく思った。杏寿郎が先ほどまで熱く型を見せていたとは思えないほどに青い顔をしていたからだ。声をかけなければ、と一歩踏み出したはひどく後悔する。
「あっ」
足元から鈍い感触が伝わり、バキッと鈍い音が耳に入る。が恐る恐る足を元見ると、割れた竹刀が視界に入った。
—— くれぐれも失礼のないように。いいですね?
出かける前に言われた一言が、の思考を埋め尽くす。
障子の奥からふにゃりとした猫のような声がした。それが引き金となったのか、終いには屋敷中に響き渡るほどに大きくなり、ついに石のように固まった杏寿郎を見て、も微動だにできなかった。

「何をしているのです、早くお乗りなさい」
路面電車に乗り込む足は鈍く、上手く足がかからない。見かねた晴子がの体を抱えふわりと体が軽くなり、ようやくそれに乗りこんだ。ガンガンと頭が痛むのはひどく揺れるせいだろう。一時間ほどの滞在だったが、校庭を走り回った後のように疲れていた。
「」
「はい」
「もし本当に嫌というのなら……私は次で降り、頭を下げて参ります」
は眼をまん丸にして母を見つめた。人に優しくすること。嘘をつかないこと。自分で決めたことは守ること。そのように言ってきた母が、初めて覆す発言をしたからだ。
本当に母が言ったのだろうか。
は心の中で反芻する。
大人が頭を下げること。それがどれ程のことか、なりに理解しているつもりだった。しかも、粗相をしたのは自分の方だ。それがどうしてそのような言葉になるのか。少なくとも、断る側ではないはずだ。
「どうしますか?」
瞬時に杏寿郎の姿が目に浮かんだ。そして次に杏寿郎の母、瑠火の顔が浮かぶ。
確かに嫌とは言った。嫌、本当に嫌なのか。
は何度も自問した。心底嫌かと問われると少し違う。けれども、今のにはそれ以外の言葉が見つからない。あの後、あの子はどうなったのだろう。のもやもやとした気持ちは晴れないままだ。
だが、これを言ったら二度と引き返せはしない。この路面電車のように一度乗り込んだ以上、目的地まで途中下車することはできない。生まれてこの方、両親に言われるがままに従っていたは、ガタガタと揺れる電車の中で大きな選択を強いられている気がした。
「……い、嫌ではありません」
この答えが正しいものであったか確かめようと、そっと母の様子を窺う。しかし晴子は目をつむり口を結んでいた。もしかすると、ころころと変わる娘の言葉に嫌気がさしているのかもしれない。そうしていると、次の停留所が見えてきた。
閉じていた瞼がゆっくりと開く。そして、じっと前を見据えた晴子は「わかりました」と一言述べたのだった。