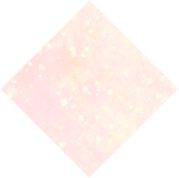第二話
杏寿郎は折れた竹刀を見て考えあぐねていた。
今まで竹刀がすっぽ抜けることなど一度もなかった。もし、少女に当たっていたらどうなっていただろう……。考えついた先は後悔だ。その想像が欠けていたのだ。
「ただいま」
玄関先から聞こえる声に、杏寿郎は新たに背筋を伸ばした。柱合会議に出ていた父が戻ったのだ。普段は嬉しい足音が今日は少しばかり怖かった。
「父上、おかえりなさいませ!申し訳ありません!」
「な、なんだ?」
事態を知らない父、槇寿郎は慌てた。縁側で正座をし、突然頭を下げた息子の言動に何の心当たりも無いからだ。しかし、折れた竹刀に目を遣ると小さく息をついた。原因はこれだと思っているに違いない。
杏寿郎はどこから説明すべきか思案した。まずは竹刀を持ちだしたことだろうか。先にあの少女に竹刀を向けてしまったことを言わなければ。寝ていた弟を起こしてしまったことも、母たちの話を遮ってしまったことも。ぐるぐると一連の記憶が駆け巡る。
「折れてしまったものは仕方がない。だが、道具は大事にしなさい」
「はい!……父上」
普段ならきっぱりとした返事をする杏寿郎がもたつく様を見て、槇寿郎ははたと思い出した顔をした。
「そうだったな。どうだった?」
「はいっ! いえ、はい、いえ!」
「……どっちだ?」
「さんは、二度とお会いになりません!」
杏寿郎はこんなに呆けた父の顔を見たことはなかった。思いがけない言葉だったのだろう。「そりゃあ、……」とその先が続かない。槇寿郎がかける言葉を探していると、瑠火が割って入った。
「申し訳ありません、槇寿郎さん。明日にでも先方へお詫びに伺いたいのですが、家を空けてもよろしいでしょうか?」
「詫び?」
自身と瓜二つの目が、杏寿郎を捉えた。
事情を把握した槇寿郎は、「お前の話は端的すぎる」とため息をついたのだった。

その日の路面電車はとても混んでいた。時折、嗅ぎ慣れない匂いが鼻につく。その妙な匂いが葉巻であると、杏寿郎は初めて知った。
見慣れた平坦な景色がだんだんと小さくなり、代わりに立派な建物が視界に飛び込んできた。遠くに見えていた建物の先端が、想像以上に大きく感じられる。しばらくすると、賑やかな市街の隙間から広い更地が見えた。あまりにも不自然な様に杏寿郎は興味を抱く。
「父上、あれは何でしょう?」
「鉄道。噂の話だ」
大きな駅ができる。人の往来も増える。槇寿郎はそう言って停留所で席を立つ。電車を降り、街中を歩くこと数分。
もうすぐ着くぞ、と足取りを早めた槇寿郎に付いて行くと、建物を見て立ち止まった。
レンガの塀と鉄の門、その奥に洋館が建っていた。目の前の表札には『』としっかり書かれている。間違いではない。しかし槇寿郎は外門を開けようとしない。
「父上、この屋敷は鬼が出るのですか?」
「いいや……」
今は正午、眩しいほどに陽が照りつけている。なのになぜ父がこのような反応をみせたのか、杏寿郎には理解できなかった。
意を決して門をたたけば、驚いた顔をして婦人が出迎えた。
「どうぞ、おかけになられてください」
槇寿郎と同じく杏寿郎が椅子に腰掛けると、テーブルに紅茶とカステラが並ぶ。
「杏寿郎さんは甘いものは大丈夫かしら?」
「はい!」
客間と思しき部屋は、床は板張りで中央にテーブルと椅子があった。足袋の先がもぞもぞするのはおそらく赤い敷物のせいだろう。天井からランプがぶら下がり、壁沿いに漆塗りの棚がある。段違いのその棚には書物や壺が飾られている。中でも杏寿郎の目を引いたのは虎の置物だ。今にも襲いかからんばかりに口を開けている。さっきからずっとこちらを見ている気がしてならない。
「明日、伺おうと思っていたところでした。もはっきりと話せば良いものを。本当に申し訳ありませんでした」
「いえ、頭をお上げください」
杏寿郎はこんなにも慌てふためいた父を見るのも初めてだった。だが謝罪に来たはずが先に謝られてしまったのだから、そうなるのも仕方がない。しかも「竹刀はこちらで弁償いたします」と包を差し出される。何が入っているかは尋ねるまでもなく、
「そのようなものは受け取れません、お気持ちだけで十分です」
槇寿郎のやり取りを耳にし、杏寿郎は背筋を伸ばし晴子の方を見つめた。
今、言わなければならない。あの場で竹刀を振ったことを謝らなければ。杏寿郎はせっつかれたように息を吸う。あの字に開いた口を杏寿郎は既のところで飲み込んだ。
「杏寿郎さん」
「はいっ!」
「直にが帰ってきますのでお待ちいただけますか?」
「……はい!」
杏寿郎は思う。何のためにここへ来たのだろう。何度も謝ろうと考えたが、なぜか調子をくずされる。それは槇寿郎も同じであったらしく、何度か口元が動いては閉じた。そうしているうちに刻々と時間は過ぎていき、やがて時計の針は14時を指した。ゴーン、ゴーンと鐘が鳴った。玄関から物音が聞こえたのは間もなくのことだった。ガタンと玄関の開く音と足音が聞こえ、
「ただいま帰りました!お母さま、お母さま聞いてください、今日は試験で満点を……」
ハツラツとした声はそこでぴたりと止んだ。晴子が事情を話しているのだろう、杏寿郎は重い扉の向こうへ耳をそばだてたが、何を話しているのかさっぱりだった。
そしてゆっくりと扉が開くと、そこには先日の少女が立っていた。だ。ただ、服装は違っていた。ひらひらとした洋服ではなく、花模様の着物姿だった。すると、こちらを見たの瞳がいっそう大きく見開く。
「き、杏寿郎さんのお父さま、はじめまして。と申します……」
そして杏寿郎の顔を見た途端、母親と同様に頭を下げたのだった。「ごめんなさい」と、真っ赤な顔をする女の子を誰が怒ると言うのだろう。なのに今にも泣きそうな顔をして、はこちらを見る。
この子が気にすることはない。そもそも自分が竹刀など持ち出さなければよかったのだ。杏寿郎は何度も思うが、隣でなだめる父を見ても何もできなかった。尻が椅子に張りついたのだと思った。おかしなことに、さっきから立ち上がろうとしてもびくともしない。
「落ち着きませんでしょう?」
晴子は遠慮気味にそう言った。杏寿郎は心の内を読まれたのではないかと思ったが、どうやら故意に投げかけたわけではないようだ。
「このような屋敷になりましたのはつい最近なんです。夫の仕事の関係もありまして、それで」
家は貿易で財を成していた。こってりとした家財の数々は特別な趣味ということではないらしく、杏寿郎には晴子の顔がわずかに恥じているように見えた。
槇寿郎と晴子の話を聞いていると、が様子を窺いながらこっそりと歩み寄ってきた。
「あの……杏寿郎さんはカルタはお好きでしょうか? 」
―― カルタ、正月に読むあれか。
杏寿郎が好きか嫌いかと考える間に晴子が口を挟む。「」とたった一言呼ばれただけだが、少女の口に蓋をするには十分だった。は見るからにしゅんとして、杏寿郎から身を引いた。
「カルタは好きです」
途端にの瞳に光の粒が宿る。それに気づいたのは杏寿郎だけではなかった。すかさず「こちらは構いませんよ」と槇寿郎はこちらを見る。
「すみません、……、少しだけですよ」
渋い声とは裏腹に、優しい眼差しをしていた。

客間を出たは足早に階段を駆け上がる。杏寿郎はその後を追いながら、踊り場の窓が気になり足を止めた。覗き込んだ先に市街が見えると考えていたが、残念ながら見えたのは屋根と樹木だった。
そうしているとの姿がないことに気づく。先には同じような扉が二つある。困り果て立ち尽くしていると、「杏寿郎さん」とが奥の扉からと顔を出した。
「先日はごめんなさい」
部屋に入るなり、はまたも頭を下げた。ずっと気になっていたのだと彼女は言う。
「わたしが正直に話さなかったから、その、……」
「それなら心配ない、叱られてはいない」
叱られるものだろう、あの時杏寿郎もそう思っていた。しかし、たちが帰宅した後、瑠火は折れた竹刀を拾い上げた。そして『どうして叱られると思うのか、よく考えなさい』と静かに言った。すべてを見ていたわけではない。なのに、それだけだった。その理由を考えていたところへ槇寿郎が帰宅したのだ。
「そう……そうでしたか」
すっかり安心したのか、の頬が緩んだ。それを言うなら、と口を開きかけた杏寿郎には言う。
「そうだ、カルタ!少し待っていてください!」
カルタはただの口実ではなかったらしく、は戸棚の中から3,4つ箱を取り出した。そして蓋を開けたはそれを不揃いに並べる。
「杏寿郎さんはどれがお好きですか?」
予想もしない問いかけに杏寿郎は考え込んだ。
「む。どれも美しいから選べないな!」
美しいのは本当だった。だが、カルタは歌を読み遊ぶものだ。けれども、はずっと絵柄を眺めていて、一向に「はじめましょう」と言わない。その代わりに「わたしはこちらを気にいっております」「こちらは色が好きです」と杏寿郎に話して聞かせた。
杏寿郎は意外だった。先日はずっと黙っていたので、てっきり彼女は口が利けないのだろうと思っていた。遊ぶにしても女の子の遊びに詳しいわけでもない。ならば一番熱を注いでいること教えようと竹刀を持ち出したのだが、まさかあのような事になるとは思わない。とんだ誤算であった。
集まったカルタは祖父母や叔父からの贈り物だと言う。
カルタは一人で遊べない。なのでいつも眺めているのだとは言った。他もあるのか尋ねると、は喜々とした顔で戸棚の中を広げてみせる。どれも似たようなものだったが、一つだけ開けようとしないものがあった。
「それは?」
「あっ、これはいけません!」
は慌てて『おばけかるた』に風呂敷をかぶせ、引き出しの奥へ押し込んだ。一度も開けてないのだと真剣な顔をして言う。よほど大切なものかと思いきや、「飛び出してきたら大変だもの……」と眉を寄せ心配そうにする。それがあまりにもおかしくてたまらなかった。くつくつと胸の奥で笑いが起きた。
「そうか、君は怖いのか」
「杏寿郎さんは怖くないの?」
「怖くない」
「うそ、本当に?」
「なんなら今開けてみてもいい!」
「えっ、やだ、ぜったい開けないで!」
絵を見たくないのかと尋ねれば、見たいとは言う。しかし、開けたくないとなんとも矛盾したことを言った。
「じゃあ、今度うちに来たら良い」
「杏寿郎さんのお家に?」
「そしたら飛び出しても怖くないだろう」
もし、飛び出しても道がわからなければ帰りようもない。この部屋にはたどり着けない。杏寿郎はに説いた。
「……うん!」
頷いたがそれはそれは大切に風呂敷に包んでいるから、これまた杏寿郎はおかしくてたまらなかった。笑うのは失礼だと口を閉ざしたが、しばらくの間くすぶっていた。
それ以外にもこの部屋は様々な物があった。煉獄家にはないものばかりで杏寿郎は物珍しく思った。ほとんどが姉のお下がりだとは言う。実姉は遠方に住んでいて、時々手紙を書くのが最近の楽しみだと。
「これは?」
「これはね、おばあさまから頂いたの」
杏寿郎は灯篭のような形をしたそれを上からそっと覗きこんだ。外側が黒く筒状になっていて、内側に絵が描かれている。絵柄は兎のようだ。ほのかに香の匂いがする。
「違うよ、横、この隙間から覗き込むの」
「あ、こっちか!」
「そのまま見ていてね」
が縁を指で回すと、中の絵柄が動き出した。止まっていた兎はぴょんぴょんと跳ねる。止まっては跳ね、止まっては跳ねると繰り返す。速く回すほど速くなる。大人しくなったり騒がしくなったり。
まるでのようだ。そう思うと収まった笑いがこみ上げる。
「ははっ!」
「そんなに面白い?」
「面白い!」
しばらく回転覗き絵を堪能し、知らないものはどんどん訊いた。杏寿郎がいくら言ってもは嫌な顔をしなかった。全部答えがかえってくるものだから、最後までその調子だった。
「、降りて来なさい」
一階からお呼びがかかり、展覧会はそこでお開きとなった。屋敷を出る際、槇寿郎は風呂敷を持っていた。さっきの余韻を引きずったまま杏寿郎は父に問う。
「父上、それは何ですか?」
「手土産だ」
槇寿郎は妙な顔をした。それを見て、杏寿郎はふと思う。謝りにきたのではなかったか、と。
遠出など、と買って出た父を何度も母は止めた。その理由をなんとなく理解する。帰宅後、杏寿郎が謝れなかったことを伝えると、瑠火は眉を下げ「そうでしょうね」とくすりと笑った。