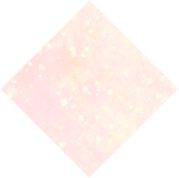第三話
どうしてこんなに小さいのだろう。どうしてこんなに柔らかいのだろう。どうしてこんなにも温かいのだろう。
煉獄家を訪れたは一室に入り浸っている。
甘い匂いの正体は、赤子の匂い。
はすっかり夢中になっていた。飽きもせず、口を開けば「かわいい、かわいい」と言うに杏寿郎が加える。
「、かわいいも良いが、かっこいいの方がより喜ぶだろう!」
千寿郎は弟だから、と杏寿郎は言う。まだ歯も生えていない赤ん坊にどっちがいいかと尋ねても、答えが返ることはない。それでも話をするのが楽しくてたまらなかった。
「でも、かわいいよ、綿飴みたい」
「綿飴は柔らかすぎるかもしれないな」
「じゃあ、杏寿郎さんは何だと思う?」
「大福餅!」
杏寿郎に弟がいるなんて知らなかった。がそう言うと、晴子は話していたでしょうと呆れた顔をした。そうだっただろうかとは考えたがまったく覚えていない。おそらく話していたのはショートケーキに苦戦していた時だろう。
「なんのお話をしているのですか?」
眠る千寿郎を眺めていると、楽しそうですねと瑠火が顔をだした。「母上!」と弾かれたように杏寿郎は振り返る。
「千寿郎が大福餅のようだと話していたところです!」
は杏寿郎に視線を向けた。あまりにもはっきりとした言葉に、言い出しっぺのはひやりとした。瑠火は一瞬驚いた顔をしたが、「まあ」と目尻を下げた。その顔を見てはほっとする。そして、ますます目の前の温かい存在が愛おしく見えた。もちもちとした頬、ぷっくりとした唇。小さな爪。気がつけばまた食い入るように見ている。頭の先から爪先まで。街で見かける負ぶわれた赤ん坊とは違って見える。
「抱いてみますか?」
想像もしていない言葉に、は慌てて飛び退いた。
とっさに思い浮かんだのは大福餅だ。手に触れてとろんとする。一口食べると形がくずれてしまう。茶の湯の師に「さん。大変お行儀が悪いです」と言われるのだが、いつまで経っても直らない。そんな自分が抱いたら、この子はどうなってしまうだろう。
「いっ、いいえ!こわしてしまいます!」
とてもじゃないが抱っこなどできはしない。はふるふると首を振った。
すると杏寿郎はきょとんとした。その隣で瑠火は好奇心と恐怖心の間で揺れるに諭すように言う。
「大丈夫です。人はそう軟なものではありません」
しかし、には想像もつかないことだった。しっかりと首と頭、尻を支えること。首も座っている、大丈夫。そう言われても、そうは見えないのだ。
「ほら、こうすると怖くないでしょう?」
「あの、……」
結局、ほとんど瑠火が抱いていて、抱き上げるというより触れただけだった。だが、それでもには十分だった。
「杏寿郎もさんもこうして育ってきたのですよ」
すると千寿郎の顔がくしゃりと歪んだ。かと思えば、たちまち火が付いたように声をあげた。この小さな体のどこにそんな力があるのかと思うほどに、力いっぱいの泣き声だ。なぜ泣いているのか分からずうろたえたは「腹が減ったと言っております!」という杏寿郎に感心する。
「どうしてわかるの?」
「声だ」
「声……?」
千寿郎は腹を空かせると一段と大きく泣くらしく、瑠火に抱かれ出て行った。杏寿郎はそのうちわかるようになると言うが、やはりそうは思えなかった。赤ん坊に慣れているいないの話ではなかった。そもそも、杏寿郎のように四六時中一緒に居るわけではない。それに彼とは決定的な違いがある。杏寿郎は兄だ、兄弟だ。どんなに愛おしく思っても、それに並ぶことはできない。
部屋が静かになると、杏寿郎は待ってましたと言わんばかりにに言った。
「、早く開けよう!」
本題を切り出した杏寿郎に、は尻込みする。
「もう少し経ってからでいいんじゃないかな……」
「そんなことを言ってると日が暮れてしまうぞ!」
今日こうしてが煉獄家にいるのは、単に遊びに来ただけではなかった。出張に出ていたの父が横浜から戻る知らせが入り、急遽晴子が駅まで迎えに行くことになった。当然、も一緒に行くつもりでいたのだが、取引先に寄るというもので少々事情が変わってきた。正月でもないのに一家総出で行くのは憚れると判断したのだろう。日が暮れるまでには家路につけるよう、晴子が迎えに来ることになっていた。
は煉獄家を訪れる際、鞄に入れた物があった。カルタだ。今日の本題は赤ん坊の子守ではなく『おばけかるた』なのだ。しかしながら、はどうにも気が向かなかった。
「うん。でもね、その……」
「じゃあ、そのカルタはずっとそのままだな」
杏寿郎は声をあげて笑う。は不思議でならなかった。箱には『おばけかるた』としか書かれていない。何が飛び出してくるか分からない。なのにどうして怖くないのだろう。男の子はみなそうなのだろうか、とは思う。
しかし、杏寿郎の言うように開けないことには絵柄を見ることができない。開けるのなら昼がいい。ずっと封を開けずにいるのも、それはそれで怖かった。
杏寿郎とは陽の当たる縁側に腰掛け、その間にカルタを置いた。
「じゃあ、いい?開けるよ?」
「ああ」
胸を高鳴らせ、は蓋を開ける。しかし、瞼はぎゅっと閉ざしたままだ。
「杏寿郎さん、どう……?」
「どうもない」
「本当?」
「本当だ!」
杏寿郎の小気味良い返事を聞き、は恐る恐る目を開けた。
「うわっ!」
ぱっと視界に入ったのは杏寿郎の大きな瞳だった。
「どうだ!」
「どう……」
カルタは、と視線を落としたは拍子抜けする。どんなに恐ろしいものだろうと思っていたが、よくあるカルタだった。これに怯えていたなんて、とは少しばかりがっかりした。
「おばけが飛び出さなくてよかったな!」
「そうだね……ふふっ」
が笑うと、杏寿郎も笑った。
秋晴れの空の元、庭先で雲雀の声がする。空も風も鳥も、一緒になって笑っているようだった。
初めて会ったあの日、どうして竹刀を持ち出したのか理由を尋ねると、杏寿郎は「他に思いつかなかった」と言った。
「本当はわたし、石蹴りがしてみたかったの。でも、洋服はひらひらしているでしょ?」
「たしかにあれでは遊べないな」
「それにね、まさか竹刀が飛んでくるとは思わないでしょ?」
「俺も飛ぶとは思わなかった」
「わたしも踏むとは思わなかった。それで、なんだかお団子が喉に詰まったみたいになって……」
もし、スエードの背広や学帽を被った“彼の人”であったなら、こんなにも心躍らせることはなかっただろう。
もちろん、この時は自分が嫌だと言ったことなどとうに忘れていた。
「杏寿郎さんはお父さまとそっくりね。千寿郎くんも」
先日、国語の試験で満点を取った日のことだ。いつもなら見計らって外門に出ている母親の姿がなく、はいち早く報告をしようと玄関から大声で呼んだ。すっかり浮かれていて、玄関の履物はまったく視界に入っていなかった。
客間から出てきた晴子はしっと口元に手を当てた。「煉獄さんがいらしてますよ」と言われ、は考えた。煉獄さんと言ったら、あの煉獄さん。ひょっとしたら、他の煉獄さんかもしれない。レンゴクさん、れんごくさん―― 。
しかし、「杏寿郎さんにきちんと謝りなさい」と釘をさされ、確信する。「お父様にお会いするのは初めてですから、きちんとご挨拶なさいね」と、鞄を降ろされ、着物を正され、髪を撫でつけられ、頬を撫でられたは扉を開けることとなった。
客間で見た時の衝撃たるや。
が瓜二つだと言うと、杏寿郎は言った。
「俺は父上のようになりたい」
父上のような立派な剣士に、炎柱になるのだと。杏寿郎は誇らしげに話す。
「素敵な夢ね」
「は何になりたい?」
なりたいこと。夢はなんだと言われてもはピンとこなかった。杏寿郎のようにはっきりと言葉にできることは何もない。
「わたしはまだわからないなぁ」
「そうか、はのんびりだな」
「杏寿郎さんはちょっぴりせっかちだね、お煎餅もぱくぱく食べちゃうし」
おやつに出された煎餅をうまい、うまいと頬張る姿を思い出す。「もどうだ!」と醤油、海苔、塩と次々に勧められるが、口の中は間に合っていて、何度も断ることになってしまった。
「栗鼠だったらたくさん食べられるのに」
「それを言うなら兎だろう!」
その言い分には首を傾げたが、杏寿郎はそれしかないと言い張った。ならば杏寿郎は、千寿郎はと話は進み、あれでもないこれでもないと話は尽きない。
心が弾んだ。まだ見ぬ時に思いを馳せた。
「千寿郎が大きくなったらカルタをやろう!二人より三人の方が面白い!」
「うん、それまで大事にしまっておかなくちゃ」
「また風呂敷に包むのか?」
「もちろん。寝てる間におばけがよみがえったら困るもの」
半分は冗談、半分は本気だった。今は良くても夜はどうだか分からない。それを言うと杏寿郎は笑うだろう、はそう思っていた。
「貸してみろ。そんな結び方ではすぐに解けてしまう」
「あっ、うん」
「……うむ。これでよし!」
弁当のようにがちがちに包まれたカルタを見て、杏寿郎は完璧だと満足そうに言った。
「ありがとう」
はそれを大切に鞄へしまった。怖いものが楽しみへと変わる。
次に風呂敷を開けるときは、この縁側はもっとにぎやかになっているだろう。
「御免下さい」
門の方から声がする。
日が落ちる前に、という約束が急に惜しくなった。
「の母上だ。はい、ただいま!」
「あ、まって!わたしも」
は杏寿郎の背を追った。小さな足音が廊下を駆けていく。
「母上!の母上が、晴子さんがお見えになりました!」
お土産だと晴子に手渡された大福餅の袋を見て、二人はくすくすと笑った。