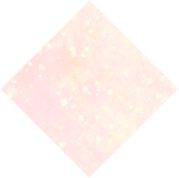第四話
あれから一年と半月が過ぎ、の日常に“休日は煉獄家へ通うこと”が加わった。時間帯は様々で、午前に顔を出す日もあれば午後から顔を出すこともあった。今まであまり昼を跨ぐことはなかったが、最近は朝から長居することが多くなっていた。
「食べることは生きること。心を豊かにするの」
昼時、炊事場に立ったはふうふうと竹筒を吹く。「釜にも癖がありますからね」と瑠火の助言を元に、試行錯誤を繰り返して幾度目。
《食は生きる源である。食は心を豊かにするものである。》家庭の教科書に書かれたその一節を、はとても気に入っていた。
初めは何度も失敗した。ある時は砂のように硬く、ある時は粥のように柔らかい。硬い米は炊き直せばよいが、柔らかい米はどうしようもなく、真夏の昼に熱々の雑炊を食すのは苦行のようだった。それでもありがたいことに、「こんな日もありましょう」と瑠火は咎めることをしなかった。杏寿郎は汗を流しながらいつもと同じく何杯もお代わりをしたが、さすがに暑かったのだろう。後で水場に駆けて行ったのをは目撃した。喜んで食べていたのは千寿郎である。彼の食事はいつもゆっくりだが、程よく冷めたそれはぺろりと平らげた。
そうだ、全部冷やし雑炊にすればいいんだ。がそう思った時にはすでに釜は空になっていた。
「初めちょろちょろ中ぱっぱ、ブツブツいうころ火を引いて」
「ジュウジュウ吹いたら火を引いて、ではなかったか」
「ブツブツだよ?」
「そうか、俺はジュウジュウと教わった」
そんな事を言っていると、ブツブツともジュウジュウとも言えない音がする。は慌てて灰をかぶせた。これ以上火を強めていると、“どこまでおこげで許されるのか”悩むことになりかねない。今日は何があっても失敗したくはなかった。額を拭ったはほっと息をつく。
「グツグツだったかもね」
「ブクブクだったかもしれないな!」
そんなことはどっちでもいいじゃないか。と、ならないのが二人であった。この答えは次に考えるということで話がついた。しかし、「腹が減ったなぁ……」と炊事場に槇寿郎が顔を出し、更に話はもつれ込む。
槇寿郎は家を空けていることが多く、が顔を合わせたのはひと月ぶりだった。今日は外出の予定がないらしく、朝から薪を運んだり力仕事に励んでいた。
杏寿郎が「父上はどう思われますか?」と槇寿郎に問うと、
「『初めちょろちょろ、中ぱっぱ、赤子泣いてもふた取るな』だろ」
ブツブツもジュウジュウもない。そんな音は入らないという槇寿郎の話に杏寿郎とはますますわからなくなった。
「それはそうと、いつもすまないね」
台に並んだ料理を見て、槇寿郎は申し訳ないと言わんばかりに眉を下げる。煮物は晴子が持たせたものだ。魚は買ったものを杏寿郎と一緒に焼いた。片面だけ若干焼きすぎているのはご愛嬌とする。
「いえ、好きでしていることですからいいんです」
以前から瑠火と炊事場に立っていただが、近頃は杏寿郎と一緒に昼の用意をすることが増えた。というのも、このところ瑠火の体調が芳しくない。杏寿郎の母の体があまり強くないことはも聞かされていたが、初めて会った時は全くそうは見えず、気に留めていなかった。目に見えて変化が現れたのは正月が明けてしばらく経ってからだ。暮れから続く寒さに加え、東京では珍しく雪が降った。それが起因となったかは定かではないが、徐々に寝込むことが多くなっていた。
それでも瑠火はが訪れた日は炊事場へ顔を出し、家事を指南することもあった。もしかすると自分の前では気丈に振る舞っていたのかもしれない、と後になっては思う。
何しろ炊事は手がかかる。水を瓶に溜めるには力が要る。釜に水を入れるのも柄杓が、火を使うには薪が。炭を起こすにも火が要った。最近は特に晴子も気にかけている。初めは気を遣わせないためか、「作りすぎたわ」と煮物の類を持たされたが、度々となればそれも使えない。妙な嘘より思い切って「お手伝いさせてください」と言ったのは良かったとは思っている。
「母君に宜しくお伝え願えるかな?」
「はい」
全く苦ではなかった。杏寿郎が稽古に打ち込んでいる間に下ごしらえをし、食事を作る。それはにとって重要なことだった。
槇寿郎が炊事場から出て行くと、はこそこそと杏寿郎に言った。
「美味しく炊けてるかな」
「ああ!うまそうな匂いがする!」
「上手くできたら今日はおにぎりにしようと思うの」
「おにぎりか、いいな。具は何にする?」
「梅とおかか。縁側は暖かいし、そこで食べるのはどうかなと思ったんだけど、……」
「今日は調子が良いみたいだ!」
「そっか、よかった」
の提案に、杏寿郎は大いに頷いた。本当は野掛けをして、外の空気も楽しみたい。しかしそれは難しいことだ。
「ならば風呂敷がいるな」
「風呂敷?」
「ただ皿を並べるのは味気ない!確か居間の戸棚にあったはずだ、探してくる!」
「うん!ありがとう」
全ては愛する人のため。美味しいごはんを食べれば元気になるに違いないとは思っていた。杏寿郎も同じであったと思うが、本当のところは訊けはしなかった。
「杏寿郎、何を探して……は? 風呂敷?……それは正月用だ、こっちを使いなさい」
風呂敷を敷くのなら大皿より重箱と言い出したのは誰だったか。初めは「縁側で昼餉?」と疑問を抱いていた槇寿郎も文句を言わなかった。
調子が良いと言ったのは本当らしく、縁側にやってきた瑠火は顔色が良い。「今日はおめでたいことでもあるのかしら?」と重箱を見つめた。「杏寿郎たちが、たまにはこういう日もあっていいんじゃないかって話になってな……」と、妻に説明する槇寿郎の様は他人事を装っているが、その声色は明るい。
「そうですね、たまには良いものですね」
花火の季節としては遅く、紅葉にはまだ早い。そんな日だった。
「さん」
杏寿郎の隣で一緒になって煮物をつついていたはあわてて箸を止める。
「お料理、上達しましたね」
瑠火の言葉には頬が熱くなった。初めて褒められたのだ。
「あの、煮物はほとんど母が作りまして、鯛の塩焼きは杏寿郎さんが焼いてくださったので、わたしはそれをひっくり返しただけで、風呂敷は杏寿郎さんと槇寿郎さんが出してくださいまして、その……ありがとうございます」
言わなくともわかるであろうことも全て話した。瑠火を目の前にすると、どうしても黙っていられないのだ。桜の花が散った風呂敷を見て、瑠火は花見のようだと言った。
「でも、おにぎりはさんですね」
「はい」
「それで、こちらの大きなおにぎりは杏寿郎ですか」
「はい!」
杏寿郎の声は弾んでいた。時に厳しく時に優しく。瑠火の言葉は芯から熱くする。
「では、しっかりいただきませんとね」
さすがにそれは腹が膨れすぎると槇寿郎が大きなおにぎりを半分に割り、母の半分を千寿郎がねだり、おにぎりはだんだんと小さくなっていく。縁側での時間は屋内で囲むよりもあっという間に過ぎていく。
「もう満腹か?」
手にしたおにぎりがすすまないを見て、杏寿郎が声をかけた。
「あっ、うん、おいしいね」
自画自賛とも気づかずに、はそれを頬張る。
見とれていたのだ。この景色に。
家には縁側がない。よって、松や紅葉、柊やツツジを眺めることもない。出張ばかりの父と一家団欒というのも縁遠い。ふと、自分もここにいてよいものかと疑問が浮かぶ。そして母はこの時も一人で食事をしているのだと気づいた瞬間、はちくりと胸が痛んだ。

「娘を持つ親ならば皆そのようなものです。それを気にしていては嫁になど出せません」
帰宅後。ぐつぐつと鍋を煮込みながら、晴子は淡々としていた。一人きりの食事に何の抵抗もないというからは少々驚いた。特に今日は朝から野菜を煮詰めていてそれどころではなかったらしく、昼はおにぎりを食べたらしい。朝の残りご飯、具は漬物と言った。「何を作っているのですか」と訊けば「ビーフシチューです」と慣れない言葉がでてくる。
「お母さま、これはわたしも作れますか?」
「たくさんたくさん頑張れば作れます。その前にお魚はきちんと焼けましたか?」
「はい、杏寿郎さんに手伝ってもらって、少し焦がしてしまいました……でも、お米はきちんと炊けるようになりました」
仮に今夜の夕食がおでんだったとして、はおでんを作りたくなったかもしれないし、豚汁であれば豚汁を作ろうと思っただろう。
「お母さま、実は今日ね、縁側でお昼をいただいたんです」
槇寿郎さんがいらっしゃって、瑠火さんも、千寿郎さんも、そして杏寿郎さんも、わたしも混ざって、みんなで風呂敷を広げていただきました。お母さまと作った煮物も大変好評で、杏寿郎さんと焼いたお魚も大変好評で、梅干しとおかかのおにぎりも大変好評で。
「お母さまも一緒だったらもっと楽しかったのに」
はぽろりとこぼした。
晴子は変わらず鍋をかき混ぜている。それでも母の耳は娘の言葉を拾っていて、それはなりませんと断言する。
「どうしてですか?」
「私は家の人間ですから」
「わたしも、です」
わたしはだ。
が訴えるように晴子の顔を見上げると、晴子は焚口から薪を数本抜いた後、と同じ目線になるよう屈み込んだ。
「本当は、ビーフシチューよりも覚えることがたくさんあるのだけど……」
は見てはいけない気がした。灰を被った時のように赤くなった晴子の眼は、今にも涙が溢れそうだ。
「は杏寿郎さんたちのこと、お好きかしら?」
「はい。杏寿郎さんも槇寿郎さんも瑠火さんも千寿郎さんも、みんな好きです」
「そうですか。それはよかった、本当によかった……」
一つ一つを噛み締めるように、晴子は言った。
「神様は時にせっかちでいらっしゃる」
晴子は秘め事を話すようにに語りかける。
「いいですか、」
不意に温かい手が頬を包む。そして、晴子はに杏寿郎の母の命が残りわずかということを告げた。そこでは『鬼狩り』という言葉を初めて耳にする。
煉獄家は鬼狩りの一門である。それが煉獄家の生業だと晴子は言った。
「は、あなたは、ささえる人でありなさい」
焚口の中で、薪がごろりと落ちた。
唯一残った一本がじっくりと燃え尽きるまで、はそれを見つめていた。まだ母の手の温もりがあるようで、そっと頬に触れる。
それからまた一年が経とうとしていたある日。
が学校の身支度をしていた朝のことだった。