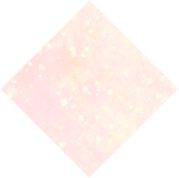第五話
朝霧が出た。
にわかに、杏寿郎はこの家だけが霞んでしまったのではないかと思った。先が見通せず、庭から眺める景色は味気ないものに見える。まるでこの世から切り離されてしまったようだ。
しかし、朝霧は晴れる。
だんだんと陽が昇り、稽古場に光が差し込んでくる。
杏寿郎が朝稽古を終え、人の気配に門へ向かうと、風呂敷を抱えたが立っていた。
「杏寿郎さん、おはようございます」
「おはよう!今日は随分と早いな」
「早く目が覚めたから朝ごはんを作ってきたの。千寿郎くんは?」
「まだ寝ている。もうすぐ起きるだろう」
あの日。
明るかった縁側はすっかり陰り、冷たい空気が漂っていた。桜の風呂敷、重箱を囲ったこと、すべてが遠い昔のことのようだった。
瑠火の訃報は家に伝えられ、晴子とともにはやってきた。黒い着物を着た彼女はすでに目を腫らしていて、目があった瞬間「杏寿郎さん」と言葉を詰まらせた。そんな彼女を見て、杏寿郎は言葉を探した。しかし、いくら探しても頭の中は靄がかかり一つも声にならなかった。泣いてはいけない。そう言い聞かせるのに必死だったこともある。の方もそれきりで、ほとんど口を結んだままだった。
藤の者、近所の者、の母が率先して葬儀の世話役をこなす中、事ある度に大人たちの哀憐の情が杏寿郎たちに降り注いだ。そのさなか、が千寿郎の相手を買って出たことは杏寿郎にとって助けとなった。何しろ杏寿郎には大切な役目があった。朝昼晩、ずっと蝋燭を見張っていた。炎を絶やすことのないように、迷うことのないように、あの世とこの世の道標が途絶えることのないように。
千寿郎は初めこそきょとんとしていたが、やがて長らく物を言わない母親にすがった。そして幾度となく泣きながら母を呼ぶ。その声が切なく、その度に杏寿郎の心を締め付けた。どんなに父が抱いても兄があやしても、泣き止むのは一瞬だ。思い出したように泣き、夜は赤子に戻ったようにぐずる。母という無二の存在には敵わないのだと、杏寿郎はあらためて思い知った。
不安定な千寿郎の相手をするのは骨が折れたことだろう。それでもは嫌な顔をしなかった。「ごめんね、母上じゃないね……ごめんね」と何度も言いながら、子守に徹していた。
杏寿郎は思う。月日が経つのは早いものだと。
最愛の人がこの世を去り、一年を過ぎようとしている。
あれから杏寿郎は必死になって一日を追いかけた。少しでも遅れると置き去りにされ、気を抜くとあっという間に恐ろしい闇へ引きずられる気がした。
だが、いつしかその感覚は薄れ、ゆっくりと今と馴染もうとしている。
千寿郎は以前より物を話すようになった。未だ何かを探す眼差しこそあれど、母上と声に出すことはない。また、も変わらず顔を出した。そのことも、ここに日常が、今があるのだと示しているように思えた。
生きている限り、明日は来る。
変化があるのは、そこに未来があるからだ。
母には敵わない。到底及びもしない。今もそれは変わらない。自身が与えられた温もりを、実弟に与えることは難しい。けれども、兄としてなら—— 。
「あにうえ!」
杏寿郎が振り向くと、千寿郎は慌てて草履を履いた。そしてにこにこと笑みを浮かべ、駆けてくる。
「あにうえ、あねうえ!おはようございます!」
「おはよう!」
「あ!千寿郎くん、おはようございます」
誰が教えたわけでもない。なぜか千寿郎はのことを『姉上』と呼んだ。杏寿郎は「は姉ではない」と度々言って聞かせたがあまりに何度も言うもので、杏寿郎もも根負けした形となっていた。
「千寿郎、紐がぐちゃぐちゃだ!脱げたらみっともないぞ!」
ゆっくりやればできること。しかし今朝はよほど急いだのか、へその位置で結ばれた前紐はゆるく形を成していない。杏寿郎がいつもの調子で笑うと、千寿郎はもたもたと腹を抱え込んだ。紐をいじるものの、きつく結ぶどころかすべて解けてしまいそうだ。ついには、
「うっ、……」
と眉を下げ、助けを乞われては無視することなどできはしない。
「仕方ない!今日は俺が結んでやろう!」
その光景を見て、はふふっと口元を綻ばせる。
「よかったね、千寿郎くん」
ある時、藤の家の者が「千寿郎さんはお利口であられます」と感心していたことがあった。されども、食事はもちろん着替えを覚えさせるにも、最初は何事も一苦労ある。癇癪こそ起こさなかったが、できないと泣くこともままあった。だが、不思議とが来ると教えたことは一人でこなそうとする。この者の前ではきちんとしなければならない。そう思っているのかもしれない。
ゆるい紐、掛け違えた足袋の留め具、小さな恥じらい。すべてが愛おしく、世話を焼くのがこんなにも嬉しいことだと杏寿郎は思ってもみなかった。赤子の可愛さとはまた違う。のかわいいと言っていた言葉が、今頃になって身に沁みるようだった。
「よし、できた!」
「ありがとうございます、あにうえ」
きちんと前紐が結ばると、千寿郎はほっとした顔をした。
「杏寿郎さん、槇寿郎さんは……?」
「父上は二日前から任務に出ておいでだ」
の「どうしよう」と小さな声が杏寿郎の耳に入る。
「父上に用か?」
「あっ、違うの。ちょっと作りすぎたかなぁって……」
風呂敷を抱え直し、の声は尻すぼみになっていく。
「そういうことか!余りは昼に食べればいい、今日の気温なら痛みはしないだろう」
「そうだね、そうしましょう」
は煉獄家に来ると、真っ先に仏壇へ向かう。「おはようございます」「こんにちは」と声にするのはそこまでで、しばらくの間、背筋をまっすぐに伸ばし位牌を見ている。何を話しているのだろう、そう思うこともあったが、杏寿郎は声をかけようとはしなかった。
「わたし、お湯を沸かしてくるね」
「湯なら今沸かしている」
「でもお風呂の方も沸かさなきゃ。そのままでいたら風邪を召してしまいます」
の言葉に杏寿郎はスンと息を吸う。言われてみれば、少し肌寒い。そして稽古着のままだったことを思い出した。
「……すまない!」
「大丈夫。これくらい朝飯前よ!」
「ははっ!それは頼もしい!」
「煉獄の旦那、わたしがすぐに沸かして差し上げますゆえ!」とは風呂釜の方へ駆けていく。
というのも、最近は学校で劇の稽古をしている。普段なら絶対にこんなことを言いはしないが、いよいよ本番が迫っており、煉獄家を訪れる度にこの調子だった。の家は風呂釜を変えたため、演技の練習にはならないと言う。
『杏寿郎さん、わたし風呂屋のおばさんになるの!』
突然が嬉々として言ったので、杏寿郎は驚いた。どういうことかと思えば、それは劇中の話だった。たった一行ほどの台詞らしいが、の熱の入りようといったら。彼女曰く、“普段通りを演じたい”とのことだが、杏寿郎としてはが本番で「煉獄の旦那」と言わないことを願うばかりだった。
それで思い出すのは、先日槇寿郎が帰宅した時のことだ。ずかずかと廊下を進み「杏寿郎、勝手に見知らぬ者を上げるな!」と声を荒らげたことがある。風呂場から戻ってきたは途端に大人しくなった。「……お客様がいらしたの?」とこそこそと言う。当然、誰も来ていない。杏寿郎はそれ以来、ぴしゃりと閉じだ障子の奥で父は何を思っていたのかと想像する。その度に、の演技は父上のお墨付きだ。そう言ってやりたい衝動に駆られた。
「今火を入れたから、杏寿郎さんも炊事場で暖をとって待っててね。千寿郎くんはわたしとお味噌汁をつくりましょう」
は千寿郎をつれて炊事場へ向かう。切って煮るのは、千寿郎は味噌を溶かし入れるのが役目だ。大役だとが言うと千寿郎はとても喜んだ。
杏寿郎が風呂から上がると、既に朝餉の準備が整っていた。しかし、
「……ごめんなさい、やっぱり多かったよね」
は遠慮ぎみに言った。重箱にみっちり詰まっているのは黄金色の稲荷寿司。しかも、二段ある。
「実は、昨晩お父さまが帰る予定で、それが変わったのを知らなくて……」
家と煉獄家。足りないよりは、と釜いっぱいに炊いたのだとは言った。三段目には卵焼きときんぴら、芋を揚げたものと肉料理が詰まっていた。このような和洋折衷の重箱は煉獄家にないものだ。
「この肉は?」
「ビフテキです。焼豚のようなもの、と本には書いてあったけど……もちろん、味は美味しいと思うの。お母さまも美味しいとおっしゃったから」
が持ち寄る料理は時々珍しいものが入っている。それを見ると、杏寿郎は家の洋館を思い出した。
「そうか!しかし、こんなにうまそうな料理を食べられないとは、の父上は気の毒だな」
実に気の毒だと杏寿郎は思った。は昨晩から張り切って下ごしらえをしただろう。帰りを楽しみにして、油揚げを煮たはずだ。ビフテキも手間をかけたことに違いなく、実の娘が丹精込めて作ったそれを食べられないのだから、それを気の毒と言わず何と言おうか。
そこでぐうと腹の虫が騒ぎ出す。杏寿郎はしまったと思ったが、頬を赤らめたのはだった。
「お、お腹空いたね!食べましょう!」
がさっそく取り分ける。手を合わせ、いただきますの声で杏寿郎は椀を手にとった。味噌の風味が食欲を掻き立てる。その傍ら、千寿郎はさっと稲荷を頬張った。
「あねうえ、おいしいです!」
「しかし千寿郎、食事は汁物が先だ!」
「あっ」
「さっそく頬にご飯粒が付いている!」
「えっ」
先に手を付けた弟を、杏寿郎は少しだけ羨ましく思った。もちろん味噌汁に不満があるわけではない。どちらも甲乙つけがたい。しかし、口の中で真っ先に広がる煮汁のしみた揚げの味を想像すると、やはり惜しいことをした気持ちは拭えなかった。
目の前のことを当たり前と思わぬこと。
杏寿郎がそれを教わったのは、千寿郎が生まれる前。炊事場に近寄ることを許されたのは、今の千寿郎と同じくらいの年頃だった。初めは見ているだけ。次は米を研ぐことを許され、翌年は葉物を切ることを教わり、その翌年には薪を焚べることを覚え、火入れを教わった。竹筒で息を吹けば、ぼうっと燃える。吹けば吹くほど燃えるので、思わず杏寿郎は「母上、火も生きているのですか」と言った。そして、
—— 母はなんと言っただろうか。
杏寿郎がはたと考えていると、が様子を窺っていた。なぜかしょんぼりとした顔をして重箱に視線を落とす。
「どうした?」
「ごめんなさい、このお肉、千寿郎くんも食べられるか聞くの忘れちゃって」
失敗した、とは言う。
「しっかり焼いたのなら食べられるだろう。見たところ、牛鍋の肉が厚くなったもののようだ」
「千寿郎くんは牛鍋食べたことあるの?」
の問いかけに、千寿郎は目を点にした。「ぎゅうなべ?」と見上げるそれに、杏寿郎が答える。
「牛鍋というのはその名の通り、牛の肉が鍋に入っている食べ物だ。葱も入っている!豆腐も入っている!醤油と砂糖で甘辛く、ご飯がすすむ!」
「わぁ!」
千寿郎は興味津々にビフテキを見る。
「まって、これは牛鍋じゃないの、ビフテキっていうの。牛鍋はもう少し柔らかくて……わかりました、次は牛鍋にします」
だからこれはビフテキなの、とは言う。そして、またも失敗したと呟いた。千寿郎くん、とが皿を見ると、
「あっ!」
どちらが言ったかわからない。小さな口で肉を頬張る千寿郎に、は困惑し、杏寿郎は笑った。今日は先を越されてばかりだが、行儀の話は目をつぶる。
「千寿郎は舌が肥えそうだ!」
うまそうな料理ではない。間違いなくうまいのだ。

「あの、杏寿郎さん?」
食後の片付けをしていると食器を拭っていたが手を止め、改まった顔をした。
「杏寿郎さんに頼みたいことがあるのですが……」
「うむ。俺にできることならなんでもしよう!」
「その、今日の昼稽古ですが……、わたしも側で見ていても良いですか?」
いつもは昼をすぎると家に帰る。日が落ちる前にという言いつけもあるが、彼女も暇ではなかった。学校の宿題の他にも習字や琴、茶の湯と忙しい。杏寿郎の稽古が日課のように、の日課もそのような習い事で埋め尽くされていた。
師である槇寿郎は不在。近頃は家に居ても相手をしてもらえることが減っていた。打ち合いをする相手はおらず、千寿郎の型を見ながら素振りをするのみ。が武道をしているのなら多少の面白みもあるだろうが、そのような習い事をしている風でもない。まず、杏寿郎はが息を切らして走っている姿を見たことがなかった。運動神経も特別に良いとも言わない。剣より筆が代名詞と言ってもよい。
「それは構わないが、退屈だろう」
「そんなこと……あっ、もちろん邪魔になったらすぐに帰ります。お願いします」
その眼光が思いのほか鋭く、杏寿郎は目を見張る。
がどこまで知っているのか知り得ず、「わたしも剣を握りたい」などと言い出しはしないか不安がよぎる。
「はっきり言うが、は剣士には向かないと思う。それでもなりたいと言うのなら、俺は」
「いっ、いえ!わたしは剣士になりたいわけでは……やっぱり、いけませんか?」
「いけないことはないが……」
さすがにもう竹刀を飛ばすことはないと思うが、千寿郎の場合はわからない。
「ただし、離れた場所に限る。それでもいいか?」
「はい」
「よし!そうとなれば、千寿郎はと見取り稽古だ!」
二人の視線は想像以上にむず痒いものがあった。だが、それも目の前に集中するにつれて気にならなくなった。
竹刀が木刀へ変わり、木刀から本物の刀を持つまでどのくらいかかるのか見当もつかない。それでも杏寿郎は懸命に腕を振る。額から流れ出る汗を何度も拭った。
絶対に手を滑らせてはならない。絶対に離してはならない。
最後の一振りで、杏寿郎は思い出す。
『—— そうですね。不思議なことに、炎は心を込めるほど強くなるのです。』