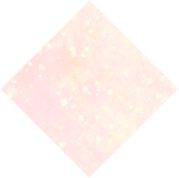第六話
『—— ですから杏寿郎、そのあたりにしておきなさい。ほら、焦がしてしまいますよ!』
杏寿郎が竹筒を吹くことに気を取られていると、瑠火の声が焦ったものに変わった。すると炊事場には炭のような匂いが漂い始め、もくもくと煙が充満する。結果としてご飯は上澄みを食べることになり、茶碗が物悲しいことになった。当たり前だがお代わりもない。杏寿郎にとって当たり前が当たり前でない、最初の日だった。
「それで、釜が一つ駄目になったことがある」
千寿郎とは杏寿郎の手の振りや足さばきに見入っていた。しかし、突如として杏寿郎の手が止まり、『そうだ、米が焦げたのだった!』と稽古場に響いた。あの時のはとんでもないものを見た顔をしていた、と杏寿郎は語る。
「杏寿郎さんがいきなりあんなことを言うから、熱に浮かされたのかと思ったの」
「俺は身体が丈夫な方だ!」
千寿郎は二人を交互に見やり、話を理解しようと努めた。「千寿郎も見ていた」と言われ、乏しい記憶をかき集めてみる。だが、杏寿郎が竹刀や木刀を振るうのはいつものこと。も隣に居たと言われても、炊事にかかると大抵は隣に居る。
千寿郎の結論は、少しも覚えていない。それに尽きた。
「そんなわけで、千寿郎にとって俺は反面教師だ!あれ以上の出来の悪さはない!」
「ちなみにわたしのご飯は砂のようだった!次は粥のようだった!くるしゅうない、少年よ!ワハハッ!」
—— ああ、ついに姉上がおかしくなった。
千寿郎の不安な眼差しを、は違うように捉えたらしい。「大丈夫、今日は息を吹くだけだから」と正気に戻った声で話しかける。
千寿郎がを案ずるのには理由がある。
は小学校の卒業を期に、女学校への進学を余儀なくされていた。受験というものにまだ縁がない千寿郎にはその苦労は未知である。ただ、日々疲弊していく様子にそれが恐ろしいものという認識はあった。「今日は指が使い物にならないの」という日があったかと思えば、せっかく来たのに一言も話さない日もあった。「緑色で口を開けない」という筆談では一生分の茶を飲んだとも言った。
すべては、受験という魔物が姉上をおかしくしている。
その千寿郎の予見は概ね外れてはいなかった。
実際、琴や茶の湯の練習では爆発寸前だったのだ。おまけに自宅には作法の講師が付き、は家に居ながら猫を二重三重にもかぶらなければならなかった。思えば、「先生が寝る寸前まで見ていて、目を開けても見ている」と彼女が言った時から予兆はあったのかもしれない。
それを知ってか知らずか、
「ここに失敗者が二人もいる!なんの心配もない!」
杏寿郎はいつものようにわははと笑う。
そんな二人に背後に立たれ、千寿郎の不安は募るばかりだった。
なぜこのような話になっているのかと言えば、千寿郎は味噌を溶かす係から米を研ぐ係に昇格し、たった今、火を起こす係りになった。
しかし、自ら志願したことを千寿郎は少しばかり後悔していた。竹筒を握りしめ、悩ましげに焚口を覗く。

はじめはそうでもなかったのだ。
いつからか、父、槇寿郎は「女手がないのなら」と言う幾人の申し出を断った。もちろんすべて親切心だが、それも無下にした。「奥様の代わりに」などと言おうものなら男女構わず怒鳴りつけ、二度と来るなと叩き出した。そして、任務がない夜は顔により深い影を落とし、無言で位牌を眺めていた。
杏寿郎が葬儀の日に感じた靄が、槇寿郎の心を覆い尽くしていた。暗雲のように垂れ込めている。
“近寄りがたくなった—— 。”
誰かの囁きが、冷たい風に乗って広がっていった。
やがては給仕を引き受けていた藤の家の者まで何かと都合をつけて寄り付かなくなった。こしらえた作物や衣服の類は届けられるが、それも門まで。槇寿郎が任務に出ている間にこっそりと置き去っている。杏寿郎や千寿郎が庭に出ていると挨拶を交わす、その程度だ。以前と変わらず煉獄家を訪れるのは、ごく限られた者と家の晴子、そしてくらいなものだった。
「千寿郎くん、門にお野菜が届いているけど、どなたがくださったか知ってる?」
「ああ、それは藤の方です」
「フジさんとおっしゃるの?」
「いえ、いつもの藤ですよ」
「そういえば、この前も反物が届いたよね。フジの家の方はたくさん稼業をされているのね」
凄いね、とは感心した様子だったが、千寿郎は違和感を覚えた。時々妙なところがあるとは思っていた。は本当に武道の類に疎く、最近になってやっと型の見分けが付いてきたと言っていた。槇寿郎が出ていく時も、“お仕事”ということがあり、はっとした様子で任務と言い直すことがある。そして一番は食事だ。食事処でしか食べられないような御菜をは重箱に詰めて持ってくることがある。高価であろう甘い菓子も、は「お父さまに頂いたの」と持ち寄った。まれに読めない文字の包みが混ざっている。
「……姉上は藤ではないのですか?」
気づけば、ぽっと湧いた疑問が口をついた。
「え、フジなんて社名はついてなかったはずだけど……。あっ、言ってなかったよね、わたしの父は貿易会社を営んでいるの。最近は造船業の方とも親しいみたい」
「ぼうえき?」
「貿易は色々な物を外国に売ったり、買ったり……ごめんなさい、今度詳しく聞いてくるね」
は食事の用意を終えると、試験の準備があると言って早々に帰っていく。しかしそれは、千寿郎にとって大きな疑問となり、たちまち膨れ上がった。
その日の夜。
夕餉を見て、千寿郎は一度手にとった箸を下げた。
「どうした、腹でも痛むのか?」
二人きりの食卓。杏寿郎は目の前に座る千寿郎の不可解な動作を不審がる。
「ひとつお聞きしたいのですが、あね……さんは、藤の者ではないのですか?」
「うむ。は藤の者ではない」
千寿郎は頭の中でがらがらと崩れる音がした。けろりとしている兄を見て、理解に苦しむ。
物心ついた時から出入りしているが藤の者ではなかった。
藤の家でもない者が頻繁に出入りをしている。
それは少なからず千寿郎に衝撃を与えた。
藤の者は鬼殺隊に命を救われ、恩を返すために尽くしている。それを無下にするのは無礼だ。千寿郎はそのように聞いていた。だからこそ厚意はありがたく頂戴し、感謝の意を表してきたつもりだ。しかし、がそうでないとするのなら……。この温かい食事も、洗濯、掃除、雑用まで何もかも。に尽くしてもらう道理がない。思い返せば、ありがとうと御礼の言葉は交わせど、それ相応の返礼をしたこともない。そればかりか、に甘えてばかりいたような気さえする。そもそも、どうして自分が『姉上』と言っているのかもわからない。ただ、物心をついたときから千寿郎にとっては『姉上』だった。
先日の会話を加味しても、千寿郎は家と煉獄家の繋がりを見いだせずにいた。
「僕は、夕餉に手をつける資格がないように思います……」
千寿郎がちらりと様子を見やると、杏寿郎はすでに箸を置いていた。
「理由を聞いてもいいか?」
その声は静かで、柔らかい。
「はい。……僕は、情けないのですが、今までずっと姉上は藤の者だと思っておりました。しかしそうでないと言われると、その…………僕は何もしていないのに」
「そうか。しかし、今はこの膳を快く食すのが礼儀だ」
そう言って、杏寿郎は何事もなかったように再び箸をとった。それからいつものように白米を茶碗いっぱいにお代わりをして、一粒も残さずに食べている。
「千寿郎も早く食べないと固くなるぞ」
「え……は、はい」
—— 食べてもいいのだろうか。
その気持ちは消えはしないが、料理を目の前にしての空腹には耐え難く、結局は全部の器を空にした。
「ごちそうさまでした……」
「千寿郎」
「はい」
「さっきの話だが、千寿郎が気兼ねせずに済む方法はなんだろうか?」
千寿郎は視線を泳がせた。何も考えていないわけではなかったが、言葉にするのを躊躇った。
「……あ、兄上もお忙しいことですし、姉上もこれから学業がお忙しいのではないかと思うので、」
もしも、料理ができればに手間を取らせることもないだろう。の母が気にかけて様子を見にくることもない。千寿郎は目の前の食器に視線を落とす。
—— こんなに上手く作れるようになるものだろうか?自信がない……でも……。
「その……僕も、少しくらいご飯を、……料理ができれば何かとよい気がします。もちろん、掃除や洗濯はもっとがんばります!」
「うむ。ならばまずは火を起こすことを覚えよう!」
「はいっ、がんばります!」
一つ、ほっとした。そのついでに千寿郎は口を開く。
「姉上のお父上は、ボウエキというものをされているそうですね」
「の父上は随分と多忙らしい。ふた月居ないこともあるそうだ」
「そんなに?父上よりも多い……あ、たしか外国がどうとか、ぞうせん?ともおっしゃって……それにしても、」
—— どのようなお方だろう。
一つ消えては一つ増え、泡のように湧いて出た。杏寿郎がじっと見ていることも忘れ、千寿郎は物思いに耽る。
「家の屋敷は洋館だ。鉄柵はあるが、藤の家紋はない。そしての父上はひょろりとしておられる……と思ったが、服のせいかもしれないな」
「えっ!兄上は行かれた、お会いになられたことが、あっ」
千寿郎は慌てて両手で口を覆い、視線を膝に向けた。
「昔、……ちょうど千寿郎と同じくらいの歳の頃、いや、少し後だ。俺が面倒を起こしたもので、父上と家に謝罪に向かった。しかしまあ、謝ることもできず終いには手土産を頂戴したわけだが、あの芋羊羹はどこのものだったんだろう?…… の父上は、母上の葬儀の後、一人でいらした。終始申し訳ないとおっしゃって、それから晴れていたのに突然大雨が降ってきた。ああ、まさしく船がどうこうと頭を下げながら走って帰られた。背広が濡れてもまったく気にしておられなかった。そういう御方だ」
千寿郎はへえともはぁともつかない声を上げた。初めて聞く話ばかりで、なんと返事をしてよいものか迷う。
「知らないことばかりだ……」
千寿郎が本音を漏らすと、杏寿郎は言った。
「それもそうだろう、話していなかったからな。それに、俺がと初めて会ったのは千寿郎がまだ赤ん坊の時だ。理由は最終選別が終わったら話そう。面白い話もある」
千寿郎は頬が熱くなった。兄には敵わない、そう思えてならない。
「すっ、すみません、兄上」
「興味が湧くのはいいことだ!成長した証だ!」
にっこりと笑う杏寿郎を見ると、ますます恥ずかしく思った。
煉獄家と家の繋がり、もとより、姉と慕うと実兄である杏寿郎の繋がりを知りたくてたまらなかったのだ。まるで手の内を見られたようで、しばらく千寿郎は顔を伏せたままだった。

「それにしても、姉上は大丈夫でしょうか?」
粒が立ち、美味しそうに炊けたご飯を見て、千寿郎は憂えた。
「というと?」
「だって、さっき変だったでしょう?ジョガッコウというのは大変なんですね」
「ああ、アレは芝居だ。卒業式で披露すると言っていた」
小学校の卒業式で劇をする。はそう言っていたと言う。
「しかし、何の芝居をしていたのだろうな?秘密と言って教えてくれなかった。千寿郎はわかるか?」
「えっ、あっ……わからないです」
千寿郎は口をつぐんだ。間違っているかもしれないからだ。仮にそうであったとしても、謎は深まるばかり。
まるで兄上のようだった、とは言えはしなかった。