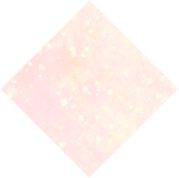第七話
は咲き誇った梅の樹を眺めた。だが、その表情は冴えない。そんなに友人は奇妙なものを見るような視線を向けた。
「お付きのセンセイが居なくなるのが寂しいとか」
「まさか」
「……そんなに難しいものではなかったと思うけど。わたしが何とかなったんだから、さんなら大丈夫よ」
「うん……」
尚も浮かない顔をするに、友人は続ける。
「わかった、脳が疲れてるのね」
「脳?」
「センセイがおっしゃっていたの。脳は糖を使うから、そういう時は甘いものを食べなさいって。今度、甘味でもお誘いするわ」
じゃあね、と友人は母親の元へ駆けていく。校門を出ると、友人と同じように晴子が待っていた。娘の浮かない表情を見ても何も言わない。しばらくそのまま無言で歩いていたが、蕾が膨らむ桜並木に差し掛かり立ち止まった。道は三叉路に分かれている。右に行けば自宅。しかし晴子は左に立ち、を見ている。
「行かないのですか?」
「あっ、行きます」
は試験が終わったらその帰りに神社でお参りをして、御守りを買う。その約束をしていた。
杏寿郎が剣の試験を受けると知ったのは、先月のことだ。が試験を受けると知って、杏寿郎は「一緒に頑張ろう!」と励ましの言葉をかけた。
頑張ろう—— はその一言に応えたかった。
神社の参道は石畳、両脇には樹木が並んでいた。多くの楠や檜にまじり大きな松の木がぽつんとある。あれが御神木だろうか、とは考える。傍から見れば森と見紛うのではないかと思うほどに、周囲は緑で溢れていた。澄んだ空気が染み渡り、まさしく神の宿るに相応しい雰囲気が漂っている。
「お母さま、……最終選別というのはどれほど難しいのでしょうか?」
本殿を目の前に、は晴子に問いかけた。しかし、なかなか返事がない。お母さま、と再度声をかけようとして、は押し黙った。隣を見ると晴子は目を閉じ、難しい顔をして手を合わせていた。
「……どうか、お守りいただけますように。」
僅かに動く口元から、は微かに耳にした。

参拝後、はその足で煉獄家へ向かった。
門の前で掃き掃除をしていた千寿郎がこちらに気づき、ぱっと表情が明るくなった。沈んでいたもつられてにこやかになる。
「今日は試験ではなかったのですか?」
「うん、午前中に終わったよ」
「そうだったのですね、お疲れ様です。あ、お昼は召し上がられましたか?」
「いただいてきたから大丈夫。さっきまでお母さまと一緒で、あ、これお土産。ここの芋羊羹とっても美味しいの」
手提げから包みを手渡すと、千寿郎は目を輝かせた。
「わぁ……ありがとうございます!兄上ももうすぐ戻りますから!」
「え、杏寿郎さんいらっしゃらないの?」
「はい、さっき豆腐屋を追いかけて行きました。その、僕が厠に行ってる間に通り過ぎてしまったみたいで……」
は肩透かしを食らったようだった。試験前というからには稽古に勤しんでいるだろうと思っていたのだ。
屋敷に入ったは仏間へと向かった。いつも真っ先にご先祖様に挨拶をする。手を合わせて、ふと晴子の言葉がよぎった。煉獄家は鬼狩りの一門である。それは数年前、晴子に告げられたことだ。
は恥ずかしく思った。考えてみれば、鬼狩りそのものを知らない。最終選別とはどれほどのものか。それ以前の問題である。
—— 杏寿郎さんのご先祖様、瑠火さん。ごめんなさい……。
は念じた。これまで幾度となく手を合わせたが、本当に恥ずかしい娘だと思っていることだろう。そう考えると、仏の前であっても顔を背けたくなる。
そうしていると、再びの気分は沈んだ。
思い出すのは試験のことだ。途中まで好調だった。しかし、手が止まったのは最終問題だ。
《良き妻について五百文字以内で述べよ》
似た問題はたくさんこなした。書けなかったわけではない。はすべて埋めたのだ。教科書のように、講師の教え通りに。ここで言う良き妻とは、すなわち良妻賢母である。良妻とは、夫に尽くし貞淑な妻であることだ。賢母とは、子どもの教育や躾をしっかりできる賢い母であることだ。しかし、書きながらずっと心の底で疼いている。
『良き妻』とは。
本当にそれが良き妻と言えるのか、は疑問に思ったのだ。その疑問を晴子にぶつけると、途端に眉を顰めた。「まさか、杏寿郎さんに訊くおつもりでないでしょうね?」と図星を付く。母の目はなんでも見抜いてしまうのだとは思った。「そんなこと絶対になりませんよ。第一に、その問題はあなたに問うたことであり、杏寿郎さんに問うたことではありません!」そう言って、しばらく晴子の眉間のシワは直らなかった。終いには、あなたは何のために学校へ行くのですか?と言われる始末だ。しかも追い打ちのごとく晴子は言う。「今日のお夕食は先生もご一緒ですからね」
は今日の試験で思ったことがある。講師は食事目当てに泊まり込んでいたのではないか、と。なぜなら、琴の試験も茶の湯の試験もすべて筆記だった。実技なんてどこにもなかった。連日連夜、見張られる意味はなかったように思うのだ。指がおかしくなるほど琴を弾いたが、楽譜に音符を書くだけだった。茶の湯に至っては一問だけだった。テーブルマナーというものが身についたところで煉獄家ではフォークとナイフでステーキを切ることは無いに等しいだろう。
なかなか戻らない杏寿郎を待っている間、は千寿郎に頼まれ炊事に立っていた。
「今日の味噌汁はきのこを入れてみたのですが、……どうでしょう?」
「うん、ばっちり!美味しいよ!」
千寿郎は料理の才があるらしい。それに気づいたのはだいぶ早い段階だった。彼が料理を覚えたいと言い出した時、は少なからず驚いた。初めは火を起こすことも緊張していたようだったが、最初に炊いたご飯は自身とは段違いの出来だった。それから千寿郎は見様見真似で包丁を握っていたが、その腕は日々上達をたどる一方だ。
「晴子さんからいただいた包丁、とても使いやすいです」
「よかった。あれね、実はわたしが選んだの」
「姉上が、ありがとうございます」
言い出したのは晴子だった。千寿郎が料理をはじめたと知らせると、晴子は刃物屋へ出かけた。あの包丁では大きすぎる。手に馴染む方が危なくないと。それで、晴子よりも手が小さいが選んだのだ。
「でも、これ以上千寿郎くんが上手になると困っちゃう」
「え?」
「だって、わたしの出番がないんだもの」
「そんな!僕はまだまだで、姉上の料理、晴子さんの料理も好きです!そんなこと言わないでください!」
「やだ、冗談よ。ごめん、半分くらいウソついちゃった」
「えっ、どっちですか?」
「ごめん、全部冗談、本当のホント」
下がり眉で見上げられ、は冗談が過ぎたと申し訳なく思った。
ほんとうに可愛い人。もう赤子の匂いはしないが、それでもには愛おしい存在であることは変わりない。ご飯を食べるようになった時。歩き出した時。話した時。訪れる度にできることが増えた。いつの間にか杏寿郎を真似て竹刀を握っていた時も驚いた。それが今は自分と同じことをしている。つくづく不思議だ。
「ただいま戻りました!」
玄関先から大きな声がする。その主はもちろん、杏寿郎他ならない。
「兄上!ありがとうございます、姉上がいらしてます」
「ああ!履物を見た!」
炊事場にやってきた杏寿郎は水の張った桶を抱えていた。千寿郎はそれを受け取り、杏寿郎の顔を見上げる。
「遅かったですね、何かあったんですか?」
「追いかけているうちに隣町まで行ってしまった!」
「えっ!」
「行きはいいが、帰りは困るな!しかし、水が溢れないように走るのはいい修行だ!」
千寿郎が抱えた桶には豆腐が一丁、崩れずに入っていた。は杏寿郎の胸元を見る。
「すごい、全然濡れてない!わたしなんてすぐにこぼしちゃうのに……」
「ははっ、はもう少し足腰を鍛えたほうがいい!」
杏寿郎に言われると遇の根も出ない。豆腐を持つとなんでも無いところ、外階段をたった三段上がっただけで手元を濡らすのだ。
「、試験はどうだった」
「何とか終わりました……」
試験と言われ、再びあの問題がちらつく。
良き妻とは。それは呪縛のようにまとわり付いた。いくら考えても答えは出ない。情けないとしか言いようがなく、は杏寿郎から目を逸らした。
「そうか!どんな結果になろうとも気にするな、命まで取られることはない!」
そして、杏寿郎は千寿郎へと視線を戻す。
「して、この豆腐はどうする?」
「あの、肉をいただいたので、その、牛鍋に挑戦してみようかと……」
千寿郎は小さな声で言った。先程の会話を気にしているのだろう。
「牛鍋!いいなぁ、わたしも食べたい」
「上手くできるかわかりませんけど、……試験も済んだことですし、姉上もご一緒にどうですか?」
ねえ、兄上。と、千寿郎の明るんだ声に対し、杏寿郎の返事は鈍いものだった。
「うむ。ただ、夕時では遅すぎるかもな」
「あっ、そうでした……すみません」
しゅんとした千寿郎を見て、はつい口走る。
「少しくらい大丈夫よ」
ほんの軽い気持ちだった。しかし、杏寿郎はいつになく真剣な顔をしてを見た。
「それは駄目だ。は日が暮れる前に帰る、そういう約束だ」
その有無を言わせぬ視線に、は内心どきりとした。
「あ、……忘れてたけど、今日は講師の先生と最後の夕食だった」
妙な空気だと思ったのはだけではなかっただろう。三人の間で、見えない糸が張り詰めた。
「何にしても、いきなりはの母上に失礼だ。次はきちんと断りを入れて来るといい。それに、牛鍋は逃げはしない」
「その、わたし……ごめんなさい」
「いや、俺が……」
刹那、は杏寿郎の瞳が揺らいで見えた。まるで冷たい冬風にさらされたようだった。
「俺が最終選別に合格したら、その時は一緒に牛鍋を食べよう!」
「……うん。じゃあ、その時はお祝いね!杏寿郎さん、あのね、」
は手提げから神札を出した。晴子と参拝に行った際に買った御守りだ。
「今度、杏寿郎さんも試験があるでしょう?種類があって色々考えたんだけど、杏寿郎さんは剣の試験だから、これにしたの」
合格祈願や勝守り、どちらがいいかと晴子に訊くことはご法度のような気がして、は随分と考えた。考え抜いた末に《志》と入った守札にした。そしてもう一つ、小さな巾着を取り出す。朱色の生地に白抜きの菊桜の模様が入っている。
「それで、こっちの巾着はわたしが縫った物だから、ちょっと不恰好だけど……守札を入れるのにいいんじゃないかなって、……」
講師には“試験の準備”と託つけて、地道に縫っていた。赤っぽい生地にしたのは杏寿郎にぴったりだと思ったからだ。
「杏寿郎さん、頑張ってね」
がそれを差し出すと、杏寿郎ははっとした顔をして手を伸ばした。広げた手は豆の跡がいくつもある。
一度、は稽古の様子を見たことがある。あれから随分日が経ったが、頑張って、という言葉では満ち足りないほどに杏寿郎は鍛錬を重ねたことだろう。
頑張って。
それ以上の言葉があるなら、今すぐに知りたいとは願った。
「……ありがとう!」
いつの間にか張り詰めた糸は消えていて、千寿郎が「兄上、」と口を挟んだ。
「さんが芋羊羹をくださいました」
「芋羊羹……」
「浅草のお店のものなの。お母さまが贔屓にしていて、お口に合うといいんだけど……」
「そうか、浅草の店だったのか!さっそくいただこう!」
それから茶を囲み、他愛もない話をして過ごした。
美味しそうに芋羊羹を食べる杏寿郎を見て、次はもっと持っていくことをは誓う。芋羊羹は甘く、もったりとしている。一つでも十分に腹が膨れると思ったのは大間違いだったらしく、が二口目を食べ終える頃には杏寿郎は3つ目に手を付けていた。そこで流れは再びの女学校の受験の話となる。自宅に住み込んでいる講師の存在は、自分が思う以上ににとって負担になっていた。
「——だから、わたしはご飯を目当てに来たと思ってるの」
杏寿郎に笑われるかもしれない。それでもの口は止まらなかった。しかし、意外にも杏寿郎はすんなりと同調する。
「の予想は大方外れていないだろうな!」
「でも、どうして?」
不思議がるのはばかりで、杏寿郎だけでなく千寿郎もくすくす笑う。そして、杏寿郎は恐ろしいことを言う。
「その講師も胃袋を掴まれているからだ!そのまま住まわせてくれと言いだすかもしれない!」
またあのような日々が続くと想像するだけで気が滅入った。それは困るとが言うと、
「もしそうなったら煉獄家を紹介するといい!」
杏寿郎は自信たっぷりな顔つきでそう言った。