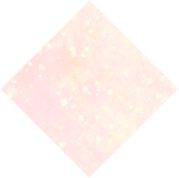第八話
『—— くだらん夢を見るな。』
隊服に袖を通す時、杏寿郎の脳裏にその言葉が浮かんだ。
任務を終え、帰途につく。それも当たり前でないことを、身をもって知ったばかりだった。
「兄上、」
「ああ、今行く!」
最終選別に合格したら—— 。
杏寿郎がその約束を果たすまで、しばらく時間を要した。最終選別を終えた後はほとんど息を付く間もなかった。鬼殺隊は忙しく、準備が整うと同時に鎹鴉がやってきた。結局には何も言わないまま、初任務に出ることになってしまった。そうしていくつも任務をこなしているうちに、とうとう夏が過ぎた。
杏寿郎が小走りで玄関へ向かうと、は頬を緩めた。
「待たせてすまない!」
「お久しぶりです、きょ……」
稽古着ばかり見ていたせいだろう、はまじまじと杏寿郎を見る。
「これは例の制服だ」
最終選別に合格したら、牛鍋を食べる。杏寿郎がと交わした約束はそれだけでなかった。合格したら隊服を着ることが許される。黒い詰襟、背には《滅》の刺繍。鬼殺隊の証であるそれをに見せる約束していた。制服と言ったのは、その方がに馴染みがあると考えてのことだった。
「おめでとうございます。あの、……よくお似合いです」
はもう一度杏寿郎をじっと見て目元を細める。
「ありがとう!……しかし、あまり見られると照れくさいな!」
「あっ、すみません」
「さあ、上がってくれ!準備ができている」
「お邪魔します」
はそっと式台に足をかける。いつもならすぐに付いてくるのだが、今日はゆっくりとしていた。履物を揃えたは前を向く。上がるまでにはもう一段。つまずかないよう、慎重になっていた。
「袴が少し長かったみたい」
「どれ、手を貸そう」
杏寿郎がぐっと手を引くと、はほっと息をつく。
「……ありがとう。やっぱり歩きにくいのはダメね、整えてもらわなきゃ」
杏寿郎は袴の裾に視線を向ける。袴だけでない。上の着物も履物も、すべて真新しいのが見て取れた。以前より幾分落ち着いた色柄だ。
「合格おめでとう」
が杏寿郎の合格を知るように、が女学校に合格したことは杏寿郎の耳にも届いていた。だが、学校に通うとは顔を合わせることは難しかった。それに加え、杏寿郎自身、生活ががらりと変わった。夜行型の鬼に合わせるというのは癪だが、そうしなければ鬼を狩ることは困難だ。移動を合わせると昼夜逆転することも多々ある。最近はそれにも慣れてきて、ようやく休暇を休暇らしく過ごせるようになっていた。
「ありがとうございます。この一式、入学祝いで揃えていただいたの。今年はすぐに暑くなったから、なかなか着る機会がなくて」
「そういうことか、それで……」
花模様の赤や桃の着物は控えめな色合いに変わっていた。あったはずの着物の肩上げがなくなったことすら気づかずにいた。握った手のひらの感触も違和感がある。
一体、いつから。
杏寿郎はその境を考えたが、明瞭になることはなかった。
「大福餅をさっき千寿郎くんに預けたんだけど……杏寿郎さん、これ覚えてる?」
悪戯をするような顔では手提げから包みを出した。弁当のように風呂敷に包まっている。もちろん中身はアレしかない。
「もし時間があったらだけど、どうかな?」
「なるほど!確かにいい頃合いだ!」
は楽しみと言わんばかりに頬を緩ませた。
そんな話をしていると、炊事場の方から「兄上?」と声がする。
「だが、その前に牛鍋だ!」

鍋を囲みながら、は目を輝かせた。
「本当に千寿郎くんが作ったの?!」
「僕なりにがんばりました。もちろん、兄上にも少し手伝っていただきました」
「俺は米を研いで火を入れただけだ!」
「そっか、でもすごいよ、本当にすごい!」
千寿郎がこしらえたものは牛鍋だけではない。ちらし寿司と吸い物もある。今日はお祝いだから、と腕によりをかけたのだ。千寿郎が稽古の合間に何度も料理の本を読み、せっせと下準備をしていたのを杏寿郎は見ていた。
「わぁ……嬉しい!杏寿郎さん良かったね!」
いつの間にかは急須を取り、三人分のお茶を注いだ。そして箸を持ち、取り皿を手に取る。
「二人ともどれくらい食べる?これくらい?」
さっと取り分けたは嬉しそうに見ている。おろおろしたのは千寿郎だ。
「そんなに肉を入れたら姉上の分がないですよ!」
「わたしはいいよ、今日は杏寿郎さんのお祝いだから」
「いえ、今日は兄上と姉上のお祝いです!兄上はいつもたくさん食べているので大丈夫です、姉上が召し上がってください!」
千寿郎はそう言って、がよそった皿を交換する。杏寿郎の前に皿が回ってきた。見事に野菜と豆腐しか入っていない。すぐに腹が空きそうな量だ。二人は困惑する杏寿郎に気づかず「こんなに食べられないよ、千寿郎くんこそたくさん食べなきゃ!」「いえ、僕はいいです、本当に!」と押し問答をしている。このままでは埒があかないと悟った杏寿郎は口を開いた。
「今日はお祝いだ、均等に分けよう……!」
どうしてあのような分配になったのか、の話を聞いて杏寿郎と千寿郎はだんだんと理解する。
“奉仕こそ女子のあるべき姿である”
が学校での教えを忠実に守った結果だった。忠実すぎるのは家の父は不在が多すぎるからだろう。実践するには困難を極めた。話しながらそれに気づいたのか、「その、学校も家も女子しかいないから……」と、は頬を赤らめた。その一方で「大変ですね……」と、千寿郎が眉を顰める。そんなことはないとは言うが、杏寿郎は弟が何を考えているのか安易に想像できた。「女学校は恐ろしい」十中八九そう思っている。
「でも、楽しいこともたくさんあるよ、わたしは国語の考査が面白いと思ってる。文学も楽しいし、算術はそこそこ。……欧語学だけは少し難しいけど」
欧語学という言葉に千寿郎は興味を示す。
「姉上は缶の文字がわかるんですか?」
「さすがにまだ読めないよ、でもこの前の飴玉はわかったの、友達に聞いたんだけど、『コーク』だって。わたしは飴屋の飴のほうが好みだったけど、……杏寿郎さんはどうだった?」
杏寿郎は一瞬躊躇した。の影響もあり外国の菓子は見慣れたものになったが、飴は見たことがなかった。『コーク』というのも初めて耳にした。すると、千寿郎が慌てて言った。
「黙っていてすみません、たしかに“飴”をいただいたんです。でも、その……てっきり薬品と間違われたのだと思って、捨ててしまいました……」
見た目は黒糖のようだった。しかし、その色合いに似つかわしくない味わいをしていて、一口舐めた千寿郎はそのように思った。余計なことを言ったと思ったのだろう、は杏寿郎を見て、
「本当にそう、薬品のようだったから、お口には合わなかったかも……」
「そうか、二人がそういうなら余程のものだろうな」
「そう、牛鍋のほうが何千倍も美味しいよ、本当よ!」
それからも、は女学校の話を聞かせた。受験の苦労は水の泡となったわけではないらしく、琴と茶の湯ではかなり得をしているとは言う。
「僕はあの時姉上がおかしくなったと思って、ずいぶん心配しました」
「そうだったの?たしかにあの時は大変だったけど、ほら、今はこの通り元気!」
と彼女は言うが、牛鍋の肉も少なめにしてくれと言い、ちらし寿司も少ししか食べていない。
「本当か?、遠慮は良くない」
「遠慮なんかしてないよ、お腹いっぱいなくらい……わたしが杏寿郎さんと同じように食べたらお腹が破裂しちゃうよ」
煎餅を出した時も同じようなことを言ったのを、杏寿郎は思い出した。美味しいねと言っていたがすぐにお腹いっぱいと言って断った。
「……そうだな、は栗鼠ではないからな!」
も千寿郎もぽかんとしたが、杏寿郎は最後の肉を頬張った。上物の肉は溶けるように無くなる。
「うまい!」

よく日の当たる部屋で、杏寿郎は包みを見る。
「千寿郎、開けてみるがいい!」
と、言ったはいいが、千寿郎は風呂敷を広げるのに四苦八苦していた。杏寿郎とがそれを見守るが、結び目はしぶとく、待てども待てども、風呂敷の中身は姿を見せない。
「硬い……いや、本当に……もしかして、これは兄上が結んだのではないですか?」
思いがけず、杏寿郎は弟の顔を見つめた。
「あ、違いましたか。そうですよね、これは姉上のものですし……」
「いや、そうだ。俺が結んだ。なぜわかった?」
「なぜもなにも、兄上の結んだものはいつもこうですから」
ぎゅうぎゅうに布が詰まって解けるものも解けない。コツがいるんですよ、と千寿郎は器用に爪をかけ、それを解いた。
「ん、カルタ……?どうしてこれが風呂敷に?」
どういう意味だと首をかしげる千寿郎を見て、は前に詰め寄った。
「千寿郎くん、よく見て」
「……『おばけかるた』。へえ、こんなカルタがあるんですね、初めてみました!」
さっそく蓋を開け、わっと頬を明るくした千寿郎に対し、杏寿郎とは時が止まったような顔をした。口を開いたのはだった。
「千寿郎くん、怖くないの?」
「え、まぁ……はじめは鬼でも出てくるんじゃないかって思いました。でも、そんなわけないですね、今は昼ですし」
ははっと千寿郎は笑う。他意はない。千寿郎は本当にそう思ったのだろう。偶然にも、その風呂敷は藤の柄をしていた。杏寿郎はの様子を窺った。なんだ、とわかりやすく肩を落としている。
「でも、どうしてカルタなんですか?」
正月でもないのに、と千寿郎はに問う。
「昔ね、杏寿郎さんと約束したの。千寿郎くんが大きくなったら三人でカルタをしようって。ね?」
「カルタは人数が多いほうが面白いからな!」
「さっそくだけど、はじめましょう!日暮れ前に何回できるかな」
最初はが読み手となった。次は杏寿郎が、最後に千寿郎が読み手となり、杏寿郎に負けたは悔しがった。「……もう1回だけいい?」と2回ほど願い出た。「次は負けないんだから!」と闘志を燃やす。しかし、の勝利はお預けとなり、
「学校ではそこそこ勝てたのに……」
悔しさをにじませ、は敗因を探る。
「は目が泳ぎすぎだ」
「目?……わたしも剣術を習ったほうがいいのかな」
杏寿郎はぎくりとした。その傍ら、千寿郎がに言う。
「剣術は関係ないと思いますよ?」
「そうよね、剣とカルタは関係ない……あ、わかった!」
そうでしょ?と言うに杏寿郎は持ち札を見せた。
「やっぱり!気に入った札ばかり取られてる!」
「バレてしまったか!次は使えないな!」
「あ〜、なんで気づかなかったんだろう」
そして、はこっそりと杏寿郎に言った。
「やっぱり兄弟ね、ああいうものが平気だなんて。わたし、ちょっと恥ずかしかったな……」
それは違う。
杏寿郎は胸の中で囁いた。千寿郎も怖いと思っていたはずだ。しかし、千寿郎にとって怖いと思うものがとは違っていたのだ。この世で一番恐ろしいと思うものが、違っていた。それだけのことだった。
カルタを終えると、杏寿郎たちはが持ってきた大福餅を食べた。満腹だと言っていたも「甘いものは別腹」と頬張った。そして千寿郎が思い切り頬張る姿を見て、杏寿郎とはあんこを喉につまらせそうになった。
は杏寿郎に目配せする。杏寿郎さんのせいだよ、そんな風に言っていた。
「君にもう一つ見せたいものがある」
が帰る間際、杏寿郎は彼女を別室に連れ立った。いつも帯刀しているそれを見せるためだ。隊服よりも、重要なそれを。
「刀?」
「日輪刀だ」
「にちりんとう……」
「最終選別に合格すると、隊服と同様に刀を打ってもらえる」
「本物……?」
は頭から鞘の先までじっと食い入るように見る。
「抜いてみよう」
「……いいの?」
「刀は刃が肝だからな」
鞘を握り、馴染み始めた柄を横に引きかけ、杏寿郎は手を止めた。
今更何を迷う必要があるというのか。そう思う反面、杏寿郎はすぐにそれを引くことができなかった。
—— 考えても仕方がない。
杏寿郎は意を決して刀を抜いた。
しばらくの間、は黙ってそれを見ていた。その視線は鍔からゆっくりと切っ先へ向かう。真っ直ぐな視線が刀を通じ、杏寿郎へと移る。
「触ってみるか?」
「え、うん……」
杏寿郎のよく知る手が柄に伸びる。しかし、あと少しというところでは手を引いた。
「ごめんなさい、やっぱりやめとくね。その、これは杏寿郎さんが頑張っていただいたものだから」
「……わかった。じゃあ、これは仕舞うぞ」
は小さくうなずいた。日輪刀が鞘に収まると、は再び杏寿郎を見る。
一時、この場から音が失くなったように静かになった。
「杏寿郎さんは、その刀で鬼を斬るのね」
「……そうだ。俺はこの刀で鬼の頸を刎ねる」
杏寿郎は目を合わせたまま、はっきりとそう言った。も目をそらさなかった。
あの時と同じだ。
初めて稽古を見せてくれと頼まれたときと同じだった。どこまでも続くような漆黒を思わせるそれに、光りが見えた。いつも見えないそれは、時折流星のごとく杏寿郎の前に現れるのだ。
「杏寿郎さん、わたしに見せてくれてありがとう。……さ、そろそろ帰らないと!」
は手提げを持って、玄関へ向かう。
「」
「あっ、何か忘れものでも、……」
杏寿郎はポケットから和紙の袋を取り出した。
「これを。守札のお礼だ。あと、入学祝い」
「わぁ……なんだろう、とてもいい香り。匂い袋?」
「藤の花だ。きつくはないと思うが」
「うん。開けてもいい?」
「ああ」
はそれを着物の袖に入れ、二、三度揺らしてみせる。気に入ったのか、いい香りね、ともう一度言った。
送っていこう、杏寿郎の言葉にはうーうんと首をふる。
「大丈夫、お母さまと停留所で落ち合うことになってるの。杏寿郎さん、本当にありがとう!」
門から出たあとも、はこちらに手を振った。杏寿郎はの後ろ姿が見えなくなってもしばらくの間見続けていた。振り返ると近所の人と目があった。小さく会釈をし、中へと戻る。
縁側から千寿郎がこちらを見ていた。いつも一緒に見送るが、今日はなぜか来なかった。
「どうしてこなかった?」
「僕は、その……」
千寿郎の視線が左右に動く。
その仕草に、杏寿郎は無性に頭を撫でたくなった。ぽんと手を乗せたが、それだけでは終わらない。撫でるというより荒らすと言ったほうがいい。
「あ、兄上?!髪が!」
「ははっ!要らぬ気をまわすからだ!」
「うわ、あにっ!まって、前髪が、兄上っ!」
千寿郎は頬をふくらませる。まさに大福餅さながらだ。
抵抗する千寿郎を尻目に、杏寿郎は笑みを浮かべた。
「……さて。こちらもいい頃合いだ」
「えっ?」
約束はもう一つ残っている。
自分と瓜二つの目を見て、杏寿郎は笑みを深くした。