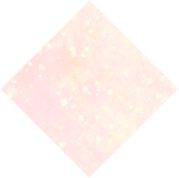第九話
まず【奉仕】という文字に線を引いた。【仕える】という文字も線を引き、最後に【支える】という文字を指先でなぞる。線を引いただけで答えがでるわけでもない。それでも眺めるのを止めなかった。
「支える。それがどうかしたの?」
友人の声に、は慌てて辞書を閉じた。
「……支えるって、なんだと思う?」
「例えば?」
「やっぱりいい、忘れて」
「わかった。殿方に何か言われたのね」
「違うよ。その殿方って言うのやめて」
そんな話をしていると、別の友人が近寄ってきた。こうなると最高な休み時間の始まりだ。根掘り葉掘りと聞き始め、噂はあっという間に広がっていくのだ。はこの時間が一番苦手だった。黙っていればどうということもないのだが、あまりに黙っていると、この狭い空間で暗黒を覗くことになりかねない。
「どうしたの?」
「う、うーうん、何も。さっきの授業でわからない言葉を調べていたの」
「ああ、そうなの。確かに難しかったものね」
そう言うと、彼女は納得したのか別の席へ向かっていく。
近頃この教室は変な緊張感が漂っている。というのも、もうすぐ母親参観の日が迫っていた。母親参観といえば当然皆張り切るわけだが、張り切るのは生徒だけではなかった。
「ねえ、さん。今日時間ある?」
「うん」
「帰りに髪留屋に寄っていかない?」
「いいよ、でもこの前も買ったのに?」
「今度は厄除けを買うのよ」
はその意味がわからなかった。髪留屋に厄除けなどない。はそう思っていたが、放課後、髪留屋を数件回り『髪花』の前に立ち止まると、「あった!」と友人は歓喜の声をあげた。
「一緒に買わない?」
「これを?」
「今流行ってるの。ほら、あの子も付けてる」
通りをみると、たしかに似たような物を付けている学生が目に留まる。頭の半分を覆うような大きなリボンだ。
「でも、派手すぎない?」
正札を見たは仰天した。簪より高値が付いている。
「これって、舶来物?」
「さんのお父様だって送ってくるでしょ?」
「お父さまは食べ物しか送ってこないよ」
「欲しいって言わないの?」
「え、どうして?」
はあ、と友人はわかりやすい態度でを見た。
「いつまでもお母さまの用意した物じゃダメ。もっとオシャレをしないと。殿方に逃げられるよ?」
「そうなの……?」
「でもまあ、さんのお母様はオシャレなお方だけど。お父様は紳士そのものだし」
「そうでもないよ、少し変わってるだけ」
「いいえ、流行は海の向こうからやってくるんですって。センセイが言ってたもの。それより、新しいお着物はどうだった?」
「着物は、……袴が歩きにくいから丈を少し短くしようと思ってるの。どう思う?」
「なるほど、その手に鈍くいらっしゃるのね」
はちくりとした。実の所、杏寿郎に新しい着物を見てもらおうと、わざわざ時期を待っていたのだ。しかし、これといって何かあるわけでもない。袴の丈で手こずったこともあるだろうが、には杏寿郎がその手に関心がないように見えた。
「もしかして、厄除けってこれのこと?」
「そうよ、これを付けておくと声をかけられないんだって。さんだってどこそこの奥様に声をかけられたら困るでしょ?」
母親参観は別の意味でも緊張した。授業を見に来るのは建前で、その内情は息子を持つ親が将来の嫁を探しているというのはよくあること。目を付けられるとそれはもう大変だ、とも聞いたことがあり、友人の言わんとすることはわからなくもなかった。しかし、断るのなら口頭でも問題ないはずだ。
「必要?」
「必要、大あり!声をかけられたらセンセイが困るもの。それにこの店のお包み、とても可愛いの!」
薄々わかっていたが、友人は昨年の受験を期に講師のセンセイにご入心だ。それが良いか悪いかは別として、
「大人のセンセイは大変なのよ」
何かにつけては“センセイ”が出てくるのだ。そう言われると、は返答に困る。友人のように悲劇さながらの恋愛をしているわけではないからだ。
「ねえ、今日のさん良い香りがするね」
「あ、……いただいたの」
「へー、匂い袋ね。誰にいただいたの?」
「きょ……」
言いかけた言葉をは慌てて飲み込んだ。今日はいい天気ね、と付け加えるも友人は逃しはしない。
「キョウスケさん?それともキョウタロウさん?」
「違う」
「香水じゃなくて匂い袋っていうのが乙よね。やっぱりさんの殿方は古風ね」
は何も言い返せなかった。
あれは小学校の卒業式で劇をした時だ。寸劇だ。演目は決まっていた。「紳士」。自分が思う紳士を演じるというもので、も自分が思う紳士を演じた。
しかし、会場はしんとして、妙な空気になった。一人がくすりとしたのをきっかけに瞬く間に広がっていった。「とても個性的な紳士ですね」と言う教師も真面目を貼り付けた顔をしていた。もちろん、が思うのは杏寿郎だ。それ以外に紳士と言われても思いつかなかった。ただ、考えればわかることだが、シェイクスピアの紳士が「ワハハ!」と大声を上げることはない。終わった後、の紳士は侍だ武士だと言われ、は何と言ってよいのかわからなかった。唯一ほっとしたのは母、晴子だけが黙って見ていたことだ。
それ以来、彼女は殿方と言って聞かないのだ。幸いにも女学校でそれを知るのは彼女のみ。他は皆違う学校に進学したり、卒業して以来それっきりとなっている。
「わたしも買おうかなぁ、匂い袋」
そんなことを言いながら、友人は熱心にリボンを選んでいる。が髪紐を眺めていると、
「ねえ、キョウジロウさんってどんなお方?」
は驚いて彼女を見た。かなり惜しい。
「……詰襟を着てる」
「学生さん、いいじゃない。センセイも詰襟を着ていらっしゃるのよ」
「それと学帽も、でしょ?」
「そう、そうなの。素敵なんだから」
素敵—— は刀を、日輪刀を思い出した。それを見た時、触ってみたい。はそう思った。だが、いざ手を近づけてみると触れてはならない気がして手を引いた。
決意、信念。はたまた、志。
正しい言葉を見つけるのは難しい。
は度々“鬼狩り”の意味を考えた。
“狩り”をするには道具がいる。その道具として、鉈や斧、色々なものを想像した。
ある時、槇寿郎が腰にさしていた刀を見た。廃刀令のある今、あえてそれを持つ意味を考えた。それを滅ぼす道具は刀。刀でできるのは、斬ること。
鋭い刃は灼熱の炎を思わせた。白い柄から熱が伝わり、剣先まで一挙に伸びるその様は、神器のごとく異様な空気を放ち畏怖すら覚える。それでいて、見事なまでに美しかった。日輪刀が特別な物であることには違いない。杏寿郎が鍛錬をして得たものを、何もしていない自分が触れるのはあまりにも都合がよすぎるように思えた。
だが、刀を目の前にしても杏寿郎に映るそれが、どのようなものかはわからなかった。
制服を着た杏寿郎は本当によく似合っていた。思わず見惚れてしまうほどに。差し伸べられた手は昔と同じ温かみのあるものだった。厚い手のひら、袖口に見えた傷跡。それを見なければ、ただ恥ずかしいばかりで何も考えはしなかったかもしれない。
少なくともこの世に『鬼』は存在する。実はどこかで斬首刑が行われていて、罪人を処罰している。それを鬼と総称しているのだろうか。それとも、—— 。
「ねえ、さんはどっちが好き?」
濃紺の縞模様と赤の花柄を見せてくる。は手に持った髪紐と見比べた。
「……赤、かな」
すると、友人は目を点にした。
「意外ね、濃紺を選ぶと思ったのに。殿方の影響ね」
は耳が熱くなった。湯上がりのように赤くなっているかもしれない。事実、は杏寿郎の姿を思い浮かべていたのだ。
「だから、その言い方はやめて」
「お名前を知らないから仕方なく呼んでるのよ。それに意味は間違ってないでしょ?」
「……ずるい」
「賢いって言って。さんはそれ買うの?」
「うーうん、また今度にする」
賢いといえば、彼女は本当に賢かった。飴の名を読み解いたのもそうだが、『コーク』というのは外国の飲み物で、それを模した飴だとに教えたのも彼女だ。多少は“センセイ”の入れ知恵かもしれないが、それでもそういった部分は昔からあった。
「ねえ、あのコークって飴、どこに売られてるか知ってる?」
「えっ、あの飴好きなの?」
は言い淀んだ。またからかわれてはたまったものではない。
「うん」
「へえ、味覚は人それぞれね。たぶん西洋館にあるんじゃない?」
「西洋館?」
「外国人が集まってる喫茶」
「……そんなところ、行っていいの?」
「経営しているのは日本人らしいから、たぶん大丈夫よ」
「そうなんだ」
「わたしも一緒についていってあげる」
「えっ、本当?」
「センセイがいるかもしれないもの。欧語学を生で学べるって言ってたから」
「……センセイって凄いね」
「そうでしょ」
友人は気を良くしたのか、2つとも買うと言って会計へ向かう。正にセンセイ様様だとは思った。
西洋館は意外にも町並みの中でひっそりと存在していた。が煉獄家へ向かう際に使う道路のすぐ近くだ。西洋館というだけに、建物は立派な洋館だった。格子状の窓枠、わずかに開いた上下窓の隙間から優雅なクラシックの音とともに葉巻の匂いが漏れ出ていた。たちはガラス越しにレースのカーテンを覗く。
「本当にここに飴があるのかな……」
「センセイはいらっしゃるかしら……」
二人の目的は違えど、屋敷の中にある未知への興味は同じだった。すると閉まっていた扉が急に開き、『open』と書かれた板が翻る。中からもわっとした空気が漂い、コーヒー、紅茶、葉巻、香水などが混ざりあった異質な匂いがした。じっと見ている間に数人の男女が出てきた。何を話しているのかさっぱりわからない。その中に日本人がいると思えず、は思わず後ずさった。
「こんなところで何をしているのです」
は振り返ることができなかった。友人は、と見るとにこにこと愛想笑いを浮かべて「ごきげんよう、さようなら」と去っていく。一方では肝が冷えた。振り向かなければ帰れないし、振り向いたら帰りたくない。「」と、鞭のような声は背中に氷を落とされた気分だ。観念したが理由を話すと晴子は怪訝な顔をした。
「飴?」
「はい。コークという飴が欲しくて。飴屋にはないものでしたので……その、西洋館ならあると聞いて」
「美味しくないと言っていたでしょうに」
は返答に詰まった。千寿郎が薬品のようだと言ったのは本当だった。同じく気味が悪くなり、興味をもった友人に譲ったのだ。
「……杏寿郎さんに持っていこうと思って、千寿郎くん……あの、……」
幼子のようにもじもじと言うに晴子はため息をつく。
「確かに、西洋館ならあるでしょうけど、」
「えっ」
「その前に、父様に頼めばいくらでも届きます。電報を打ちなさい」
なぜその案が浮かばなかったのか。そもそもあの飴は父から貰ったものだったのだ。はさっそく電報を打った。しかし字数の壁が現れる。「オトウサマ、オゲンキデスカ?コークノアメガホ」で終わってしまうのだ。仕方なくそのまま出したが、意味は通じたらしく、その一週間後には飴が届いた。

その後、が杏寿郎と会ったのは、紅葉が色づいた頃だった。が煉獄家を訪れると、杏寿郎が出迎えた。千寿郎は書き物をしていると言って部屋から出てこない。二人きりというのが久しぶりということもあり、は話を切り出すのに苦労した。なぜなら、杏寿郎の雰囲気が少し違ってみえたからだ。背丈、それとも声。視界の先に刀を置いた掛台が映り込む。そろりと視線を戻すと、緋色にも見えるそれがこちらを見ていた。はとっさにお茶を流し込む。
「千寿郎くんは勉強熱心ね。……あのね、杏寿郎さん。この前の飴なんだけど、」
手提げから正方形の缶を取り出す。
「また頂いたから、試しにどうかと思って」
「飴?」
「ほら、前にお祝いをした時に話したでしょ?牛鍋の」
は杏寿郎の様子を窺った。
「ああ、千寿郎が捨てたと言ったやつか」
「そう、それ」
杏寿郎はちらりとそれを見て、また前を向き直る。そして、再度の手を見てありがとうと受け取った。そしてさっそく一つ取り、ころんと口に放った。
杏寿郎は前を向いていた。しかし、その目はどこを見ているのかわからない。遠くを見ているようで、近くを見ているようで。一瞬、自分を見ているように思ったが、ここではない別のどこかを見ているようには感じた。
「……杏寿郎さん?」
くるりとした大きな目が、くわっと見開く。そして、ごくりと喉がなった。
「の、飲み込んだの?!」
が驚いた顔をすると杏寿郎は、
「うむ!鬼も黙る味だ!」
と、湯呑みを手にする。杏寿郎は不味いとも言わなかったがうまいとも言わなかった。
「なら、鬼にその飴を食べさせたらどう?」
鬼も黙るというのなら。そうすれば、杏寿郎があの刀を振るわずに済むのではないか。は真剣に言ったつもりだったが、杏寿郎はははっと笑う。
「それは妙案だ!」
「じゃあ、……」
「しかし、鬼は人のものを食さない!困ったものだ!」
それを聞いては落胆した。
の自室には紙箱いっぱいにコークの飴が残っている。数を書かなかったために、の父は1ダース丸ごと送ってきたのだ。杏寿郎の様子を見ても絶対に好みではないことはわかる。
鬼は人の物を食べないというのなら、何を食べるというのだろう。
は恐ろしい結論をかき消すように、不要となった飴缶を手提げの奥に仕舞い込んだ。