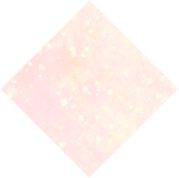第十話
時折、杏寿郎はそれを胸元から取り出した。
彼女がどのように晴子に聞かされたのかは知らない。
それでも、朱色の巾着は偽りなきものだった。
『杏寿郎さんは、その刀で鬼を斬るのね』
は鬼を知らないようで、知っているように言うときがある。晴子から聞いたのだろうか。そう思うこともあったが、千寿郎の言葉を聞く限り、杏寿郎はその考えを否定せざるを得なかった。特別に理由がない限り、鬼の存在を知る者はいない。たとえ言葉にしたところで、簡単に信じはしない。それは杏寿郎がこれまでの任務で幾度となく感じてきたことだった。
「煉獄さんは、想いの人は?」
任務の合間の戯言、仲間内でそのようなことを訊かれることが増えた。そんなとき、杏寿郎はこう答える。
「君は居るのか?」
すると大抵、身の上話に発展した。
誰かのために戦う。命をかけて守ることがどれほど過酷か、鬼殺隊の面々は痛いほど知り尽くしている。時には憎悪がその者を強くし、あるいは慈しみを持って剣技を極めた。そしてその語らいを嘲笑うかの如く、鬼は容赦なく襲いかかる。その度に奈落を覗く。
ふとした時、揺らぎそうな信念。それを母の言葉が繋ぎ止める。
しかし、父、槇寿郎が、この世から目を背けるのはどうしようもなかった。現実だ。その現実はの目にも映っていることだろう。
度々、杏寿郎はに宿る流星の正体を見極めたくなった。だが、あれは稀にしか見れない。それがまた、興味を抱かせる。

任務帰り、杏寿郎が街を歩いているとの姿が目に止まった。その背は吸い寄せられるように一軒の家屋へ消える。軒の瓦屋根には『神谷書房』とある。
「煉獄、ちょっと寄ってもいいか?」
杏寿郎の隣を歩いていた隊士は、それと向かいの簪屋に視線を向けた。「もうすぐ妹の誕生日なんだ」と言うその声色は照れた様子だ。
「急ぎではないし、ゆっくり選んでくれ!」
「……煉獄も来るだろ?」
「ん?」
「いやいや、俺一人で入らせる気か?」
「鬼を一刀する君が面白いことを言うな!」
「いや、煉獄。おっ……お願いだ、ついてきてくれ!頼む!」
三つ年上というその者は、白昼堂々、杏寿郎の腕にしがみついた。通りの人々がぎょっとした顔で二人を見る。
「もちろん行くのは構わない、ついて行こう!」
「よっし!」
「しかしながら、俺は簪屋に用がないので店の外で待っている!」
「う、ウソ言うなよ」
「嘘ではない。俺は簪屋には」
「あーっ、もうっ!入ってみればわかる!」
背を押され、腕を引っ張られ、やや強引に簪屋に連れ立たれた杏寿郎はすぐにその意味を理解した。
「簪は贈り物にはよろしゅうございまして、定番の花物、特にこの紅色のものは一番人気でございます。」
「ガラスの球は昼もよく映えまして、こちらも人気でございます。」
「銀の物は水に強く、こちらも大変人気でございます。」
「金の物は最高品質でございまして、値は張りますが、大変貴重で大変優美にございます。」
なるほど、なるほど。何度頷いたことだろう。
あの者はまだか、と杏寿郎が様子を見ると、赤か桃かとブツブツ独り言を述べている。桃を置き、買うと見せかけて今度は瑠璃色の簪を手にしている。その表情は至って真剣だ。
「どのような御予定でいらっしゃいますか?」
「うむ!誕生日と言っていた、あちらが!」
「左様でございますか……。貴方様は?」
「……っ、なるほど!」
ここは買うまで帰れない。だから自分は呼ばれたのだろう。杏寿郎は一人納得し、店内を見渡した。
簪といっても一言に収まらず、平打ち、揺れもの、結びと様々で、迷うのもうなずける。もちろん、簪の一本や二本、買えないことはない。しかし、には匂い袋を渡したばかりだ。誕生日が近いわけでもない。杏寿郎は藤を模した簪に手を伸ばしかけ、思い留まる。
—— 鬼に囚われるのは良くないな。
下を見るとつげ櫛が目に留まった。持ち手の部分は丁寧な彫り細工がある。簪屋の添え物として置くにはもったいない造りだ
「元は櫛屋でございまして、こちらも物は良うございます。一等品です」
「そうでしたか、ご説明ありがとうございます」
「いいえ、どうぞごゆっくり」
陳列された櫛を見るふりをし、杏寿郎は向かいの書店を見た。は棚を眺めていた。見ているのは中古書籍のようだ。探し物をしているのか、手にとって見比べるがすぐに書棚に戻す。そしてまた手に取ってと繰り返し、店の隅で真剣な顔をして吟味している。いつもの「杏寿郎さん」と名を呼ぶ顔とは別だった。
「お目が高いですね、お客さん」
背後から隊士の声がする。杏寿郎が振り返るとその顔はにやりとした。
「買い物は済んだようだな」
「ああ。お陰で良いものが買えたよ、ありがとう」
「それは良かった」
言葉通り、その隊士の手には袋が握られている。そして彼は杏寿郎が見る先へ視線を向けた。
「良いとこの娘さんだ。どこの学校だろう?声をかけたらどうだ」
「捜し物をしているのに邪魔をするのは悪いだろう」
「本当にいいのか?」
「ああ」
「……まあ、そうか。はは」
その笑いはどこか寂しげで、杏寿郎は真意を探した。見られた方は意表をつかれた顔をする。
「いやぁ、……あっちの詰襟とこっちの詰襟じゃ話が違うだろう?もっとも、腰にある物も違うけどさ。なんか、別の世界っていうか……」
そう言って、隊士は通りを見やった。同じような年頃の学生数人が、束となって練り歩いていた。皆、片手に風呂敷や綴った本を抱いている。ひそひそと話しながら、それらの視線はが居る書店を覗いていた。
「そんなことはない。今、書店に入ろうと思えば入れる。声をかけようと思えばそうすることもできる。同じ空気、同じ空の下。幻とは違う」
「……そうだな。ということは、俺にも見込みはあるということか」
杏寿郎が再び書店へ目を向けると、一人の学生が立ち止まっていた。は本を探すのに夢中になっているのか、それに気づく素振りもない。彼女の周りにはいくつもの可能性が転がっている。少し手を伸ばせばいくらでも。
「ちょ、真顔になるなよ。そこは笑うところだろ?」
「む、すまない!聞いていなかった!」
隊士はけらけらと笑う。それはどこにでも居る青年の顔だ。隊士はひとしきり笑うと、はーあ、と空を仰いだ。
「それで、買うのか?それ」
杏寿郎は手元に視線を落とす。つげ櫛が手に収まったままだった。
「買う」
「誰に?まさか、え!?」
「弟だ」
「兄弟いたのか、っていうか弟?妹じゃなくて?」
「俺が頭をくしゃくしゃにしたものだから絡まった。なんとか解いてやったはいいが、櫛が折れた」
「す、すごいな」
真っ直ぐに伸びた短髪を撫でながら、隊士は杏寿郎の頭をしげしげと眺める。
「心配ない。君の髪は絡まらない」
「いや、そうじゃなくてさ……」
杏寿郎は密かに刀へ指を這わせた。身を覆うのは無地の羽織。辛うじて腰の柄を隠している。
今日斬った鬼の顔が思い浮かぶ。鬼はこちらを嘲笑う。鬼は人の成れの果て。この世も地獄、あの世も地獄。この世は地獄の始まりだ。そう言って不快な笑みを浮かべる。
あのような穢れた生き物を斬ったものに触れるべきではない。それは彼女の定めではない。が刀に触れなかったことを、杏寿郎は心の裏で安堵していた。
「随分奮発したな。迷惑料ってやつか」
「迷惑料には足らないくらいだ」
「は〜、太っ腹。いい兄貴だこと」
杏寿郎のポケットへ向けられた視線には、驚きと感心が混ざっている。
「君の方こそ」
「いや、これは妹じゃなくて、」
「知ってる。妹に簪はあまり聞かない」
「……まぁ、弟に櫛もあまり聞かないけどな」
「ははっ、言えている!」
杏寿郎が店を出る頃にはの姿はどこにもなかった。詰襟の学生も居なくなっていた。まるで、彼女がそちらを知らないように、お前もこちらを知らないのだ。そう言われたようだった。

杏寿郎が屋敷に戻ると、千寿郎がいつものように庭で木刀を振っていた。
「書き物はいいのか?」
「はい、今日の分は終わりました」
「今日の分?」
「先日、姉上が書の本をくださって、稽古の合間にできるように日割りしてくださったんです。兄上、ブンブリョウドウとはどのような意味ですか?」
「学問と武道、両方に優れていることだ。が言ったのか?」
「はい」
彼女がどのように話したのかわからないが、千寿郎は嬉しそうに頬を緩めた。
「千寿郎、この前はすまなかった」
「え?」
「櫛を折ってしまっただろう」
「いえ、あれくらいどうってことないです。まだ使えますし、そんなこと気にしないでください」
「もう新しいのを買ってきた」
杏寿郎は隊服のポケットから包みを出した。真新しい和紙は櫛の色を透かしている。
「ありがとうございます、大切に使います!」
杏寿郎は千寿郎の頭にそっと手を添えた。母の腕に抱かれていたのが嘘のようだ。
「背が伸びたな!」
「本当ですか?!でも、兄上も……僕、早く追いつきたいです!」
「たくさん食べて、たくさん鍛錬して、寝て、また食べたら大きくなる!」
「はい!あ、お腹空きませんか?今日は鬼まんじゅうを作りました、兄上のお好きな芋も入ってます」
「鬼まんじゅう?」
「郷土料理で厄払いだと姉上が、鬼を食べて封じ込める意味があるとおっしゃっていました」
他にもは千寿郎に読み書きを教えているらしく、覚えたことを千寿郎は熱心に語った。
「どうやら姉上は知恵を教えるのが上手なようだ」
「兄上もお上手です……!明日は稽古を付けてくださいますか?」
「ああ、もちろんだ!」
それから、杏寿郎は鬼まんじゅうを頬張った。千寿郎はたくさん作ったと皿いっぱいにそれを出した。杏寿郎は千寿郎がコークの飴を捨ててしまったことをある意味でほっとした。
「うまい!!」
「よかったです」
「この饅頭はすごいな!芋がごろごろ入っている!」
「芋が肝とのことです」
「素晴らしい饅頭だ!」
「姉上は今日いらっしゃるでしょうか?」
「うむ、今日は来ないかもしれないな!」
杏寿郎は書店の光景を思い出した。
熱心に本を選んで、それからどこに行ったかもわからない。おそらく家に帰ったのだろう。だとすれば、今からが来ることはない。部屋の障子に影が伸び、日暮れが近づいていることを知らせた。
「そうですか」と千寿郎は一旦部屋を出ていくと、書物を持って戻ってきた。
「兄上、これはうちの書物でしょうか?」
これです、と杏寿郎に差し出すそれはそこそこの分厚さだ。一寸ほどある。
「これは辞書だ。辞書は用途によって様々だが、……は書き物をしていなかったか?」
「いえ、書き物はされていなかったと……あ、これを見ていらしたのですね」
よく見ているのだろう、辞書は角が擦れていた。しかし、物が良いのか破れている箇所はない。紙はいい風合いとなり、柔らかく手に馴染んだ。
「無いと困りますよね、早く知らせておけばよかったな……」
「最後に来たのは?」
「兄上が任務に行った日ですから、3日前でしょうか」
「ならば問題ないだろう。必要なら翌日でも取りに来たはずだ。それに今日も……」
「そうですね、姉上のことですからもう一冊お持ちなのかもしれません」
「これは次に会った時に渡しておこう」
千寿郎は皿を下げ、湯を沸かしてくると言って出ていく。
書き物をしているわけでもなく、辞書を見ていたというのはどういうことか。
杏寿郎は躊躇いながらもそれを開いた。辞書なのだから、それ以外は書かれていない。思いつきで【志】を引いてみるが、やはり何もない。どの辞書にもある言葉が書かれているだけだ。は本当にこれを読んでいたのだろうか。ぱらぱらとめくると墨ともつかない匂いが鼻を付く。インクと鉛筆と和紙。それは杏寿郎に健全な景色を彷彿させた。