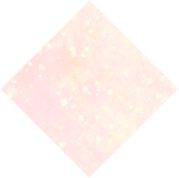第十一話
勉学に励むはずの学び舎。それが別のものへ変貌を遂げた。
は黒板を見て背筋を伸ばした。耳に入るのは教師の声、背後には保護者の足音。数名ずつ、代わる代わるやってくる。その視線は針を刺すように鋭い。晴子が来たらすぐにわかる。はそう考えていたが、全くの過信だった。
「さっきのあれは何だったの?」
見世物みたいだった、と愚痴をこぼす友人には大きく頷いた。数々の視線は我が子を見守るものとは違い、実母以上に疲労する。だが『母親参観』の目的を教師たちが黙認している以上、どうしようもないことだった。
「そういえばさん、今日のお着物少し地味ね」
友人の言葉に、は自分の着物に視線を落とす。小豆色の矢羽根柄、海老茶色や黄金色が多い中、濃紺の着物は確かに地味かもしれない。
「お母さまが洗濯に出したって。これしかなかったの」
「なるほどね。そう言えばさんのお母様は?お見かけしなかったように思ったけど……」
「必ず行くって言ってたから来てないことはないと思うけど、外で待ってるのかな」
「そうかもね。それより、さん。帰りの会が終わったらさっさと脱出、いい?」
手提げに教科書は詰め込んだか。筆入れは忘れてないか。時間割は書き留めたのか。
まるで母親のように細かい。「今日のお教室はキケンよ」と眉を潜める友人が面白く、くすりとしたはじろりと睨まれる。
「わたしは真面目に言ってるの」
「わ、わかってるよ。手提げを持って、校門まで急ぎ足。上級生に紛れて解散」
「そのとおり。とにかく油断はできないの」
参観日は午前授業。予定通り校門を出た友人はどこそこのご婦人に目をつけられまいと母親を急かし、足早に帰っていく。一人となったは晴子を探したが、やはり姿はない。どこに行ってしまったのかと考えていた矢先のこと。
「失礼ですが、あなたお名前は?」
振り返ると知らない婦人が立っていた。友人の言葉を借りるなら、この人物はまさに“どこそこのご婦人”である。名前を聞かれてこれほど返答に困ったのは初めてだ。
「緊張なさっているのね。可愛らしいお方だわ」
は慌てて回りを見渡したが、手を差し伸べる者はいなかった。それどころか羨ましげな視線を向ける者さえいる。
婦人は晴子が着る洋服と似た格好をしていた。履物は草履ではなくパンプス、羽のついた妙な帽子を被っている。ただでさえ目立つ校門で、が大人しく身を隠すのは難しかった。
—— 名乗ってはいけない。
は直感的にそう感じた。そして後頭部に意識が向く。友人に赤の花模様のリボンを借りたはいいが、何の役にもたっていないことに気づく。婦人の視線が頭部へ移り、はどきりとした。
「髪飾り、とても良くお似合いね」
「派手すぎます」
「まあ、ご謙遜なさって。」
は必死に回避する方法を探していた。友人にはエライ目に遭ったと言わなければならない。
—— わたしには煉獄さん、杏寿郎さんが。
「失礼ですが、わたしには、……」
そこからの言葉は続かなかった。笑顔の能面が迫ってくる。口元から漏れる笑みは温かみが感じられず、その瞳は貪欲だ。
もしや、これが杏寿郎の言う鬼だろうか?これらを日輪刀で斬るのだろうか。しかし、この人は斬っても斬っても生き返りそうだ—— そんな考えが浮かぶ。そのくらい、には目の前の貴婦人が恐ろしく映っていた。
「うちの娘に何か?」
ツンとした母の声をこれほど心強いと感じたことはない。
そうとわかればすることは一つ。は胸を張って婦人を見返す。
「お嬢様に少しお話をお伺いしたいと思いまして」
「急いでおりますのでその件は他をお尋ねください。失礼いたします。さ、行きますよ」
「はい。お母さま」
ちょっと、と婦人の声がするが、晴子は振り向くこと無く歩みを進める。
難所をくぐりぬけ、はため息をつく。
そしてため息を付いたのは晴子も同じだった。鋭い視線がの頭上を捉える。
「なんですか、その頭は」
「すみません、友人が厄除けというものでお借りしました」
「厄除け?まったく」
「……あ、あの、お母さま、リボンを外していただけないでしょうか?」
「言われなくとも外します!」
はあくまで借り物だと言ったが、晴子はさっさとリボンを取り去ると、手持ちの鞄へ押し込んだ。しばらくすると気が済んだのか、「……シワを払ってお返しします」と静かな声に戻っていた。それでも、「よりによって、」とぶつぶつと小言は耐えない。
不機嫌な母を前に、はどう言えば外出を許されるのか考えた。このままでは家から出るなといいかねない、そう思ったのだ。
「お母さま。今日、杏寿郎さんの御宅へ伺おうと思うのですが……」
「今日は止めておきなさい」
「実は、先日辞書を忘れたみたいで……授業で困るんです」
「辞書なら新しいものを持っているでしょ?」
「古い辞書のほうが詳しく載っているんです」
どうだろうか。
が晴子の顔色を窺うと、やや揺らいでいるようだった。
「行き先が杏寿郎さんの御宅とわかれば、あの方も追ってはこないと思います」
「それは、……それに着物も」
「大丈夫です。辞書を取ってくるだけなので」
「駄目です、着替えなさい。ただ……いつもの着物は御洗濯に出したのよ、困ったわ」
困ったわ、本当に。という母の言葉をはそのまま飲み込んだ。
晴子も困ったが、も困っていた。
「仕方ないわね……」
リボンで厄が付いたと思わざるを得なかった。
帰宅後、杏寿郎が全くもって関心を寄せない着物を着ることになり、は日を改めることも考えた。しかし、早めに辞書を取りに行きたかった。
「お母さま、行ってまいります」
は不安を抱えながら門を閉めた。

の緊張が和らいだのは、煉獄家が見えた時だった。声をかければいつもと同じように千寿郎が出迎えた。
「平日なのにいいんですか?」
「今日は午前授業で参観日だったの」
と言ったところで能面が思い浮かぶ。は慌てて周囲を見渡したが、雀が戯れているだけで特になにもない。
来たからには家事の手伝いをと考えていたが、千寿郎がこなしていて、のすることはほとんどなかった。洗濯は二人分ということで少なく、すぐにたたみ終えてしまう。夕飯の準備も風呂の湯を沸かすにも早すぎる。何もせずに座敷に座るとお客様になったようで落ち着かない。せめて何かないか、自分にもできることはないだろうか。
は千寿郎が淹れたお茶を飲みながら、しばらく悶々としていた。半分ほど飲み終え、やっと落ち着いてきたは千寿郎に切り出した。
「この前辞書を忘れたみたいなんだけど、見かけなかった?」
「あっ、あります!すみません、お困りになられたでしょう?」
「うーうん、それは大丈夫。一応代わりのものを持ってるから……杏寿郎さんは任務?」
「はい、今日帰る予定です」
「そうなんだ、いつ頃だろう……」
「夕方には戻るのではないかと、辞書、すぐ持ってきます!」
耳を澄ますと千寿郎が向かった方とは別の方から物音がした。はまさかと思ったが、さすがにここへあの貴婦人が来ることはないと思い直す。
—— 槇寿郎さん、かな……。
炊事場に向かった際、はいくつも酒瓶が転がっていたのを見ていた。すべて槇寿郎が飲んでいるのは違いないが、前よりも明らかに増えている。しばらく明るい声を耳にしていない。最後に面と向かって話したのはいつだろうか。
『よろしくおねがいします』その朗らかな声色は今でもの耳に残っている。頼まれたという思いのほかに、自分の未熟さを知らしめるようだった。それは時々の心を揺さぶった。
しんとした部屋は物思いに耽ってしまう。今のもそうだった。何かしたいと考えるが、どうすることが良いのか未だ見いだせない。
女学校では『他所の事情には口を挟んではならない』と教えがある。それを知った時、最もなことを言っているようで、の思考を妨げた。
「すみません、姉上」
「どうしたの?」
「だいぶ探したのですが、どうも兄上が持っているようで、どこにしまったのかわからなくて……」
「そっか、探してくれてありがとう」
「あの、本当に大丈夫でしょうか?」
「うん、急いでないから心配しないで。そうそう、千寿郎くんに辞書を持ってきたの。わたしは使っていたもので悪いんだけど、優しい書き方だからちょうど良いと思って」
は常々思う。
自分にできることをする。それは案外難しい。
「いいんですか?」
「わたしはもう使ってないから存分に使って!」
「ありがとうございます。そういえば、兄上が言ってました、姉上は知恵を教えるのが上手なようだって」
「えっと……千寿郎くん、杏寿郎さんになんて言ったの?」
「あ、僕は教えてもらったことを話しただけです。良くなかったですか?」
「そんなことないよ、ただ、杏寿郎さんが買い被っていらっしゃるから……」
は熱くなった耳を隠すように、後れ毛に触れた。そんなことをしても隠れはしないとわかっているが、どうも気恥ずかしい。千寿郎が気に留めた様子がないのは救いだ。
「先日鬼まんじゅうを作ってみたんです。そしたら兄上、ほとんど一人で食べてしまって。よほど気に入ったみたいです」
「任務帰りは腹が減るな!」杏寿郎はそう言って食べていたらしいが、気づいたときには一つになっていたと言う。最近はご飯もいつも以上に食べているらしく、米の減りが早いと千寿郎は言った。
「作り甲斐はあるんですけど、足らない時は焦ります」
「ほんとね。昔、たくさん稲荷寿司を作ってきたことがあったんだけど、覚えてる?」
「あぁ、いえ……」
「あの時も二段のお重の稲荷寿司があっという間になくなって。わたしは残る心配をしてたんだけど」
「はは、兄上らしいですね」
「そうね。でも、千寿郎くんもたくさん食べてたんだから」
「え、僕が?」
「うん。なんか懐かしいなぁ、また作ってみようかな」
辞書を持って帰るだけ。
はそう言って家を出だ。しかし、なかなか腰を上げる気にはなれなかった。
「ねえ、千寿郎くん。ひとつ変なこと聞いていい?」
「何でしょう?」
「その、鬼って言うのは……生き返るものなの?」
「はい、そのように聞いてます」
「えっ」
「でも、日輪刀で急所を斬ると滅びます。陽に当たると燃え尽きる」
「そう、なんだ……」
さらりと述べる千寿郎に驚く。
は密かに「そんなことないですよ」というのを期待していたのだ。
「それがどうかしたんですか?」
「今日、鬼みたいな人に会って、どうしたら追い払えるのか気になって……」
「えっ!」
「あっ、鬼ではないの!人だと思うの、というか人、貴婦人……。学校に鬼は来ないと思うし、それに、ハイヒールなんて履いてないと思うし、それに羽のついた変な帽子なんてかぶってないと……」
千寿郎が怯えているのに気づき、は慌てた。こんな話をしに来たわけではない。あくまでも辞書を取りに来ただけ。怖がらせに来たわけではないのだ。
「その、何ていうか……女学校は色々あるみたいね」
早く帰ってきてくれないだろうか。は何度も玄関に耳を澄ました。
それに気を取られ、は千寿郎がさらに不安な顔を浮かべたことに気づかなかった。
は最初、学校に置き忘れたのだと思っていた。しかし学校にも家にもないとなればここしかない。置いていった辞書は線を引いたものだ。もし、杏寿郎が見たら変に思うかもしれない。それに気づき、早めに手元に置いておきたかった。
それと、ほんの少し。
ひと目でいいから杏寿郎の顔を見たかった。
出来心で聞くものではなかったと分かったときは遅かった。今では言いようもない不安がの中で渦巻いている。千寿郎の言葉は杏寿郎が何をしているのか、少しずつ見えてくる。鬼は生き返る。それは何度でも向かってくるということだ。鬼が日輪刀で頸を斬られるのを心待ちにしているのなら話は違うが、そんなことはないに等しいだろう。
は日没間際まで粘ったが、結局、杏寿郎は戻らなかった。家に帰れば鬼の形相をした晴子が待ち構えているだろう。帰りに貴婦人と出くわすかもしれない。
やはり厄を付けたのだ。はそう思わずにはいられなかった。