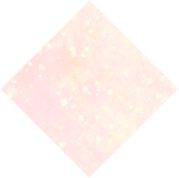第十二話
時刻は零時を過ぎようとしていた。
ハイヒールの鬼。羽の付いた鬼。女学校に鬼。
帰宅した杏寿郎は、千寿郎の言葉を噛み締める。
「千寿郎、もう一度ゆっくり話してくれないか?」
「はい。ハイヒールを履いた鬼が、羽のついた帽子をかぶって、真昼に女学校へ行く……ということはあるのでしょうか?」
任務が長引き予定より帰宅が遅れた。やっと家に着いたと思えば、とっくに寝ているはずの弟が泣きそうな顔をして待っていた。がくれたという辞書を抱えて、玄関に座り込んでいたのだ。
最初は千寿郎が寝ぼけているのではないかと思った。しかし震える声で「姉上が、」と言われ、杏寿郎はの身に何か起こったのだと思った。だとしたらさすがに父が、と考えたが、槇寿郎は酒を呷り眠り込んでいる。
真夜中となった今、何をしようにも時間が経ち過ぎていた。
「がそう言ったのか」
「はい。あと、鬼は斬っても生き返るのか、ともおっしゃいました」
「それで、千寿郎は何と答えた」
「日輪刀で急所を斬ったら滅ぶと、あと陽の光でも……」
「うむ。何度も言うが真っ昼間に鬼が出ることはない。羽の帽子とやらをかぶっても昼間に生き長らえることはないだろう。おそらくそれは鬼のような人であって、鬼ではない。つまりは、に聞かないことには何のことかさっぱりわからん!」
「そうですね、すみません……」
不可解ではあるが、これ以上千寿郎を問いただすことはできない。
尚も不安げな表情を浮かべる千寿郎に杏寿郎は言った。
「明日は非番だ、俺が家に行って詳しく聞いてこよう。ついでに辞書も返してくる」
「そうでした、姉上は辞書を取りにいらっしゃったのに……」
「辞書の件はすまない、また紛れると思い引き出しに入れておいたのを言いそびれた。とりあえず今日はもう遅い、千寿郎も早く布団に入りなさい」
「でも、……」
「心配ない!何かあればの母上が連絡をくださる!」
「はい」
少し安心したのか、「おやすみなさい」と眠たげな顔をして千寿郎は自室へ入っていく。
千寿郎の言うように、どのような格好の鬼も存在するだろう、女学校もありえなくはない。ただし、日中に鬼が出たとしたら鬼殺隊で大騒動になっている。
が日没間際まで待っていたのは他にある。
杏寿郎はそっと戸棚から辞書を取り出した。やはり何度見ても普通の辞書にしか見えなかった。

杏寿郎は門の奥へ視線を向けた。周りの住宅こそ変わりはしていたが、立派な洋館は今もそのままだ。
玄関には呼び鈴と思われる丸い鉄がぶら下がっていた。鉄紐で音が鳴る仕組みだ。杏寿郎は試しにそれを引いてみた。その音は鈴より重く、寺の鐘より甲高い。
一つ奥の通りから下校する子供の声がした。軽く明るい声は近寄っては遠ざかり杏寿郎の耳元を抜けていく。片や家は、樹木がすべての音を吸い取ったようにそれは静かなものだった。
ひょっとしたら留守かもしれない。杏寿郎はそう思ったが、思いの外早く開いた。
「お待たせいたしました……あら、杏寿郎さん」
あの時と同じく、玄関からの母が顔を出した。
「こんにちは!お世話になっております。さんはいらっしゃいますか?」
「生憎、娘はまだ学校から戻っておりません。どういったご用件でしょう?迎えに行きましょうね」
「いえ、迎えなどは結構です!渡したいものと、少しお伺いしたいことがあります」
晴子の視線が小脇の風呂敷へ注がれる。
「わかりました。ではどうぞ、中でお待ちください」
「はい、失礼します」
「お越しになるのはいつぶりでしょうね……」
客間に通され、杏寿郎は懐かしく思った。家に足を運ぶのは約七年ぶりのこと。しかし、今日は一人きりだ。部屋もあの時より少し狭く感じる。ただ、どこからともなく香ってくるそれには覚えがあった。が持っていた回るおもちゃと同じだ。
「杏寿郎さんはお茶と紅茶、どちらがお好きですか?」
「どうぞお構いなく。お話したらすぐに帰ります」
晴子は察したように「お茶をお持ちしますね」と、部屋を後にした。以前目にした段違いの棚は様変わりし、今はガラス戸の棚が鎮座していた。戸棚には陶器やガラスの茶器、酒と思われるガラス瓶がいくつも並び、煌びやかな雰囲気が増している。
しばらくして戻ってきた晴子は、杏寿郎の前に緑茶とくず餅を差し出した。
「皆様お変わりありませんか?」
「はい、おかげさまで……父は、相変わらずです。益々酒が増えたように思います。ですが、元気にしております。弟も変わりなく元気です」
こちらをじっと見るそれはと似た色をしている。だが、晴子のそれはもっと重く、杏寿郎は身が引き締まる思いがした。
「そうですか……。杏寿郎さんもお怪我もなくお元気なようで良かったです。そういえば先日、娘が香を頂いたと大変喜んで。気にかけていただきありがとうございます」
晴子は深く頭を下げる。大人と変わらない対応に杏寿郎は少しばかり戸惑った。まるで任務途中に立ち寄る藤の家のようだ。
「杏寿郎さん」
「はい」
「何かあれば、いつでもおっしゃってくださいね……。娘のことも」
「……はい、ありがとうございます」
「昨日娘が伺ったと思うのですが、また変なことを言って騒がせたでしょう。どうも心構えが足りないところがあるから……。私には辞書を取りに行くと言ったけど、本当は違ったんじゃないかと思っているの」
晴子は探るように杏寿郎を見て、母親の勘をちらつかせた。それは杏寿郎が抱いていた疑念を確信へと変えさせた。やはりは何か言いに来たのかもしれない。だが、晴子でさえそれを知らないとなれば、やはり本人に訊く他ない。
「昨日は帰りが遅くなったものですから、お会いできませんでした。それで今日お伺いしました」
「あら、そうだったの……」
意外だと言いたげに、晴子の声が淀む。だが、すぐに落ち着いたものに戻り、悩ましげに眉を下げた。
「あの子の未熟が、あなたを傷つけていないといいのだけれど……」
「そのように感じたことはありません!未熟と言うのは俺も同じで、なかなか腕も上がらず……まだまだです!」
「……いいえ。杏寿郎さんは十分にご立派です」
晴子は目を細める。
すると玄関から来客を知らせる音が伝わった。
「すみません杏寿郎さん、少し外します。この部屋は自由に見てくださって構いませんので」
「はい」
晴子が席を外すと、部屋は時計の音に包まれた。針は四時をとうに過ぎている。杏寿郎は学校が終わる頃を見計らって来たつもりだった。手持ち無沙汰となり、杏寿郎は部屋へ視線を巡らせる。
—— そういえば、あれはどこに。
昔自分を見ていた虎の置き物。取り去ってしまったのか見当たらず、杏寿郎は残念に思った。
「—— です……来客中です。 お引取りください」
扉の向こうから晴子の強い声色が杏寿郎の耳に入った。物売りのようだ。その手の者は煉獄家にも時々やってくるが、大抵は藤の家から贈られる品で間に合っていて断るのに苦労する。そういう時も槇寿郎は知らん振りだ。しかしある時、長引くやり取りが癇に障ったのか「いい加減にしろ!」と槇寿郎が一喝した。それ以来、物売りはぱったりと来なくなり、噂が噂を呼んだのかそれきりだ。善良とは言えないが、少なくとも千寿郎は困らずに済んでいる。自身の家でそうなのだから、当主が不在の晴子やはもっと困るだろう。
—— 自分が行くべきか。しかし、余所者が断るのも失礼か。
杏寿郎がそんなことを考えていると、晴子が戻ってきた。案の定困った顔をしている。
「物売りですか?」
「ええ……あまりにしつこいと困りますね。それにしても遅いわね、どこに寄り道しているのかしら」
「俺が見て参りましょう」
「いいえ、杏寿郎さんはここでお待ちになられてください」
晴子は急かされたように玄関へと向かった。かと思えば、すぐに戻ってきて盆を抱える。お茶を淹れ直すようだ。
「今、が戻りました。すぐに来ますから」
晴子の言葉通り、間も無くしてが客間にやってきた。
「杏寿郎さん!」
扉を開けるなりは小走りで入ると、手提げを脇に置き、杏寿郎とは向かいの席へ腰を下ろした。
「お待たせしました、まさかお越しになってると思わなくて……」
「連絡もせず急に来てすまない。昨日、随分待っていてくれたそうだな。千寿郎から聞いた」
「昨日は午前授業で、おしゃべりに夢中になって長居しちゃったんだけど、……」
「それは構わない。千寿郎が妙な事を言うものだから、にも聞いておこうと思って今日は来た」
妙な事、とは考えるように杏寿郎を見る。
「千寿郎は鬼のような人がどうとかと言っていたが?」
「あっ、そ、それは違うの!鬼のような人がいたって言っただけで、杏寿郎さんの言う鬼とは違うの。紛らわしい言い方だったね……ごめんなさい、わたしのせいね」
いつになく焦った様子のは一頻り話すと黙り込んだ。途中、晴子が新しくお茶を出しに来たが、口を挟むことはせず部屋を出た。は両手で湯呑みを持ったまま、ただ見つめるばかりで口にする気配がない。
「心配するな、千寿郎には俺がきちんと説明しておく。ただ、その鬼のような人というのが何者か気になっただけだ」
事情があると察し、話を切り上げようと杏寿郎は持ってきた辞書に手をつけた。
「昨日、参観日だったの……」
「参観日?」
「親が授業を見学することを許される日」
授業が終わり、校門を出ると見知らぬ婦人から声をかけられた。その剣幕があまりに恐ろしく鬼のようだと思ったのだと彼女は言った。
「その婦人は物売りをしているのか?」
「物売り?……どうだろう、そうなのかな。でも、昨日はわたしも悪いところがあったと思うし、次はちゃんとできると思う」
は話すというより自身に語っているようだった。
本当ならもっと詳しく訊くこともできただろう。ただ、それを知ってはならない気がして、杏寿郎は思い留まる。
「今日の用はもう一つ、辞書を持ってきた。俺が引き出しに入れたものだから、千寿郎が探し出せなかったみたいだ」
杏寿郎は手に持っていたそれを差し出した。は「あっ」と顔を上げる。
「わざわざありがとう」
「こんなにも辞書を使い込むとは、はなかなかの勤勉家と見る!」
「そんなことないよ、わたしは物を知らないから、本当に……わからないとすぐに辞書を引いてしまうの」
変な癖よね、とはそれを受け取ると、ささと着物の袖で隠した。
「辞書といえば、ありがとう。千寿郎がわかりやすいと喜んでいた」
「お古でごめんね、最初に買っていただいたもので……でも、良かった」
はもう一度礼を言うと辞書を手提げへしまった。それからすっかり冷めたお茶に手をつけ、ほっと息をついた。
しばらく沈黙が続いた。カチカチと振り子が時を刻んでいく。今までにない長い沈黙だった。時計の音が強くなる。そろそろ鐘が鳴りそうだ。杏寿郎がそう思っていると、顔を上げ真っ直ぐに見たと視線が絡んだ。
「杏寿郎さんの瞳はいつも綺麗ね」
「ん……そんな風に言われたのは初めてだ」
変わった眼。変な色。そのように言われることは多々あった。慣れているし、先祖から受け継いだものに不満を感じたことはない。誇りに思っていた。けれども、上手い言葉がでてこない。ふっと湧き上がった熱が一気に全身に駆け巡る。
杏寿郎が言いようのない気恥ずかしさに窮していると、が「あのね、」と語りかけた。
「本当は、昨日遅くまで待っていたのは、その、……杏寿郎さんに逢えるかもって——」
そこでゼンマイが一際大きく唸る。掛け時計の音が鳴り響き、は名残惜しそうにそれを見た。ここが煉獄家なら帰宅していなければならない時間だ。窓の外を見て、ははっとした顔をする。
「ごめんなさい、だいぶ暗くなったね、杏寿郎さん大丈夫?」
「……そうだな、そろそろお暇しよう」
玄関まで来るとも草履を履こうとしたのを見て、杏寿郎は慌てて止めた。
「見送りはここまでで結構だ、ありがとう」
は渋ったが、そばに来た晴子がそれを制した。そして杏寿郎にだけ分かるように小さく頷く。それに応えようと口角を上げ、ふと視線を感じた杏寿郎は玄関の飾り棚に目を向けた。
「杏寿郎さん、今日はありがとう。気をつけて帰ってね。またお伺いするから、それから千寿郎くんにもよろしくね、あとは、その……また」
「ああ。では、失礼します」
杏寿郎が門を出ると、背後から杏寿郎さんとの声がする。玄関から身を乗り出し、こちらに手を振っていた。見えなくなるまで見ている気なのか、はなかなか家に入ろうとしない。杏寿郎が戻ろうとすると、晴子に促されようやく中へ入っていった。
杏寿郎は閉まったばかりの玄関を見る。曇りなき眼で見るを思い出し、急に熱さが振り返した気がした。思わず頭を振って、ある一点に目が留まる。
住宅の裏側に面する方にわずかに藤の花が顔を出している。杏寿郎はさらに目を配ったが、やはり藤の家紋はなかった。
昔は睨まれていると思った虎が、今日は違って見えた。
お前はそれくらいか?まだまだだろう。
そう、問うてきた。
杏寿郎の草履に力が入る。それに答えるように、しっかりと前を向く。
もう少し、あと少し。
足元を救われないように、一歩一歩踏みしめるように。