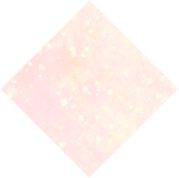第十三話
若葉の茂る季節。
時代は明治から大正へ。新たに時はめぐり、は十六を過ぎた。安泰な学校生活。杏寿郎も千寿郎も変わらず接してくれる。穏やかな日常だ。
「いたっ」
指先にぷっくりと血がにじむ。
洗濯したばかりの衣服にシミをつけないよう、は慌てて傍に避けた。千寿郎に縫い物の手本を見せようとしていたはずが、あるまじき失態だ。
「大丈夫ですか?」
「うん」
は手を拭い、もう一度針を手に取った。
「もう、三十回!」
屋敷の奥から杏寿郎の声がする。
「まだだ!顎は引く!腰も低く!振りが甘い!右足は踏み込む!」
杏寿郎は昨年から弟子を取っていた。しかし訪れる度に顔ぶれが違う。ある日いつものようにが煉獄家を訪れると、裸の木刀を片手に素足で草履をひっかけた少年が、「も、もう無理ですっ」と泣きながら門を飛び出していった。今は別の弟子が付いているが、泣いているのか「ふぁいっ!」と言う返事はしゃっくり混じりだ。千寿郎曰く、杏寿郎の稽古は人一倍厳しいと有名らしい。
「相変わらず手厳しいな」
声高らかな兄の声に、千寿郎は不憫そうに呟く。
「……よし、できた」
きっちりと縫い付け、今一度綻びがないか確認する。こうして広げてみると意外と大きい。が縫っていたのは杏寿郎のシャツの釦だった。杏寿郎が着ている白いシャツはかなり上等だ。見た目は市販のものと同じようだが、縫い物をしているとよく分かる。これも制服同様に支給品だという。だが、縫い付けが甘いのか、度々釦が取れかけていた。
「どうかしました?」
「うーうん」
が千寿郎を見ると、弟子の袴を畳み終わったところだった。襞も綺麗に揃えている。
「あの、千……」
素早い足音がの言葉を遮る。だんだんとこちらに近づいてきて、スパンと襖が開いた。
「千寿郎、隊服のシャツを知らないか?!」
「兄上、何か上を着てください!」
「すまない!脱衣所にシャツを置いたはずが、……」
首に手ぬぐいを下げた杏寿郎と目が合った。その顔は「なぜここに?」と告げている。と言うのも、この部屋はいつもの居間ではなく千寿郎の自室なのだ。
「ぬ、縫い物を教えていたの」
「そうか!縫い物を!」
「シャツ、これでよかったらどうぞ。釦を縫ったばかりだけど……」
逸らすこともできず、は手元のそれを差し出す。
「ありがとう……!」
の手からシャツがするすると逃げていく。千寿郎が何か言っていたが、はそれどころではなかった。自分が何をしようとしていたか思い出せない。千寿郎に何か言おうと思っていた。なんだっただろうか、そうだ。
「わたし、お茶の準備をしてくるね」

その翌日。いつものようにが教室へ入ると、しくしくと涙を流す学友に同情の視線が集まっていた。
食事を作ったり掃除をしたり、着物を用意するのは許婚のすべき事ではない。
彼女はそう言って腕に顔を埋めて泣いていた。嫁ぎ先がそのようだと知らず、動揺しているのだ。
「私、騙されたんだわ」
それにも衝撃を受ける。何がそんなに悲しいのか全く理解できないこともある。
「それって、」
団子になった視線がを貫く。余計な言葉だったとが後悔していると、窓際の一人がハッとした顔で席に着いた。すると蜘蛛の子を散らす勢いで学友たちは離れていく。教師がちらりと教室を覗く。その足音が遠ざかると、の声どころか彼女の嘆きさえも無いものとなり、その話題はそれきりとなった。
二十名ほどいた学友が一人、二人と教室から居なくなったのは昨年の暮からだ。別れの言葉は「おめでとう」自主退学だ。退学と言うと聞こえは悪いが、この教室においては別の意味を指していた。
自習という名の縫い物をしながら、はそれとなく友人に言った。
「あれからセンセイとのお話は進んでる?」
「ええ。順調よ」
友人は例のセンセイと一緒になると決めている。願いは叶うもの、叶えるものを見事に実行したのだ。両親は婿養子として秀才を招き入れようという魂胆だ、と彼女は話す。こんなことは言いたくない。けれども、は黙っていられず、重い口を開いた。
「気分を悪くしたらごめんなさい。センセイとのお話だけど……騙されるというか、良いようにされてるとか、そういうことじゃないよね……?」
は恐る恐る友人の顔を覗き込んだ。もう二度と口を利かないと言われるかもしれない。だが、友人がおかしな目に遭うのもは嫌だった。
「そうかもね」
「そんな、」
「でも、わたしはセンセイの学帽とお顔に惚れ込んだわけじゃないのよ」
訊けば“センセイ”は研究者だった。研究には膨大な時間と費用がかかる。どんなに優れた学生でも一人でその費用を工面することは不可能に近い。時間はどうしようもないが費用ならどうにかできる。彼女はそのように考えていた。
「最初は何のお話をされているのかわからなかったけど、わたしはその研究がいつか素晴らしいものになると信じてる。だから、金のなる木にしか思われていなくても構わない」
「そんな言い方しなくても……」
「立場はそう変わらないわよ、わたしたち。結局、行き着く先は同じなんだから」
そう言って、彼女は目標として掲げられた『良妻賢母』の張り紙を見る。その横顔は少し淋しげだ。
「さんこそどうなの?最近ちっとも話題に上がらないじゃない」
「お忙しい方だから……それより、釦が取れにくい縫い方を知らない?」
「9頁の応用。襟首はよく取れるのよね。わたしもセンセイによく縫ってくれって言われるの」
は教科書の9頁を開いた。釦の縫い付けが複数載っている。
「これね、ありがとう。……胸元の釦は取れないの?」
「胸元なんてめったに取れないと思うけど。どうして?」
「その、なんとなく。あと……たぶん、センセイはそんなふうに思ってないと思うよ」
そうでなければ、わざわざ彼女の帰宅を待って釦付けを頼む必要がどこにあるのだろうか。友人の家には3人も女中が居るのだ、頼もうと思えばいつでも頼める。
友人は小さな声で「ありがとう」と告げると、針山に縫い針を挿し込んだ。糸切狭みで桃色の糸を切り落とす。
鐘が鳴り、自習時間が終わる。あとは帰宅するのみだ。
が手提げに道具を詰めていると、他の学級の友人が廊下の窓から顔を出した。
「さん、紳士がいらしているわよ」
「えっ」
驚いたのはだけではない。教室が少しざわついた。友人もニヤリとした。
杏寿郎が女学校に来たらさぞかし目立つにちがいない。しかし、廊下に出ても然程賑わっている様子もない。慌てては校門へ向かう。
手を振った人物を見て、はどれほど自分が浮かれていたのか思い知った。
考えてみれば、学友が杏寿郎の顔を知っているはずがない。それに学友は紳士と言った。背広を着てすらりとした様は絵に書いたような『紳士』そのものであった。
「すまないね、キョウジュロウくんじゃなくて」
と、その口調は全く悪びれた様子はない。
「どうしてお義兄さんが……姉が来てるんですね」
は落胆と同時に杏寿郎が不在であることを思い出した。今日から長期の任務だと。どれくらいかと訊けば、「遅くても一ヶ月くらいではないでしょうか?」と千寿郎から聞かされたばかりだった。
遠路はるばる姉夫婦がやってきた理由は一つ。
「ご誕生、おめでとうございます」
「ありがとうございます」
姪が生まれた。晴子に孫の顔を見せに来たのだ。しかしは浮かない顔をしていた。もちろん可愛い姪は気になるが、姉の言葉も気がかりだった。原因は先日の手紙にある。「お元気ですか?」から始まったそれは、
“—— 近頃ちっとも手紙をくれませんね?勉強ばかりしているのではないですか?婚姻のお話は進んでいますか?煉獄家の方とはうまくやれていますか?”
と、つらつらと書かれていた。
の姉はまさに良妻賢母を地で行くような人物だった。学校も十五の秋に自主退学し、自ら嫁ぎ先で嫁入りの準備をするような人だった。
もしも「許婚と思われているか疑問だ」と言えば、姉は即刻別の縁談を持ってくるだろう。そう考えると、の不安は募るばかりだ。
が憂鬱な気分で玄関を開けると、赤子を抱いた姉が待ち構えていた。
「おかえりなさい、遅かったわね」
その雰囲気は受験時の講師を思い出させる。当然ながら、楽しいはずの団欒も楽しめない。
「父様は相変わらずね。母様はよくやっていらっしゃると思う。は学業に力を入れすぎね。もっと大事なことがあるんじゃないかしら?」
言い方を変えながら、姉は度々を突いてきた。そうかもしれないですね。そうだったらいいでしょうね。と、はあらゆる答えを出したが、「そうですね」とは絶対に言わなかった。断固としてそれを言わない妹に姉がしびれを切らすのは時間の問題だったのだ。
「そうね、そんなにアレなら明日伺いましょうね」
はぎょっとした。箸から人参がぽとりと落ちる。
「いっ、いきなりはご迷惑になります!」
「お顔を拝見するだけよ」
「赤ちゃんは?連れてはいけないよ?通りは人が多いのに、悪い病気でも感染ったら……」
「一時間もかからないし、母様に見ていただくわ」
はっとしては晴子の顔を見る。母は義兄に葡萄酒を勧めていた。黙認する気でいるようだ。それもそうだろう、母は娘と違い初孫の面倒を見るという楽しみがある。不都合どころか好都合だ。
とにかく言い出したら聞かない。姉はそういう人だったということをは食卓でじっくりと思い出していた。

結局、姉には逆らえない性分で、は煉獄家に足を向けることとなった。居ないかもしれない。何度言っても姉は構わないの一点張りだ。今日逃したら次はいつになるか分からない、と。
「明日死んで後悔したらどうするの?」
「……そんな野蛮なこと、言わないでください」
むっとしたを気にもとめず、姉は他所に目移りしている。
「あ、その前にちょっと買い物をいい?やっぱり東京は物が違うわね」
帰りの列車に間に合うように、そう言ったのは姉。それなのに、とにかく寄り道が多かった。それをにこにこと見ているのは義兄だ。
「……姉はいつもああなのでしょうか?」
「そうだね。まあ、久しぶりに外に出たからはしゃいでいるんでしょう」
そういうものか、とは子供服や雑貨を選ぶ姉をぼんやりと眺める。
「そういえばちゃん、こういうのしないんだね」
似合うと思うよ、と棚に下がっていた大きなリボンをの髪に当て、義理の兄はうんうんと一人頷いている。にとって鬼門とも言えるそれは数年間で大流行。髪留屋にとどまらず、雑貨屋や呉服店にも置かれている。女学生だけでなく、今や女子になくてはならない存在として君臨していた。
「花の飾りもいいけど、たまにはこういう物も付ければ、ね?」
意味深に言われ、は閉口する。
リボンより、竹刀を振るえる方がよほど良いのではないか。近頃の杏寿郎を見ていると、どうしてもそう考えてしまう。自身、曲がった思考だと感じてはいる。だが、正そうとすればするほどおかしなことになってしまう。そんなこともあり、は姉に手紙を出さないと決めた。学校の話も特に書くことはない。たった三行の手紙など何の面白みもない。
「ねえ、ちょっと来て」店内から姉の声がする。「はいはい」と様子を見に行く様は良夫。どこにでもいる夫婦の像。女学生が羨むその姿は、教科書の“幸せの縮図”を見せられているようだった。
立派な塀が立ち並ぶ住宅街は、昼でも静かなものだった。
一角を曲がり、の足取りは次第に重くなっていく。すると、不意に姉の夫は足を止めた。
「僕はここで待ってるよ。さすがに荷物を持って伺うのは失礼だ」
「そうね、お願いします。、煉獄さんの御宅はこちらでいいわよね?」
「は、はい」
はこっそり姉の顔を盗み見る。何を言い出すのか見当もつかない。
そうこうしていると、門の外で掃き掃除をする少年が見えてきた。もちろんその姿は千寿郎だ。
「あちらが煉獄家の次男、千寿郎さんです」
「そう、あちらね」
姉さま、とは声をかける。しかし全く耳に入れることなくの姉は千寿郎の前までやってきた。そして、
「こんにちは。千寿郎さん」
案の定、千寿郎は困った顔をしている。をみて「姉上」と一端は言葉にしたが、すぐに口をつぐんだ。
「こんにちは。……あの?」
なんだろう、そう言わんばかりの面持ちで千寿郎はに問いかける。
「千寿郎さん。こちらは、わたしの姉です……」
「えっ?!」
そんなの聞いていない!千寿郎の心の声が飛び出したようだった。杏寿郎とそっくりの目をまん丸にしてこちらを見る。
戸惑う千寿郎を見て、は思う。自分は今どんな顔をしているのだろう。
「どうもはじめまして。突然の訪問をお許しください。近くに寄ったもので、ご挨拶に伺いました」
姉の姿は母、晴子そのものだった。
目の前で優雅な佇まいを見せつけられ、はただただ口を閉ざす。
「は、はじめまして。煉獄千寿郎と申します。いつもお世話になっています。すみません、兄は外出しておりまして、今日は戻らず……あの、よろしければどうぞ、お上がりください」
「お心遣いありがとうございます。ですが、それには及びません。お目にかかれて良かったです。早々ですが失礼いたします」
はくるりと背をむけた姉と、おろおろする千寿郎を見比べた。本当に顔を見て帰るとは思わなかったというのもある。奇妙なやり取りに、千寿郎はぽかんとしている。
「ええと、そういうことですので、また来ます、また……」
はひらひらと手を振ってみたが、千寿郎はぼうっとしたままで、箒を手から滑らせ、ようやく我に返っていた。
角を曲がるとそこに義兄の姿はなく、は辺りを見回した。しかし、どこにもいない。そこで二人が打ち合わせ済みだったのだと悟った。姉はまぎれもなく千寿郎に会いに来たのだ。
疑問を浮かべるに姉は言う。
「千寿郎さん、可愛い弟さんね。てっきりうまくいっていないのかと思ったけど、そうでもなさそう」
「どうして、会ってないのに……。わたし、反対しにきたのかと思った」
「お顔が穏やかだった。私は杏寿郎さんを呼んでほしいと言っていないのに、すぐにわかってくださった。それに“姉上”なんて嫌いな人に言えないでしょ?が言っていたように杏寿郎さんも良い人でしょうね」
達観した言葉を吐く姉に、は恐れすら覚えた。うんともすんとも言わないを見て、姉は呆れた顔をする。
「悪いようなら母様が何か言うもの。それにしても、どうして反対すると思ったの?」
「それは、……」
は二の句を告げなかった。すべてを話すと今度こそ本当におかしなことになる、そう予感した。
「許婚に恋煩いするなんて、変わってるわね」
「ちがっ、そういうのじゃなく、違います」
「さあ、帰らないと。汽車に乗り遅れてしまったら大変。結構お高いのよ」
駅の乗降場は混んでいた。夜行列車で移動をする人は多く、は混雑した空気に圧倒される。それに驚いたのか、寝ていた姪が泣き出した。けたたましい声は千寿郎が泣いていたときよりも大きく感じる。
「お乳が足りないのでは?」
「さっきあげたばかりよ」
「……そう」
「おしめも替えたばかりなのに。ほら、おばちゃんの袖をはなしなさい」
「おばっ」
「もう、本当になんで離さないの?なにか持ってる?」
「え?」
は考えたが特に赤子が好きそうなものは持っていなかった。その間も小さな手が着物の袖を握っている。考えた末にが匂い袋を出してみると、ピタリと泣き止んだ。
「ああ、お香。そういえばずっと家でも焚いてたものね」
赤く小さな手が懸命に袖を握りしめ、顔をくしゃくしゃにしたかと思えばつぶらな瞳がを見上げる。それを見ていると、千寿郎の時にも感じた未知が再び顔を出した。
この世界はこの子にはどのように見えているのだろう。
「……それ、あげるね。ずっと泣いてたらかわいそう」
「でも……悪いわね、ありがとう」
「ねえ、姉さま。……気をつけて帰ってくださいね」
「ええ、またね。また来るから。も早く帰るのよ」
出発の合図が鳴り響く。は小さくなる列車を見ながら思う。
今度手紙で聞いてみようか。
姉さま、鬼狩りって知ってる?
沈みゆく夕日を見て、は駆け足で駅を後にした。