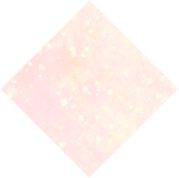第十四話
「無事着いたそうですよ」
手紙を手にした晴子は娘夫婦の帰郷を知り、ほっとした顔をした。その傍ら、はテーブルの小包を見た。荷物は姉が送りつけてきたものだった。
急いで開けてみると、中には見慣れない品が入っていた。チョークのように細長い形をしている。同封された一筆箋には口紅と書かれていた。先日のお礼とある。もしかしたら、とは箱の底を探ったが、くしゃくしゃの藁半紙以外何もではしなかった。
「のそれはなんだったの?」
晴子は棚から便箋を探しているところだった。テーブルの上にはの姪の写真が数枚並べられている。まったく気分の上がらない娘と違い、母は珍しく鼻歌まじり、上機嫌だ。
「口紅をいただきました」
「そう。一緒にお礼を書いておきましょうね」
「はい、お願いします」
あの後、は思いつく限り商店で同じ物を探した。だが、似たような物はあってもあのような香りのするものはどこにもなかった。
着物から香る匂いは日に日に薄くなっていく。いつまでも同じ着物を着ることはできず洗濯に出すが、完全に消えてしまった香りはに罪悪感という形で主張した。

「本当にごめんね、姉は言い出したら聞かない人だから」
千寿郎は洗濯物を畳みながら、の話を聞き入っていた。先日の訪問には驚いたようだが、理由を知ればが思うよりもすんなりと受け入れた。
「今思えば、晴子さんによく似ていらっしゃった気がします」
「そう、母そっくり。わたしも会ったのは数年ぶりだったの、なかなか会う機会がなくて」
「そうですよね、遠くにいらっしゃるのなら尚更です。えっと、神戸というと……船でいらしたんですか?」
「うーうん、汽車、特急列車」
船は酔うから嫌だ。そう言っての姉は時々晴子を呼び寄せていたが、鉄道の開通はの姉にも大きな影響を与えていた。
「そう言えば、お止めになったんですか?」
千寿郎はの袖を見た。香りがしないことに気づいていたらしい。
「うん……実は、姪にあげたの。駅でずっと泣いて、わたしの袖を離してくれなくて。それで杏寿郎さんに謝ろうと思ってるんだけど、……」
近頃、は杏寿郎と会うことが少なくなっていた。昼に訪れても杏寿郎はさっさと任務へ出てしまう。夕方に杏寿郎が戻ればは帰宅しなければならない。日中、寝ているところを起こすわけにもいかない。完全に入れ違いだ。併せて弟子の出入りもピタリと止んで、最近の煉獄家はしんとしていた。
千寿郎が慣れていて、自分が慣れていないだけか。は思う。
「杏寿郎さんがいらっしゃらないと静かね」
「兄上は声が大きいので、余計にそう思うのでしょう」
外を見ていると土の湿った匂いが縁側から流れ込んできた。しとしとと降り出した雨はやがて本降りとなって地面を濡らす。風が吹いてきたのかカタカタと障子が踊っている。千寿郎が立ち上がったのを見て、も立ち上がり後に続いた。何をするのかと思えば裏庭の雨戸を閉めるらしく、千寿郎はせっせと戸板を運び出した。それを見て、も真似る。
「姉上は座ってまっていてください、けっこう力が要りますので」
「これくらい大丈夫よ、この板はどこでもいいの?」
「それは左側です、真ん中あたりに四と書いてますよね?」
「四……わかった、左ね」
身幅以上の一枚板を抱えるのはにとって一苦労。千寿郎はすっかり慣れた様子で次々に戸を閉めている。日頃から鍛錬しているためか、軽々と持ち上げていた。
「本当に重いので気をつけてくださいね」
「うん……千寿郎くん、これってここでいい?ちっとも前が見えないんだけど合ってる?」
「はい、合ってます」
下を見れば上が揺れ、上を合わせると下が外れる。うっかり溝からはみ出ると外に落ちてしまう。千寿郎が三枚を閉める間に、は四苦八苦して一枚を閉め終えた。
「ありがとうございます、助かりました。袖が濡れたんじゃないですか?」
「少しね。でも、すぐ乾くから。いつもこんな風にしているの?」
「そうですね、ここを閉めるのは今日みたいな日と台風くらいなものです」
が煉獄家に出入りしてそれなりに経つ。だが、今日のようなことは初めてだった。自宅は窓横の板を閉めるのみ、このような重労働はしたことがない。たった一枚で疲れたとは言えず、は一つ息をつく。
すっかり帰宅の機会を逃したはお茶を飲みながら雨が止むのを待った。
「どうしたの?」
千寿郎が見ていることに気づき、は様子を窺った。「いえ」と千寿郎は顔を背ける。
「あ。もしかして」
おやつに持ち寄った串団子。あんこの乗ったそれを頬張ったばかりだ。は懐紙を出し口元を拭った。あんこは取れなかったが、薄っすらと桃色に色づく。それに気づいた瞬間、は頬が熱くなった気がした。
「姉が口紅を送ってきたから、ためしに付けてみたの。変だったよね」
「口紅?いえ、そんなことありませんよ……」
その声は浮いていた。彼の頭の中は他のことでいっぱいになっているようだ。悩み事か、とは思う。
「何かあったの……?」
「いえ、大したことでは……」
千寿郎は薄く唇を噛んだ。窺うようにを見て、軽く握った拳へ視線を戻す。そして小さな声で続けた。
「僕の母上が、どのようなお方だったか……姉上は、ご存知ですか?」
おぼろげな記憶に感じる『母』という存在を確かめようとしているのだろう。千寿郎の問う姿は、恥辱と秘めた思いを覗かせていた。
「……瑠火さんは、凛とした御方だった。会うと背筋が伸びる感じがするの」
こんな風にね!とは背筋を伸ばしてみせる。あまり格好がつかなかったのか、千寿郎はふふっと笑った。
「わたしは本当に何もできなくて、火入れや料理、色々教えてくださった。いつもは厳しいお顔つきなことが多いんだけど、千寿郎くんのことも杏寿郎さんのことも、とても優しい目で見ていらしたのを覚えてる。時々優しく微笑んでくださる時があって、わたしは好きだったな」
時の経過は無情だ。たくさんあったはずの楽しい思い出もわずかしか残らない。
優しい手、そこから伝わる温もり。声、香り、空気。
あの頃の光景をそのままに、彼に見せてあげられたらどんなにいいか。が知ることは杏寿郎よりも遥かに少ない。語るには足りなかった。千寿郎の思いに沿うには微力すぎた。
「私の記憶はそんな感じ。たくさん話せなくてごめんね」
「いえ、ありがとうございます。違う一面を知れた気がします……」
千寿郎は眉を下げ、力無く笑った。
「弱き人を助けることは、強く生まれた者の責務。母上はそうおっしゃったそうです」
「責務……」
「僕も兄上のようにと思うのですが、なかなか……」
口を閉ざした千寿郎を見て、はまたも思い違いをしていることに気づく。
「千寿郎くんはすごいよ」
「いえ、僕はそんな」
「そうだ、手を貸してみて」
「あ、はい……」
は優しく包んだ。やはり母たちのようにはいかない。それでもなんとかしたいという思いが勝った。千寿郎の手には豆の跡がある。幼い時の杏寿郎と同じだ。時に、憧れと敬意はひとりでに心を焦らせる。そのことをはよく知っていた。
「千寿郎くんはすごい。一人でも頑張ってる。本当にすごい子」
「そ、そんなことないですよ……」
「杏寿郎さんも絶対にそう言うよ。おかえりになったら聞いてみようか?」
「そ、それは勘弁してください!」
「じゃあ、これは秘密ってことね」
「えっと……はい、秘密です」
は微笑んだ。すると硬い表情のままだった千寿郎も目元を緩めた。初めての秘密にくすくすと笑い合っていると、光と同時にドンっと地を貫くような音が轟く。
「い……いまの、近かったよね?」
「そうですね……」
は手元に目をやり、ごめん、と思い切り掴んだ手を離した。きっと千寿郎がいなければ悲鳴を上げていただろう。息を止め、体をこわばらせたと違い、千寿郎はけろりとしていた。まったく動じていない。
「雷、平気なの?」
「はい。というより、さっき風が冷たかったので来るだろうなと思ってたんです」
雷が鳴る前は空気が冷える。杏寿郎から教わったのだと千寿郎は言う。
「そうなんだ、わたしなんておへそを隠すくらいしか知らないのに、さすがね!」
今度は否定しなかった。
千寿郎は眉を下げ、照れくさそうに頬を緩めた。

が席を立つと、「表まで送ります」と千寿郎も一緒になって出てきた。通りで鉢合わせた初老の男がこちらに向かって会釈し、「すごい雷でしたね」と空を見上げる。驚いたのは自分だけではなかったと知り、は少しほっとした。
落雷の後、光が差すのは早かった。雨上がりの空はからりと晴れた。その反面、路面はぬかるみ、履物の裏は糊がついたようにべっとりとする。場所によっては草履が置き去りになりそうだ。
「大丈夫ですか?」
袴への泥跳ねを気にしているのか、千寿郎がの足元を見やる。
「うん、千寿郎くんこそ大丈夫?」
「はい。僕のは普段着なので平気でっ……す」
ずるりと足を滑らせ、千寿郎は目をぱちくりとさせる。とっさに千寿郎の袖を引いたも足を持っていかれそうになった。もう少し遅ければ二人で尻もちをついたに違いない。
「は~、あぶなかったね」
「ありがとうございます、この辺りはいつもこうなんです。なので、小さい頃はよく兄上が手を引いてくださって」
「それで送ってくれたんだ、ありがとう」
路面電車に乗り込んだは空いた席に腰を下ろす。前席には同じ年頃の女の子が並んで座っていた。二人とも髪にリボンをし綺麗に結い上げている。楽しそうに話す内容は途切れながらもの耳に届く。学校の話題、好きな雑誌の話。が教室で聞くものとさほど変わらない。隣の席には親子が座っていた。千寿郎より小さな男の子が両腕いっぱいに風呂敷を抱えている。足がつくかつかないか、というところでなんとか踏ん張っている様子を父親と思われる男性が微笑ましく見ている。
は流れる景色に目を凝らした。だんだんと人通りが増え、車両は街中へ向かっていく。「もうすぐ川開きね」「太郎さんを誘ってみたら?」「もちろんそのつもりよ」—— 。
一駅手前では下車する。考え事をして帰るには丁度よかった。電車を降りると、運の悪いことに側を通った人力車の車輪がの袴に泥水を浴びせた。通りかかった婦人が気の毒そうな視線を向けたが、そのまま通り過ぎていく。
千寿郎と歩いた道は何度も通った道。が手を握ったのは母の手だった。姉でも、父でもない。けれども、それは遠方にいるからだ。
千寿郎は兄の手だった。父の手ではない。多忙だから、という理由だけではないだろう。は千寿郎が「父上」と言葉にした記憶があまりなかった。いつも杏寿郎を慕っていた。
今この時も、杏寿郎は邁進していることだろう。は在りし日の少年を思い、胸が締め付けられるようだった。
『俺は父上のようになりたい』