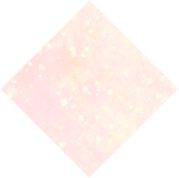第十五話
どんなに疲れていても家が近づくにつれ、不思議と足は早まった。
遠方の任務を終え、杏寿郎は生家の門をくぐる。
「雷が落ちたと聞いたが?」
それは下山を決めた時だった。杏寿郎は雑木林の隙間から遠雷を見た。一度は天から走る光の筋に目を奪われたが、先を巡らせ不安を覚えた。
「神社の松に落ちたそうです」
神社は幼い頃に杏寿郎が千寿郎を連れて出かけた場所。生い茂った欅の中にぽつんと松の木があった。秋になると松ぼっくりを拾うのが楽しみだった。そのことを思い出したのだろう、幹が折れてしまった、と千寿郎は残念そうに言った。
「きっと松の木が守ってくださったのだろう」
「そうかもしれませんね。ちょうど姉上もいらしたので、かなり驚かれて……怖がりなんですね」
意外だ、と千寿郎は口元を緩ませる。その笑みは杏寿郎に違和感を抱かせた。
昔から千寿郎は悲しいことがあるとすぐ顔に出る。そしてまた、嬉しいこともすぐ顔に出た。いつもは「兄上」とすぐに話をするが、今日はそれがない。浮足立っているというのも少し違う。ただ、いつもより朗らかだった。
「姉上にはお見せになられましたか?」
千寿郎は杏寿郎の羽織る物を見つめた。春風が裾を揺らし、炎のように舞う。
やっとここまで来た。炎柱になった。
杏寿郎はそのことをいち早く槇寿郎に知らせた。しかし、その答えは寂しいもので、それを知った千寿郎がひどく落ち込んだ。励ましの声が届くまで、杏寿郎は肩を抱いた。それでも零れた涙が乾くまでしばらくかかった。そんなこともあり、千寿郎が自ら羽織の話をするとは思いもしていなかった。
「まだだ。いつ来るか聞いているか?」
別段、隠しているつもりはない。いずれはと考えていても時期を逃すとなかなか難しい。隊服の時もそうだったな、と杏寿郎が思い返していると千寿郎が言った。
「その、……しばらく中間考査で来れないとおっしゃっていました」
中間考査。聞き慣れない単語に杏寿郎は空ける。されども、学生なら当たり前と思い至るまで、そう時間はかからなかった。
「学業は学生の本分、忙しいのは良いことだ!俺は着替えてくるとしよう!」
「湯も沸いてます」
「ありがとう!」
杏寿郎は自室へ向かい羽織を掛けると、それを眺めた。ずっと憧れていた、代々続く炎柱の羽織。
『どうでもいい』
消えない声が蘇る。それでも為すべきことを為す。それは不動だ。
—— 彼女は、は何というだろう。
どさっと畳を叩く音で、杏寿郎は我に返る。
脱いだばかりの隊服が腕から滑り落ちていた。
「おっと、……」
上着を抱えると、今度は巾着が飛び出した。鮮やかだった朱色はくすみ、生地の角は擦り切れていた。先日のような山林で落としていたら気づけなかっただろう。杏寿郎は畳の上から拾い上げ、上着の胸ポケットの奥深くへと蔵めた。

「いい湯だった!」
杏寿郎が湯から上がると、居間で千寿郎が縫い物をしていた。
「よかったです。お茶を淹れますね」
何を縫っているのかと見てみると、自分の着物を直していた。袖の部分から縫いかけの糸が伸びている。何かにひっかけたというよりも傷んでいるようだ。原因は家事で使うたすき紐だろう。が縫い物を教えていたのは知っているが、器用なものだと杏寿郎は思う。
「お待たせしました……どうしました?」
「縫い物までできるようになったのかと感心していた!」
「できてないです、こんなの全然……」
見せられたものではない、と千寿郎は慌てて着物を部屋の角へ追いやった。
「自分の着物なら練習になると思ったのですが、難しいですね。あっ、そうだ」
一度部屋を出た千寿郎は隊服のシャツを抱えて戻ってきた。
「この前、洗っていて気づいたんですけど……こっちのほうが新しいですよね?」
千寿郎は二枚のシャツを広げる。以前のシャツは戦闘で痛んでしまった。代わりとして、新品が支給されたばかりだった。
「こっちはもう釦が取れそうになっていて、お気づきでしたか?」
「いや、一方はが縫ったものか」
「そうです。こっちの生地が古いはずなのに」
千寿郎は変だなと首をかしげる。
杏寿郎はシャツへ視線を落とし、先日のことを思い浮かべた。稽古を終え、汗を流そうと脱衣所へ向かった。しかし置いたと思ったシャツがなく慌てて探した。『みっともないです、姉上がいらっしゃるのに!』—— みっともない。だからこそ、杏寿郎は急いだのだ。しかしそれが仇となり、の様子は下手な操り人形のようにぎこちないものとなった。言うなれば、そのシャツは杏寿郎にとって戒めのシャツである。
「兄上はなにか心当たりはないですか?」
「そうだな、……」
と、考えはするものの、さすがに隊服の中まで気にしていない。はっきりとした理由は思い当たらず、杏寿郎は二枚のシャツを見比べた。ある程度は推測できても詳しいことは判らない。幼い頃は母、瑠火が縫い物をしていたこともあって尚更だ。その後も藤の者や晴子、そしてと続き、杏寿郎が針を触る機会は皆無だ。父はと思ったが、槇寿郎こそ最たるものだろう。
「うむ!心当たりはない!」
「兄上がわからないのなら僕がわかるはずがないな」
「縫い物は千寿郎の方が詳しいだろう?」
「いえ、詳しいというのなら姉上が……」
千寿郎は頬を綻ばせる。そして杏寿郎を一瞥すると、視線を下げた。
「あの、兄上……」
「ん?」
「兄弟というのは、皆似るものでしょうか?」
兄弟と言えば、の姉が来たと千寿郎は驚いた顔をして話したことがあった。その数日後、槇寿郎と杏寿郎に宛てて手紙が届いた。槇寿郎は「捨ててしまえ」と開けようともしなかったが、自分宛でもあるのだから見ても構わないと杏寿郎は判断した。内容はこちらへの労いや妹が世話になっていることの礼、前触れもなく来たことの詫びだった。それから千寿郎のことを称揚した内容が書かれていた。
「の姉君はどうだった」
「姉上様は、晴子さんに似ていらっしゃいました」
「は晴子さんと似ていると思うか?」
二人の顔を思い浮かべているのだろう、千寿郎はじっと考え込む。
「う〜ん……よくわかりません。父上様に似ていらっしゃるのでしょうか?」
「似ると言っても、外見だけではないからな」
千寿郎は杏寿郎の顔を見て、もじもじと指先を絡ませながら「そうですね」と呟いた。
なるほど、と杏寿郎は喉で笑う。
「なるほど?」
「千寿郎がご機嫌な理由だ」
「ごっ、あの……」
黙っていられないな、と千寿郎は恥ずかしそうにため息をつく。
「うむ、それは難しいだろう!俺は正直に話してしまう方だ!」
おそらくもこの顔を見たに違いない。幼さを残し目尻を下げる弟を杏寿郎は微笑ましく思った。
程よく冷めたお茶で喉を潤す。
気づかないうちに、得体の知れないものが喉に張り付いていた。その正体がとんでもなくくだらないものだったと気づき、杏寿郎は失笑する。なんと愛らしい秘事か。
千寿郎は二杯目のお茶を注ぎ、菓子器を並べた。余計な話かもしれませんが、と前置いた千寿郎は、ゆっくりと座り直し膝の上で拳を作った。
「姉上のお香は、鬼避けですよね?」
「ああ、そうだ。それがどうした?」
「……姉上は今、お持ちでありません。姪御さんにあげたとおっしゃられて、赤子が泣き止まないからと……その、ちょっと気になったもので」
気遣うような視線が杏寿郎へ向く。
「そうか、知らせてくれてありがとう。今は幾分日も長い、心配するほどでもない。それより泣き止まないという方が気になる」
「そうですか?」
「時に赤子のほうが敏感だ」
赤子はわけが分からず泣いているわけではない。物を話せない代わりに泣いて色々なことを伝えてくる。もちろん、はじめて杏寿郎にそれを教えたのは弟、千寿郎だ。そうとも知らず千寿郎は「へえ」と感嘆の声を上げた。
「でも、無事帰られたそうですし、良かったです」
「神戸はなかなかの長旅だな!」
「地図ではあんなに離れているのに、一日もかからず着くなんて不思議ですね」
昔、杏寿郎が見た広い更地には噂通り東京駅ができた。今や当たり前となった駅は、様々な理由で多くの人がやってくる。しかし、どんなに時代が変わろうとも変わらないのが鬼だ。古から脅かす存在、それが妖の証でもある。
「夕餉の準備をしてきます」
千寿郎は席を立つ。
杏寿郎が一緒に立ち上がろうとすると、千寿郎が慌てて肩を押した。
「お疲れでしょう、兄上は座っていてください」
「二人で作ったほうが早い」
「下ごしらえは済んでいるので大丈夫です、本当に」
「む!では千寿郎様に甘えるとするか!」
「ははっ、ぜひそうしてください」
着物の袖を肩に寄せ、千寿郎は意気込んで部屋を出ていく。言われるがままに座って待っていた杏寿郎は思い立って自室へ向かった。
—— たしか、ここに。
杏寿郎は書棚の奥に仕舞い込んだ桜の風呂敷を取り出した。幾重にも折りたたみ挟んでおいたそれは懐かしい香りがする。かつて瑠火が袖に忍ばせていた匂い袋だ。
幼いながら、大切なものだと思っていた。肌身離さず持っているべきだと思った。
葬式の前日。いつの間にか母の着物は衣紋掛けに下がっていた。杏寿郎は袖からそれを抜き取った。—— 母上、お忘れです。大事なものです。
だが、知らぬ間に白い着物へ着替えの済んだ母にこっそりと忍ばせることは至難の業だった。袖を取ろうとするが、手が言うことをきかない。受け入れがたい思いが袖に触れることを拒んでいた。考えあぐねた杏寿郎は槇寿郎に問う。すると、あの世に鬼はいないと返ってきた。
極楽への道は真っ当に生きた者のみに与えられるのだと。

「千寿郎、ちょっといいか」
夕餉を終え、杏寿郎は片付けをする千寿郎を呼び止めた。座敷で向かい合うように着座すると、風呂敷を広げた。ふわりと漂う香りが鼻腔を掠める。
「母上がお持ちだったものだ」
千寿郎も知るはずの香りは今では遠いものになってしまったらしく、「母上が……」と驚いた顔をした。
「さっきの話でずっと仕舞い込んでいたのを思い出した。千寿郎に譲ろう」
唯一の形見とも言えるそれに何を思うのだろう。
杏寿郎の中で、知りたいと思う気持ちとそうでない気持ちが入り混じる。千寿郎は戸惑いながらも壊れ物を扱うように両手でそれを受け取った。
「……ありがとうございます。ですが、これは姉上に渡してください」
僕はもう満足です。そう言って、千寿郎はそのまま杏寿郎の元へ差し出した。
「本当にいいのか?」
「はい。その方が母上もご安心なさると思います」
本心で述べる弟にそれ以上言うことはなく、杏寿郎はそれを受け取った。なぜか、してやられた心地がした。しばし考え、杏寿郎は顔を覆いたい衝動に駆られた。
—— 俺は、……。
そうさせているのは、己の本音。
「それはそうと、手に豆ができなくなったな!」
「あ、言われてみれば……」
「右に豆ができないのは上達している証拠だ!一人でよく頑張っているな、偉いぞ!」
頭を撫でようとした杏寿郎は手を下ろし、両腕を広げた。千寿郎は呆けたように見た。はっとした顔をし、やがて満面の笑みに変わった。思い切り杏寿郎の胸元に飛び込んできたのはそれからだった。束からはみ出し短く跳ねた髪先が、杏寿郎の顎や頬をつつく。嬉しさにくすぐられているようだ。その感情は次第にくすくす笑いへ変わり千寿郎にも伝染する。
ふたりで肩を揺らし、弾けるような柔らかい声が響いた。
胸から顔を上げ、千寿郎はあどけなさの残る顔で言う。
「兄上、今年は川開きに行きませんか?もちろん、任務がなければの話です」
両国の川開き。両国橋のたもとで行われる祭りだ。川岸にずらりと船が並び、隅田川を沿う店の前には見物用の桟敷が組まれ、夜店や露店を楽しむ。数日行われるそれは、初日が最も賑わう。
「花火か」
もう何年も行っていなかった。幼い千寿郎を連れての夜の街は不安を覚え、人の多い場所は避けてきた。花火が上がる日は、千寿郎を膝に抱え縁側で半円の花火を眺めた。
「そうだな、考えておこう」
今なら、今だからこそ。杏寿郎は思いを巡らせた。