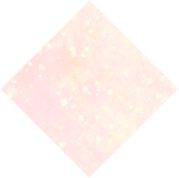第十六話
昼下がりの午後、家の客間は紅茶と甘い焼き菓子の匂いが漂っていた。
椅子に座ったは澄ました顔をする。その隣で晴子は愛想笑いをするでもなく、と同じく澄ました顔をしていた。困惑しているのは目の前の教師のみ。
中間考査を終え、面談の時期がやってきた。いわゆる、家庭訪問である。
「お母様、さんは許婚がいらっしゃるということですが……?」
「はい、そうです」
担任は持ってきた書類を何度も見比べる。何かがおかしい、そう言いたげに。
「それで、学業はご継続なさるということですね?」
「はい」
「さんもそれでよろしいですか?」
「はい、先生」
「あの……そうですか、わかりました」
成績について苦言を申す、というのならも納得しただろう。しかし、担任は何を思ったのかしきりに“学業を継続するか否か”訊いてくる。終いには、
「私はお相手がいらっしゃらなくとも恥ずかしく思いません。お教室にもいらっしゃいますし、何より卒業は良いことです。立派なことです。実に素晴らしいことです」
これにはも返答に困った。思わずが担任の顔を見ると、わずかに視線を逸らされた。目の前に提示されたあらぬ疑惑にも、晴子は顔色一つ変えない。自分の湯呑みに口をつける余裕すらある。その自信の源を、は理解できなかった。
「ええと、お母様から何か質問はございますか?」
「いいえ、特にございません」
事前に用意するよう申し伝えられた、印鑑と筆の用意が不要と知ったのは、担任が書類をしまってからだ。鞄の隙間から見えたのは、退学届の文字。
「何度も言いますが、本当に成績は申し分ありません。免許状も大丈夫でしょう。……このまま学業に励んでください。では、本日はこれにて失礼いたします」
は時計をちらりと見やった。担任がこの部屋に来て5分ほどしか経っていない。紅茶がよい温度になった頃、教師は家を後にした。

杏寿郎さん、わたしは—— 。
杏寿郎さんはわたしの—— 。
わたしは杏寿郎さんの、……。
は頭の中で議論を繰り広げる。なかなかしっくりくる文言が思いつかない。ただ、自分が許嫁であるか否かを確認したい、それだけだった。しかし、どうしても回りくどくなってしまう。さりげなく聞くにはどうしたらよいか。そもそも、さりげなく、というのが間違いなのか。
『姉さまは鬼狩りをご存知ですか?』
がこの一文を記すのに何枚の便箋を無駄にしたことか。は姉からの返答をあれほど待ち遠しいと思ったことはなかった。日になんども郵便受けを見に行き、配達員が呼び鈴を鳴らすのを待っていた。そしてついに返答が来た日、封を開けたは嘆息した。『—— そのことは知っていますよ。』何度も紙をめくろうとしたが、二枚目が現れることはなかった。文面では直に会って話すようにはいかない。どのように知っているか知りたい、なのに……。
訊き方がわるかった。いや、知らないのではなく、忘れているのかもしれない。何しろ十年近く前の話。弟がいるというのも聞き逃していたのだから、そうあってもおかしくない。けれども、全く印象に残らないのも妙だ。その話をしている間、よほど呆けていたとしか考えられない。しかし今更。今更すぎては晴子に言えなかった。
「お悩みですか?」
「あ、いえ……」
しかも、今はそれについて考えに来たわけではない。
『髪花』にて、髪紐を選んでいる最中だった。家庭訪問が早く終わり、久しぶりに街中へ繰り出していた。よって、いつも助言を述べる友人も居ない。一人きりの買い物だ。
手にとったまま考え込んでいたに、店員は言う。
「今お持ちの髪紐は紅花で染めたものです。左のこちらは茜。絹のように透き通る色もよし。綿糸の色むらも味があってよろしいかと思います。どちらもよくお似合いです」
「いえ、これは……」
二つを見比べ、は時間も忘れ吟味する。散々迷った末に一方を棚に戻した。
「すみません、これをお願いします」
包み上がるのを待つ間、は通りを見た。
立派に働いていたらもっと良いものが買えたかもしれない。だが、一学生であるには小遣いを貯めて買うのが精一杯。友人は母に言うだけでポンと財布が暖かくなると言うが、小遣いといっても晴子は簡単にくれはしない。帰宅した父のシャツにアイロンをかけ、母の着物の綻びを直してこつこつ貯める。先月、父が一週間ほど帰宅した。その際にヘソクリと言って3円小遣いをくれたが、なぜか晴子に見つかった。与えすぎ、貰いすぎ。親子揃って説教を受けた。
五月の初旬。杏寿郎の誕生日が間近に迫っていた。西洋には誕生日を祝う習慣があると知り、ずっとは考えていた。
「お待たせしました」
「ありがとうございます」
店を出たはどうしたものかと思う。手にした薔薇柄の包み。髪紐は使ってもらえそうだと思って選んだが、
—— 浴衣を縫って差し上げた方がよかったかも……。
今頃になってそんなことを考えても仕方がない。生地を買う余裕も時間も足りない。
自宅へ向かいながら、は通りの人々を横目で見た。こんな風に探すようになったのはいつからだろうか。学校やお使いの行き帰り。もしかしたら、と考える。
は杏寿郎が街にいるところを見たことがなかった。任務というのも東京でも広範囲、山奥となれば全くの別方向。つい、目を奪われる黒い詰襟は、名前も知らない大人びた学生だ。以前、書店で本を見ていると目が合ってとても妙なことになった。こちらに近寄ろうとしたのに気づき、は慌てて逃げだした。それ以来じっくりと見るのはよしておこうと決めたはずが、盗み見る悪い癖は抜けなかった。こんなことが晴子に知れたら何を言われるかわからない。
「あっ」
トンと後ろから肩がぶつかり合った。一瞬前のめりになり、は足元からよろける。
「す、すみません!大丈夫ですか?」
「いえ、こちらこそ……」
はもう一度その者を見た。の視線は男の腰元を捉える。
「か、刀……」
腰に刀を持っている。そして、彼の背には『滅』の文字が。急に手の指がじんと冷えた。彼らは杏寿郎と同じだ。
「いやっ、これは違うんですよ、ハハッ」
「バカ、だから言っただろ!早く行くぞ!」
いくら近かろうと意味がない。と、黒髪の青年が二人、こそこそと隠れるように立ち去る。
「あ、ま、待って……!」
思わず駆け出しそうになったを路面電車が阻んだ。道路を渡り、は彼らを探した。
見間違いだったかもしれない、何度もそう思った。砂にまみれたそれは小さな泥となって踏み潰されていく。誰も気づいていない。誰も気にしていない。しかし汗でも水でもないそれは、黒くなってに現実を語る。血だ。あの二人のどちらかは怪我をしている。はしばらく探し回ったが、地面に落ちたそれはあるところで断たれ、どこにも続いていなかった。まるでその場で忽然と姿を消したように無くなっていた。
刹那、嫌な緊張がを襲い、ぞくりと背筋が寒くなった。
『明日死んで後悔したらどうするの?』
姉は妙なことを言ったものだ。悪い想像はあっという間に浸食する。自宅へ向かっていたの足は、真逆を目指す。いつもの路面電車、乗車代は二駅分しか残っていない。帰らなければ日が暮れる。でも、もし何かあったら。それがしきりにを急きたてた。
黄昏時を待つばかりとなった停留所は、たくさんの人が溢れていた。帰宅がほとんどらしく、両手に荷物を抱えている者も多くいる。待ちに待ってやってきた電車に、は素早く乗り込んだ。すし詰めになりながら座席の間に立っていた。
—— 少し、お顔を見るだけ。少しだけ。
電車を降り、はさらに早足になった。いつもより手前で降りたこともあって、なかなかたどり着けない。近道はどの道か。慣れた景色も曖昧に見える。考えている間にはいつも降りる停留所に着いていた。伸びる影を気に留めることなく歩く。
頭の中では帰らなければならないとわかっていた。わかっていたはずだ。
そうしてやってきたは、門を見るなり思い出したように息をついた。そして閉まったそれに向け、声を張る。
「御免下さいませ」
遠くの方で門を閉める音がした。来客としては遅い時間。門を開け放った家はもう一軒もない。夕食の準備をしているのか、もしくは出かけているか。それとも、本当に何か。いつものように千寿郎が出てくる様子はない。
「ごっ、御免下さいませ……!」
狭まった声は奥まで届いているかわからない。それでもは門から動かなかった。
ほどなくして草履の音がした。ガラガラと戸が開き、
「お前……うちに何の用だ!」
思わずは身を竦めた。酒瓶を持った槇寿郎がいきなり怒鳴りつけたのだ。その体は酒気を帯びており、の頭上を見ている。かなり酔っているようだ。鷹が獲物を狙うようなギラリとした眼がを捉えた。そして、次第に虚ろなものへ変わる。槇寿郎は素面を装う声で、
「……なにかあったのか?」
と、じっとりとした視線をよこした。
「いっ、いいえ……」
の目が泳ぐのはどうしようもなかった。しどろもどろになりながら、なんとか言葉にするのがやっとだ。
「おっ、遅くにすみません……き、杏寿郎さんは、いらっしゃいますか?」
ぎこちない言葉は槇寿郎の眉間にシワを作る。針のようにちくちくとしたものがを刺した。その姿は想像していたよりもずっと違っていた。の知る温かな空気はすっかり消え失せ、今や見る影もない。鬱陶しいものを見る視線に耐えかね、は下を向いていることしかできなかった。
「……千寿郎と醤油を買いに行った」
「そ……そうですか、お醤油を。……また後日伺います」
どっと疲れた気がした。自分に嫌気が差した。
は一礼し、門に背を向ける。すると、大きな手がその肩を掴んだ。予想もしていなかったは露骨に肩を揺らす。
「……どうせ直ぐ戻る」
槇寿郎は西の空を睨んだ。
暮色の中、白みがかった帯が影絵のごとく山脈を映し出し、昼と夜の境を見せつけていた。
拒むこともできず、結局は言われるがままに屋敷へ入った。無言で部屋に通され、一人待ちぼうけた。槇寿郎はよろめきながら自室へ消えたきり出てこない。
心臓が落ち着かない。酒に酔った槇寿郎を目の当たりにしたこと。あるいは、初めて門限を破ろうとしていることもあるかもしれない。
は自分の手のひらを見つめ、俯いた。そうしていると、少しずつ焦っていた気持ちが冷めていった。見境をなくしたのは初めてだった。
静寂の中、冷えた頭で思うのは、やはり晴子からは聞かされていないということだ。なぜ、晴子がはっきりと言わなかったのか。きっとこうなるだろうと踏んでいたに違いない。幼い時に知ればどんな行動をとるか分かりきっている。が杏寿郎を困らせる自分を想像するのは容易かった。
鬼狩りなんて辞めて。
そう言って、考えなしに泣いて縋っただろう。
は悔いていた。街で彼らを見て、一瞬頭が真っ白になった。もし、杏寿郎の身に何かあったら—— 。思考の端にあった『何か』がくっきりと浮かび上がる。
杏寿郎が帰宅したら、きっと驚くことだろう。
こんな風に家に行くことはあってはならなかった。
母のようにもなれず、姉のようにもなれない。その理由がこの過ちに表れていた。