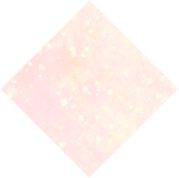第十七話
「これで煮物が食べられる!」
「間に合ってよかったです」
灯ともし頃、杏寿郎は弟と並び歩いていた。
醤油屋は大通りへ出て程なくした場所にあった。店は閉店間際、滑り込みで買った瓶は二本。それを杏寿郎は楽々と抱えている。ついでに味噌も、と千寿郎の腕には小ぶりの樽が乗っていた。どの家も食事の準備をしているらしく、どこからともなく香ばしい匂いが漂ってくる。
急いで料理に取り掛かろう、そう言って千寿郎は門をくぐる。しかし、駆けていくだろうその足は玄関を前にしてぴたりと止まった。
「草履が、……」
姉上の草履がある。その言葉に杏寿郎は三和土を覗いた。そこには確かにの物と思われる女物の草履が揃っていた。
「何かあったんでしょうか?」
千寿郎の疑問は杏寿郎にも響いた。は勝手に家へ上がり込むような者ではない。槇寿郎が上げたとしか考えられず、心の内で杏寿郎は弟の言葉を反芻する。
「たまたま寄っただけかもしれない。ただいま戻りました!」
静まり返った屋内に、その声はよく響いた。杏寿郎に続き、佇立していた千寿郎も草履を脱ぐ。
「兄上、醤油はそこに置いておいてください」
後で取りに来ますから、と千寿郎は炊事場へ向かう。ああ、と生返事をした杏寿郎は真っ先に居間へ向かった。
「はて……」
どうりで明かりがないはずだ。襖の先にの姿はなかった。
杏寿郎は父が何を考えているのか度々想像したが、今回ばかりは不思議でならなかった。まさかという思いから、その場所は考えていなかった。もう誰も通さないだろうと思っていたのだ。開かずの間となってしばらく経つ。
「失礼する。遅くなってすまない!」
杏寿郎が障子を開けると、薄暗い部屋では正座をして待っていた。
「おかえりなさい。……遅くにお邪魔して、すみません」
と、杏寿郎をひと目見るなり、日陰の花のように沈みこんだ。
「お顔を見たら帰ろうと、最近お逢いしてなかったから……」
「そうか、てっきり大ごとでも起きたかと思った!」
「あ……いえ」
「暗いな!明かりを点けよう!」
行灯に火を入れると、温かな色が辺りを照らした。杏寿郎はの前に対座し、考えた。いつもならすぐに顔を上げるが、今日はこちらを見ようとしない。畳へ視線を落とし、思いつめたように口元を引き締めていた。
「……杏寿郎さんに、いくつか話したいことがあります」
彼女の声は静かだった。一聴すれば冷ややかとも取れ、杏寿郎は握った拳に意識を寄せた。
「話か!承知した」
「……もし、違っていたら訂正してください。わたし、杏寿郎さんの言う鬼狩りについて、随分調べたんだけど……」
晴子に鬼狩りという言葉を聞いて以来、ずっと答えを探していた。そう言って、は紡ぐようにぽつりぽつりと話した。
「どんな本を見ても、どこにも載ってなかった。これだと思った本も、塗りつぶされていて読めなくて。初めは斬首刑を想像して、でも、それとは違う……。鬼は、頸を斬らなければ居なくならない。滅ぶまで何度でも向かってくる。杏寿郎さんはあの刀で……でもこちらは、人……」
杏寿郎はが泣いているのではないかと思った。その声は震えていて、それでも懸命に言葉にしようとしていた。
「少しずつ、そうじゃないかと思ってた。でも、絶対的なことは言えなくて……怖くて聞けなかった。とても大事なことなのに」
は小さく息を呑む。
「今日、怪我をした人を見たの。杏寿郎さんと同じ服を着ていて、随分探したんだけど途中で見失って。それで、……」
ごめんなさい、とは罰の悪そうな顔をした。
「おそらく隠が連れて帰ったのだろう」
「かくし?」
「鬼殺隊を補助する隊員のことだ。鬼殺隊は正式に認められた存在ではないので、あまり目立つ事はできない」
もし重大事案があれば一報があるだろうがそれもない。平隊士、おそらく下位。怪我は胴ではなく手を切った。止血が緩く、傷口が開いた。それを彼女は見た—— 杏寿郎は考えを巡らせる。
「その者が歩けていたのならまず心配はない。今頃その隊士は治療を受けて寝ている」
「……わたし……とんだ早とちりね」
今日は家庭訪問だったの、とは付け足した。
静かな声は彼女の猛省の末だった。浅はか。他の者が訊けばそう言うだろう。
「心配ありがとう。ただ、が思うような事態は早々に起きない。しょっちゅう怪我をしていたら大問題だ!」
彼女の眼は今にも涙が溢れそうになっている。ぽつりと落ちないように必死で堪えていた。
今、こんな事を言うのは酷ではないか。
そのように考えないこともない。しかし、いつかは言わなければならないこと。むしろ、話すには遅すぎるくらいだった。
「君が想像するように、鬼狩りをするからには命を落とす事があるかもしれない。だが、天命だと俺は思う。だから君は、」
そこで杏寿郎は口を閉ざした。前を向いたがひとつ瞬くと、小さな珠がはらりと落ちた。は慌てて顔を背ける。
泣きはらした顔は知っているが、泣いた顔は見たことがない。真珠のように落ちた涙を、忘れるのは難しい。泣かせてしまったと罪悪感を覚える反面、杏寿郎は己の感情に疑念を抱いた。不覚にも、が流した涙を美しいと思ったのだ。
一方で、は作ったようにツンとした顔をした。伏し目がちになった彼女が「失敗した」そう思っているのは明らかだった。
「失敗は悪いことではない。気づきのないことのほうが恐ろしいことだ!そして今回のことは失敗とは言わない!」
杏寿郎は安心させるように微笑むと、ややあって、も弱ったように眉を寄せ、笑みを見せた。
「杏寿郎さん、ありがとう……。わたしが怖がりだから、ずっと黙ってくれてたんだよね。今までわたしに合わせてくれて、ありがとう」
突如、の眼に写り込んだそれに、杏寿郎は一点を突かれた。
—— そうか、そういうことか。
死を想像し、涙を見せた時とは別の物が瞳に宿る。瞬く間に消えてしまう光の正体。一つ一つのの想いが、杏寿郎の心を引き付けていた。そこには彼女なりの覚悟があった。

「送っていこう」
杏寿郎が外へ出ると、濃紺の景色が広がっていた。千寿郎が玄関まで見送りに出て、はそれに手を振った。帝都の夜は長い。街の方はぼんやりと点り、遠くの方から夜通し走り続ける路面電車の音がした。
家を出る直前、杏寿郎の手のひらを見たは驚いた顔をした。千寿郎が話したと悟ったのか、
「せっかくいただいたのに……勝手なことばかりしてごめんなさい」
「が気に病むことではない、気にするな!これは母上のもので間に合せになってしまうが、まだ香りは残っている」
「瑠火さんの、大切な形見でしょ?」
受け取れないとは手にすることを拒む。
「君が持っていたほうが母上も安心なさる。千寿郎も君に持っていてほしいそうだ。藤の匂いは鬼が嫌う」
「……ひょっとして、あのお香も特別なの?あ、実は似たようなものを探したんだけど、どこにもなかったから」
「あれも藤襲山の麓で採れたものだ。易々と街に出回るようなものではないな!」
聞いたこともないと思っているのだろう。藤襲山、とは繰り返した。
「前は言い損ねたが、これはできるだけ身に付けていてほしい」
「……わかりました。ありがとうございます」
瑠火さん、お借りしますね。とはそっと袖にしまった。
近道となる裏通りはほとんど人がいなかった。時折心地よい風が若草と夜の匂いを運ぶ。静寂に浮かぶ月は細く弓を描いていた。
四方に気を配りながら歩みを進めていると、チラチラと様子を窺うに気づき、杏寿郎は足を止めた。
「杏寿郎さん、その羽織物は……」
「柱の羽織だ。ふた月ほど前に炎柱になった!俺も君も忙しくしていたから、……」
気を取り直すべく、杏寿郎は一つ咳払いをする。
「本当は早く見せたいと思っていた」
むず痒い心地を抑え、杏寿郎はの方を向き直る。はぼんやりとした顔で見ていた。やがてその面持ちはゆっくりと華やいでいく。萎んだ花がみるみる息を吹き返す。
は向き合ったまま一歩踏み出した。
「炎柱……昔からの夢だったよね」
「憶えていたのか」
「忘れないよ、だって、あんなにずっと……」
付かず離れず、戸惑いながら手を差し伸べたに、杏寿郎も自然と答えていた。握りしめるのは、傷一つない剣とは無縁の小ぶりな手だ。「杏寿郎さん」と不意に見上げられ、杏寿郎は息を呑む。
「本当に、おめでとうございます」
柔らかく穏やか、且つ芯のある声が杏寿郎の胸元に響く。それからはゆっくりと距離を取り、じっくりと羽織を見入った。
「初めて隊服を見た時もそうだったけど、……本当によくお似合いです」
「あ、……」
話下手になったのか。たった一言の「ありがとう」に手間取る杏寿郎をよそに、の視線は羽織から刀へ移る。
「鞘も違うね、前は黒だった」
「刀も新しくなった」
「あと、釦も」
「本当によく見ているな」
「あっ、その、しょっちゅう見てるわけでは……」
金色は目立つでしょ?とはドキマギとする。杏寿郎がくくっと笑うとも笑みを漏らした。その視線は再び刀へ向く。
「見てみるか?」
「いいの?」
「前も言っただろう、刀は刃が肝だ。今は少々見えにくいかもしれないが」
幸い、路地は二人以外誰も居なかった。杏寿郎は迷うことなく刀を抜く。白抜きの『悪鬼滅殺』の文字が、真っ先に飛び込んで来ただろう。それでも、は動じることはなかった。あの時と同じく、切っ先まで視線を這わせる。
昼とは違い、一瞬冷たく光る。これが本来の、技を出す前の日輪刀の姿だった。
「羽織と似てるね。綺麗な色……やっぱり、日輪刀は神器なのかな?」
「神器?」
「あまりにも美しいから、初めて見たときそう思ったの。わたしは何もしてないから、触るのは良くないと思って……」
「君は、……」
杏寿郎はははっと軽快に笑った。どれだけ想像を働かせても、彼女の思惑にはたどりつけそうにもなかった。その奇想はどこから湧くのかと、杏寿郎は思う。
「やはり君は面白いな!」
「え?」
「俺は日輪刀をそのように言う者を他に知らない。刀鍛冶にも伝えておこう!」
「やっ、やめて!笑われるよ、杏寿郎さんが恥ずかしい目に遭う……」
「笑うものか!君がそう思っているのなら問題ない。待ってみるといい」
「あ、うん」
杏寿郎が納刀し差し出すとは恐る恐る手に取る。「重いね……ありがとう」とすぐに杏寿郎の元へ戻ってきた。そして、彼女の口元は穏やかに弧を描く。
「実はね……すぐに帰ろうとしたら、槇寿郎さんが引き止めてくださったの」
「そうだったのか」
「だから……わたしも信じてる。杏寿郎さんのことも。……そうだ、炎柱のお祝い!今度は杏寿郎さんが主役だから、好きなものたくさん作るね!」
ビーフシチューだって作れるよ、とは自信満々に言う。ころころと変わる様に、杏寿郎は瞠目するしかなかった。
「……ビーフシチューとやらも気になるが、祝いというなら牛鍋か!」
「そうね、牛鍋!あの時もお祝いを、」
そこで言葉を切り、は表情を強張らせた。その顔は竹刀を踏みつけた時そのままだ。
「わたし、お母さまに黙って来たんだった……」
「うむ!それは困ったな!一大事だ!」
探しているかもしれないとは青い顔をする。しかし、さすがにを連れて全力で走って行くわけにもいかない。杏寿郎はくるりと視線を巡らせた。
「そこに居るんだろう?」
杏寿郎の呼びかけで、一羽の鴉がやってくる。低空飛行で近寄り杏寿郎の肩に止まった。見ていたはきょとんとする。
「名は要。俺の相棒、大切な仲間だ」
杏寿郎はあやすように指先でくちばしを撫でた。すると返事をするように、つぶらな眼が一つ瞬く。「はじめまして」と言うに、また一つ瞬いた。
「すまないが、少し頼まれてくれないだろうか?晴子さん、わかるな?」
要は一声上げ、颯爽と夜空に羽ばたいていく。
「何をしたの?」
「言付けを頼んだ」
「たしかに、鴉は賢いと訊くけど……」
は要が飛び去った方を眺めた。その顔は摩訶不思議と述べている。
「これからは門限の都合を付けてもらえるよう、俺が掛け合ってみよう」
「でも、夜は」
「ここに鬼狩りが居るのに、君はそんな心配をするのか!」
「……そっか、そうだね」
炎柱になったら—— 。
その思いの一つは潰えたように思った。しかし、まだ輝きは失ってはいない。より熱く、燃えるように輝いていた。
「それにしても、ちょっと不思議な感じ」
夜道を歩くこと。何よりは杏寿郎と外を歩くことがとても新鮮だった。もちろんそれは杏寿郎にも言えることで、不思議という言葉がしっくりときた。
杏寿郎には当たり前の夜景も、彼女には珍しげに映るらしく「綺麗だね」と空を眺める。
「」
「はい」
「その晩に何もなければ、花火を見に行かないか?」
は黙ったまま杏寿郎を見上げる。
なしのつぶてのごとく全く手応えのない様子に、杏寿郎は一瞬考えた。市中に住む彼女が両国橋の花火を知らないはずはない。
「花火は嫌いだったか!ではこの話は、」
「い、いえ!すき、好きです……!」
弾んだ声に、杏寿郎は無自覚に頬を緩ませる。遠くの街灯が彼女の整った輪郭をぼんやりと映し出す。
—— 。
守ることと等しく浮かんだ心情は、杏寿郎に新たな誓いを立てさせた。