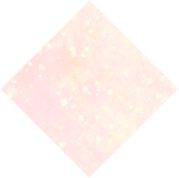第十八話
帰宅したは母の怒号を想像していた。しかし、門の前でじっと待っていた母、晴子はの姿を捉えると、駆け寄り胸に抱き寄せた。いつものような小言もない。事情を話し終えると晴子はに向け一瞬眉を寄せたが、それでも言葉にすることはなかった。また、杏寿郎の真正直な言葉も晴子に反論の隙を与えなかった。
「炎柱になりました!故に門限についてご相談がございます!さんと花火を見たいと思っております!」

祭りの日。
新聞の予報通り、朝から快晴。着物は新しい夏物を用意した。生地や帯は事前に自身が選んだものだ。手鏡を見つめ、薄く紅を引く。そして改めて姿見と向かい合った。
—— たぶん、大丈夫……。
なんとか納得させただったが、今度は髪飾りに迷った。机に並べた姉のお下がりを眺めても、時間だけが過ぎていく。
「少し早すぎやしないかしら?」
廊下から晴子の声がする。
「寄るところがあるので大丈夫です」
「そうね、道も混んでるかもしれないわね。ならば、早くしないと乗り遅れてしまいますよ……?」
「は、はい」
は慌てて部屋を出た。忘れ物はないかと手提げの中を何度も見る。いつもと同じように煉獄家へ行く。それに今日は花火見物が加わっただけだが、どうにも落ち着かない。本当にこれでいいのか、たまらずは意見を求めた。
「お母さま、おかしくはないですか?」
「少し曲がってるような気がするわ」
玄関先まで付いてきた晴子はしきりに襟を気にした。軽く首側の生地を引き、やっと満足したのか「いってらっしゃい」と背を押した。
街は紅白の提灯が飾り付けられ、商店のガラス窓や掲示板には『祭りの知らせ』が貼られていた。非日常となった情景が、東京に本格的な夏が来たことを教える。
「花火だね」
商品を包み、店主が独り言のように言った。品物は芋羊羹。晴子から立ち寄るよう、言われていたのだ。
「早いもんだ」
店主はしみじみと言う。この店主にも長いこと世話になっている。頭の手ぬぐいから覗く髪の毛がだんだんと白くなっている事を除いて、ずっと同じだ。
「風呂敷はあるかい?」
「はい」
店主は手早く台の上に広げる。芋羊羹を包んだ経木をのせ、その上に別の包み紙がのった。
「お待たせ、代金はもう受け取ってるよ」
「でも、あんこ玉は、」
「こっちはおまけ。冷やしておいたからいくらか保つが、今日は暑いから早めに召し上がれ」
「すみません、いつもありがとうございます」
「こちらこそ、ご贔屓にありがとう」
この時期は商売上がったりなものでね、と店主は目尻にシワを寄せた。
真昼は過ぎていたが、日差しは厳しく街路樹から蝉の声が賑わっている。通りすぎる人々は扇子や団扇を顔にかざした。爛々と輝く太陽。どこまでも続いているような真っ青な空に、綿雲がぷかぷかと浮かんでいる。蒸すような暑さは身に堪えるが、は嫌いではなかった。特に今日のようなカラッとした日は好ましい。

いつもの停留所、いつもの角。そこで見えてきた人影に、は立ち止まった。以前見かけた初老の男だ。「こんにちは」との声に男も一礼する。
「こちらの御宅に御用ですか?」
「はい。約束をしております」
そのまま煉獄家の門を潜ろうとしたを男の足が拒ませる。あの、とが口を開く間際、門から千寿郎が顔を出した。
「姉上」
がほっと胸をなでおろしたのもつかの間、千寿郎の表情が陰った。
「こんにちは。お父上は御息災だろうか?」
「はい、おかげさまで……」
—— なんだろう。
二人の異様な雰囲気に気づかないほど呆けてはいない。胸騒ぎがしたは前に歩み出た。
「そう言えば、先日物凄い形相で怒鳴られて居られましたね。あれはお嬢さんでしょう?可哀相に」
千寿郎はにわかに信じがたいと言わんばかりにを見た。
「姉上、本当ですか……?」
「おや、ご存知ない?出かけておいでだったのかな」
今にも酒瓶を投げつけそうな勢いで怒鳴っておられた、と男は滑るように話す。
は男の顔を見上げた。見ていたのだ。槇寿郎のあれは酩酊のうわ言ではなかった。尚も男は涼しげな声で「お気の毒だ」と毒を吐く。
「誤解です」
はむっとした。この男と自分に腹が立った。千寿郎は驚いた顔をしていたが、そのままは「行きましょう」と促す。取り合っている暇はない。早く立ち去ってしまいたかった。
「お嬢さん、お名前は」
朗らかな声色と期待を込めた視線がを見下ろす。
「と申します」
「やはりそうですか、番付の、夫人の」
その口ぶりには返答に窮した。
気味の悪い視線が下から上へと流れる。この眼を見ると心の底に氷が張った。『行き着く先は同じ』友人の言葉がぽっと浮いて、鉛のように重くのしかかる。皮肉にも父の業が背を付いてくる。ずっと、翳が付いて離れない。一体誰が考えたのか。《金満家番付》なるものがこの世になければ幾分よかっただろう。は長いことその存在を知らずにいた。知ったのは些細なこと、友人が栞として本に挟んでいたことだ。「捨てたいところだけど、紙が良いから帳面代わりにしようと思って」
なぜ女学校で声をかけられるのか。どうして親でなく子なのか。自分を通して何を見ているのか。親が駄目なら子から。友人がしきりに忠告していたのはそういうことだったのだ。
「前からお嬢様が居られると噂はあったんですけどね。でも、紙面ではお顔はわからないでしょう」
僅かにも震えないように手提げを強く握りしめ、は千寿郎を隠すように前に出る。怖さとある種の恥じらいが渦をまいた。
「……それがどうかしましたか?」
「うちにも倅がおりまして、一度、きちんとお目通り願えないかと思っておりましてね」
その顔にはしっかりと滲み出ていた。まさに、もっけの幸い。ずっと望んでいたものが今手の届きそうなところまできているとでも言うかのようだ。渋い顔に希望と勝ち気を匂わせていた。
「わたしにも意志があります。そのようなお話には応じられません」
の態度は男の顔を険しくさせた。一つ頷かせるだけで、景色が一変するかも知れない。そのように思っているのだ。小娘一人ならどうにか丸め込める。だが、決め手となるものが欠けている。そのように考えているのは明らかで、そしてまた、自身がその一歩手前まできていることも気づいているようだった。
は内心ひやりとしていた。もし、日輪刀がこの男に見つかったら……。
すると着物の袖が突っ張った。千寿郎が袖を引いていた。
我に返ったが背を向けようとした、その時。
手首を掴まれた感触に、一挙に心臓が跳ね上がる。振り払おうとするも、この期に及んで手足が棒のように固まって動かない。
「っ、……」
は怖々と見た。が、その手は初老にしては若々しいものだった。黒い袖口から白いシャツが覗いている。気配どころか足音すらしなかった。いつの間にか、の側に杏寿郎が立っていた。うわっ、と男は一寸遅れてのけぞった。
「なっ、なんだ!?」
「この屋敷の家人だ!」
「そっ、そんなことは見ればわかる!」
杏寿郎は炯眼をもって物を言う。
“ 一つの嘘も逃すまい—— 。”
そのままじっと詰め寄られた男の額には、じわりと汗が吹き出していた。
「して、この者に何用だろうか?」
「見たところ良縁に恵まれぬようだから、うちで面倒を見てやろうと思いましてな……」
さっきの勢いはどこへやら。男の気迫は消え失せ、毒気を抜かれたようにごく普通の初老へと戻っていく。
は杏寿郎の腰元を見られるのではないかとハラハラした。だが、男はそれどころではないらしく、いかに杏寿郎の視線を逸らせるか、神経を注いでいた。今や「うちにも倅がおりまして」という言葉は何の意味もなしていないようだった。
「なるほど!だが、嫁探しなら他を当って頂きたい。失礼する!」
はもう一度杏寿郎の顔を見ようと試みた。しかしそれは敵わなかった。杏寿郎は一方を千寿郎の肩に手を添え、の手を引いたまま屋敷に入っていく。羽織の裾が翻り、を包み込んだ。振り向き様、は男が押しかけて来るのではないかと思ったが、杏寿郎が何食わぬ顔をしてぴしゃりと門を閉めた。それに加え、千寿郎が慌てて鍵を掛ける。男の目と鼻の先で閉まったそれに、は心底ほっとした。
空気がしんとした。蝉の鳴く声すら遠くに感じ、嵐が去ったようだった。
しばらく三人で立ち尽くしていると、「僕は厠に……」と千寿郎がそろそろと立ち去った。
は杏寿郎が何を考えているのかわからなかった。頭の中はぐるぐると先程の言葉が巡っている。この間も、杏寿郎は前を向いたまま微動だにしない。自分から声をかける勇気はなく、は杏寿郎の言葉を待っていた。
夏の西日が照りつけ、じりじりと焦がしていく。首に汗が伝う。
「……今日は暑いな」
杏寿郎はゆっくりとその手を離した。玄関へ入り片足に指を掛け、草履を脱ぐかと思われた。しかし即座に振り返り、杏寿郎は畏まった顔をした。
夏負けしたのかもしれない。
胸は熱く、頬は火照っていた。
夏の太陽に負けず劣らず熱のこもった眼差しに、はなぜ今日のような暑さを好むのかはっきりと理解した。杏寿郎の瞳には微塵の揺らぎもない。初めて逢った日から、何も変わっていなかった。眩しいほどに澄んでいる。『良き妻』になれなくとも、ささえる人でありたい。この人なら、この人だからこそ。そう、思わせるのだ。
「早く涼みたいところだが、まずは水だな!」
特に言葉を交わすわけでもなく、は手ぬぐいを取りに行った。
杏寿郎は水場で釣瓶を引いていた。途中で耐えられなくなったのか、が戻るころには羽織を脱いでいた。上着も脱ぎ、シャツの袖を捲る。それから首元の釦を外した後、水を汲む。
「この水を使うといい」
冷えていると杏寿郎は桶を差し出した。
「いえ、杏寿郎さんがお先にどうぞ」
「俺は桶がなくても構わない。君のは濡れたら困るだろう、よく似合っている」
「あ……ありがとうございます」
は手ぬぐいを濡らし、頬と首元へ当てた。汗は引いたが、頬の熱はなかなか引かない。桶の水は冷えているのに、何度当てても変わらなかった。
杏寿郎は釣瓶桶から直接水をすくう。豪快に顔を洗っているように見えたが、意外にも襟元は濡れていない。垂れた前髪からぽたりと雫が滴る。が真っ新な手ぬぐいを差し出すと、杏寿郎はありがとうと受け取った。顔を拭い手早く掻き分けられた前髪は、紅花が咲くように天に向かって広がった。
「……さあ、中へ入ろう。これ以上外に居ると茹だってしまう」
は相槌を打つ。杏寿郎が言うように本当に茹だってしまいそうだった。地面が吸い込んだ水飛沫はすでに乾きかけている。生ぬるい風が駆け抜け、の袖を揺らした。