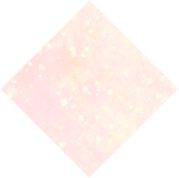第十九話
「氷を買ってきますね」
千寿郎が裏口から出てしばらく。
縁側の風鈴が涼しげな音を奏で、盆の上には二つの湯呑が並んでいた。
杏寿郎はの隣に座り、庭先を眺めた。水を浴びたおかげか、芯から煮えるような暑さは和らいだ。
今日は柱合会議だった。会議を終えた杏寿郎は家へ向かった。しかし、はすでに家を出た後。もうすぐ自宅というところであの場に遭遇したのだ。は千寿郎をかばうように立ち、神妙な面持ちをしている。何事かと思った矢先、千寿郎がこちらを見て訴えた。そこでの姉の手紙が瞬時に浮かんだ。
『—— 追伸。私の夫が御宅の近くに妙な初老が居ると申しておりました。』
私欲に溺れた人間は酷いもの。おまけに執念深い。一人去ってもまた次が来るところも似ている。されども、どんなに醜くとも悍ましくとも、香で逃げるのは鬼だけだ。が“鬼のようだ”と言ったことを、杏寿郎は言い得て妙だと思った。
「君の家に行ったらもう出たと言われて、急いでよかった」
「そうだったの?ありがとう。寄るところがあったから早く出たの」
芋羊羹を買いに行き、それから松の木がある神社に寄った。守札を買った場所だとは言う。
「松は落雷で焼けたと聞いた」
「うん。焼けて折れてしまったから切り落とす話もあったみたい。あの神社は氏神様?」
「そうなるな。昔はよく千寿郎と出かけた」
「最近ね、幹から芽がでてきたの。根はまだ生きてたんだね」
珍しいことなんだって、と嬉しそうには言う。そんな彼女の顔を、杏寿郎は覗き込んだ。は続きを催促していると思ったのか、「あ、特に落ちはないんだけど……」と視線を逸らす。そして少し真面目な顔をし、は言った。
「杏寿郎さん、番付って知ってる?」
「今場所は太刀山の一人勝ちだ!」
「……お相撲好きなの?」
「ん?前に言ったはずだが」
自己紹介ははっきりと。杏寿郎はそのように教わった。思い違いということはないはずだが、「えっと……」と言ったきり、は黙考する。
「昔のことだからな!ここに来ると、君と初めて逢った日を思い出す」
名も無き時。客間は襖で仕切られていた。話の合間、ショートケーキを取りに来た母、瑠火は、杏寿郎を呼びつけると「言われるまで入らないように」と釘をさした。杏寿郎は大人しく襖の向こうで待っていた。が、ほんのわずかな隙間が少年の好奇心を刺激した。そっと覗いた先に淡い期待を抱いた。けれども、見えるのは母の背で、少女の姿は少しも見えはしなかった。その代わりの母と目があった。その口元は薄く弧を描き、視線は隣へと移った。そこでやっと杏寿郎は少女がそこに居るのだとわかった。次は少女自身が気になった。
どんな声をしているのだろう。どんな話をしよう。
一枚の襖を隔て、想いを乗せた。
「俺はすぐに君の手を引いて庭に出た」
初めて訪れる者は、方向がわからなくなる。同じような障子が惑わす。この少女を導くのは自分しかいない。そして、杏寿郎は手を引いたのだ。
懐かしいね、とは思い出したように笑う。
「この中庭も変わってない。……実は、あの日の帰りに嫌だって言って泣いたの。紳士は背広を着ていると思い込んでいたし、あの時は言葉を知らなかったから。たぶん、緊張していたんだと思う」
あのような思いがこれからずっと続くのかと思うとまた苦しくなった。なぜか哀しくなった。知らない感情に、気づけば嫌だと口にしていたのだとは言う。
「緊張か、それならわかる」
「杏寿郎さんも緊張したことがあるの?」
予期しない言葉に、杏寿郎は呆気にとられた顔をした。
「……君は、時々妙なことを言う」
「だって、杏寿郎さんはいつも堂々としていらっしゃるから」
「また随分と買い被られたものだな」
「そんなこと、……」
その瞳は地面に転がる石を見つめた。「買い被ってなんかないよ」との声は辛うじて聞こえるほどの小さなものだ。
「背広ではなくとも、詰襟の学生もあるだろう」
「詰襟なら、杏寿郎さんだって着ているでしょ?」
「学帽は持っていない」
「学帽に興味はないの。なんならわたしの友達にも聞いてみて、絶対に笑うから」
また、風鈴が揺れる。夏の音が頭の中の塵を払い、洗うようにふわりと風が走り抜ける。温くこもった空気をかき混ぜ、からりとしたものへ変えていく。
「……わたしの紳士は昔から変わらない。何があっても、ずっと。」
真剣な眼差しは、杏寿郎の言葉を奪い取る。気づいていたことだが、どうにもこれに弱い。さっきもそうだった。杏寿郎はこれを探していたのだ。
瞬く間とはあのようなことをいうのだろう。見ようとしても何度も見れるものではない。しかしながら、その光は決して弱くはない。
「君は明けの明星を見たことがあるか?」
すぐに消えてしまうのに、いつまでもそこにあるように思う。煌々とその存在を示している。母の言葉が背を押し、それが照らす。闇夜に負けず日が昇る前に輝く、明けの明星。
「うーうん、宵の明星なら一度だけ」
「日の出前、東の空によく映える」
杏寿郎はどうしたものかと考えた。本当なら、あの光を見せてやりたい。されど、鏡を見せたところで見えるものでもなし。まるで初めて出逢った日のように、杏寿郎はその術を探した。他に何かないかと思っていると、は前を向いた。
「知ってる?金星は一人で光を放てない。だから、真っ赤に燃える太陽の周りをぐるぐる回って、その光で輝いてるんだって」
「は物知りだな」
「そんなことないよ、わたしは杏寿郎さんの方が物知りだと思う。本にないこともたくさん知っているから」
「本……」
杏寿郎は辞書を思い浮かべた。の辞書には印があった。癖の付いた頁。同じ場所ばかり見ている理由。それらを知っているのは彼女のみ。
「辞書の言葉は解決したのか?」
「うん、それはもう……」
は疑問の目でこちらを見る。
「昔、家に忘れていったとき、気になって見てしまった。黙っていてすまない!」
杏寿郎は額を付けた。今謝らなければ昔の二の舞いになると予感した。家の者は簡単に謝らせてはくれない。「全然気にしてないよ、大丈夫だから」「ねえ、杏寿郎さん?!頭を上げて、お願い!」との本気で焦る声で、杏寿郎は顔を上げる。
「わだかまりは無いほうがいいからな!」
困り顔だったはくすりと微笑んだ。
あの時抱いた想いを杏寿郎は知らなかった。まだ十も満たない子供同士、純粋に楽しい日々を過ごしていた。許婚というものがどういう存在か、理解していなかったのかもしれない。あれから時は流れ、幼いながらに感じたぼんやりとした感情はまやかしではなかったと知った。
—— 母上はなぜ、……。
杏寿郎はふと浮かんだ疑問を胸に仕舞い込んだ。考えても答えはない。ならば思うように思っておくのが一番よい。いつも仕方がないと説き伏せていたことも、存外悪くはないと思えた。
「考え癖が移ったんだろう。君と居ると、話したいこと聞いてみたいことが次々溢れ出す」
杏寿郎はこっそりとポケットを探り、先延ばしにしていたそれを手にする。の方へ向き直り、逡巡した。
だが、決して気の迷いで決めたわけではなかった。迷惑料とも違う。包みは少し傷んでいたが、今更引っ込めるつもりもない。決まりよく言うより、重要なことがある。
杏寿郎は困り果てるの姿が目に浮かぶようだった。言わなければ彼女は辞書を引いて探し出すだろう。しかし、今回ばかりはそれでは困る。何しろこの意味は辞書には載っていない。そして何より、自分の言葉で伝えなければならない。
「誤解のないよう言ってしまうが、苦労も幸せも共に過ごし、死ぬまで添い遂げようという意味がある」
はそれを見て、次に杏寿郎を見た。その表情には驚きと躊躇い、その他は窺い知ることができなかった。
「あの、……」
こんなにも時間が長く感じるものか。
煩く耳に付く鼓動が細かに時を知らせ、杏寿郎は手を焼いた。
「わたし、鬼狩りも鬼も知らないことばかりなのに」
「君が知りたいのなら、全部話そう。これはもう決めたことだ、俺の答えも変わらない!」
握った手を離してはいけない。そうしなければ、導かれた絲も簡単に切れてしまう。
守らなければならない。失ってはならない。
『杏寿郎。あなたに会わせたい方がおります』
淡い期待が大きな期待へと変わっていく。
大きな期待の落差を知っている。信じることの虚しさも知っている。それでも、杏寿郎は考えを改める気にはなれなかった。決められたことではない。これは自分で選んだことだ。そう、信じたかった。
そして彼女もまた、沢山の可能性の中で自分という存在を選んでくれはしないだろうか—— 。抱いた期待を胸に、杏寿郎はじっくりとを見た。
「受け取ってくれるか?」
やがては少女の頃とは別の、柔らかい笑みを浮かべた。
「……はい。謹んでお受けいたします」
その時、杏寿郎はあの輝きを見る。
やはり、何物にも代え難い美しさがそこにあった。

杏寿郎は湯呑を手にし、ぐっと喉に流し込んだ。するとほっとしたのか笑えてきて、杏寿郎は一人肩を揺らした。
「どうしたの?」
「花火見物で言おうと思ったことを、すべて前倒してしまった!」
は面食らった顔をした。そして眉を下げ、「やっぱり杏寿郎さんはちょっとせっかちね」と笑う。
「ところで、君の家にある虎の置物。あれは何か意味があるのか?」
「置き物……あ、口を大きく開けた?あれは厄除けとお父さまが」
舶来品。その中でもの父が特に気に入っているらしく、ずっと飾り続けているのだと言う。
「でもね、虎には勇気って意味もあるの。わたしはこっちの意味が好きだな」
「ははっ、そういうことか!」
「そういうことって?」
「用心棒」
杏寿郎は何度も問うてきたあの虎を思い出す。見る度に心の隙を突いてきた。だが、このところとんと無口だ。先日も、今日も。何も言わずに大きな口を広げている。それを知らないは尚も不思議そうな顔をした。
「他は何かある?訊きたいこと」
「学校の話、君と友人について。まだ他にもあるが、ほどほどにしておこう。また君を質問攻めにしてしまいそうだ」
は杏寿郎と目が合うと照れたように微笑んだ。
杏寿郎も目尻を下げ、穏やかな笑みを浮かべる。
見るものすべてが美しいわけではない。だが、悪いものばかりでもない。
知らなければ知れば良い。
互いに見えるものは違っていても、分かち合うことはできる。