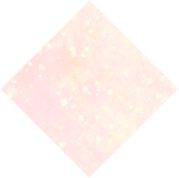最終話
『とは母上が逢わせてくださった。俺はそのつもりだが、はどうだかわからん。もし今後が姉上でなくなったら、それは俺が甲斐性無しということだ!その時は、千寿郎は気にせず笑い飛ばしてくれ!
その前に、柱にならないことにはどうにもならないがな!!』
なぜ、『姉上』か。
今となっては愚問でしかない。二人を述べるならば、比翼連理の極みであった。
数えにして十三年。夫婦としての道のりはそう長くはなかった。だが、二人の道のりそのものは長く尊いものであったのではないかと千寿郎は思う。目の前には偶然とは違う、運命とも言い難い軌跡があった。それを言い表すに相応しいものは何かと考え、天命、そのような言葉が浮かんだ。
杏寿郎は花火見物以降、を連れ様々な場所へ出かけている。ある時は歌舞伎を、そしてある時は相撲を。そして能を観劇したときのこと。帰宅後の二人は揃って「あまり話が入らなかった」とこぼしていた。
また、祝言を挙げた日はとても良く晴れていた。雪解け水が大地を潤し、桜の舞う暖かな陽気が辺りを包んだ。地は若草が萌え、花は陽を浴びようと懸命に花弁を広げていた。それらの煌きは祝福の時を待っていたようだった。
空は天まで抜けるように青い。
二世の契りを結ぶに相応しい好天の下、羽織袴で礼装をした杏寿郎は千寿郎にこっそりと言った。
「今、竹刀を振ったらすっぽ抜けるかもしれない!」
いつも堂々としている杏寿郎がそのように言ったのは、千寿郎にとって意外だった。
兄、そして姉と慕った二人の門出。弟として気の利いたことでも話せばよかったのかもしれない。しかし、
「大丈夫です。祝言に竹刀は要りません」
そう返すことで精一杯だった。何しろ千寿郎自身、媒酌人を務めることになっていて、失敗するわけにはいかなかった。味噌のようにはいかない、一度きりの大役である。そうしていると、奥の部屋から「整いました」という藤の者の声がする。
一歩ずつ歩み寄る気配に、千寿郎は胸を高鳴らせる。おそらくそれは杏寿郎も同じであったであろう。
部屋の前に、静寂が訪れる。
そちらに目を向け、千寿郎は言葉を失った。そこにいるのは「姉」で間違いないが、姿形はまるで違って見えた。紅を引いた口元がこちらに柔らかく笑いかける。千寿郎はわぁ、と声が漏れるのを抑え、隣を見やる。
「兄上、……」
同じく笑いかけているのだろう。そう思っていた千寿郎だったが、思わぬことで言葉が詰まる。兄はとても真摯な顔つきでを見ていた。眉一つ動かない。真顔だ。
それを見て、千寿郎は竹刀どころか盃をも取り落とすのではないかと不安に思った。足元に扇子が落ちたことにも気づいていない。変わらず呆けたままの杏寿郎に「まぁ」「あらあら」「炎柱様ったら」介添人たちがくすくすと笑い出す。一度は消え失せようとしたものが、再び繋ぎ合わさっていく。どこか懐かしい心地に包まれながら、同じく肩を揺らしていた千寿郎は、一瞬、気を取られた。
姉の顔は綿帽子ではっきりと見えはしなかった。けれども、じっと見た兄は何かを語っているように見えた。
その瞬に、二人だけしか知らない言葉の交わりを見た気がした。
やっと口を開いたと思えば、「本当に俺の妻だろうか」と言い出すので、どっと笑いが起きた。も肩を揺らし、やがては杏寿郎も笑い出した。
それは心地の良い笑い声で、幸福が手招きをしているようだった。