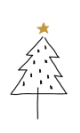その姿が見えたのは、ライトアップされた街路樹が煌めき始めた時だった。
「今日は冷えるな!」
待ち合わせ場所にやってきた煉獄くんの息は少しだけ上がっている。準備が遅くになったので早足で来たと言って、素のままの両手を擦った。いつもの毛糸の手袋は持ってこなかったらしい。遅刻しそうなときこそ早く着いてしまうのはよくあることだが、いつもどんな時も一番に待っている煉獄くんにしては珍しかった。
「君ひとりか?」
「うん。そろそろみんなも来ると思うけど……」
手元のスマートフォンの画面にはメッセージの通知が届いている。
「あ。今、向かってるって」
集合時刻まであと数分ある。普段ならたわいも無い話であっという間に過ぎる時間だ。けれどこの日の私たちはそれからすっかり黙り込んでしまって、友人たちの姿が見えるまで、視線の置き場に苦労した。
*
あれは数日前。後期テスト目前というのに、講義室はどことなく浮足立つような空気が流れていた。もうすぐ冬休みということもあるが、差し迫った一大イベントがそうさせているのだ。授業の時間になり、慌てた足音が講義室の出入り口でピタリと止まった。ひょいと顔を出した人物は斑に空いた席を見渡し、こちらにずんずん向かってくる。
「ここ空いてるか? 座ってもいいだろうか?」
「うん、大丈夫だよ」
よかったと、煉獄くんはさっそく机に筆記具を広げる。煉獄くんは私と同じゼミを選択している。なので講義が被ると時々こうして、本当にごく稀に近い席に座ることもあった。
「ギリギリだね」
いつもは5分前には着席してるのに、今日は私と逆の立場だ。
「ああ。うっかりそこの廊下で話し込んでしまってな!」
誰と、とは言わずに煉獄くんはテキストを捲った。色とりどりの付箋が目につく。黄色と水色が主であったが、どういうルールで色分けしているのか私には見当もつかない。真似しようと思ってもきっと同じようにはできない、そんな気がした。
「君、25日は空いてるか?」
それが囁くような小声で、思わず「え」と呟いた。彼は聞こえなかったと思ったようで、さっきよりはっきりとした声で続ける。
「12月25日だ」
気の所為ではないと思う。一瞬、前の席の女の子の手元が止まった。
「あ……うん、空いてる。空いてるよ」
「駅前のクリスマスマーケットに」
せめてあと5秒。ほんの少し講師が遅く来ていたらと思う。「遅くなってすみません」と授業が始り、煉獄くんはさっきのことなどまるでなかったようにこちらを見向きもしなかった。90分、一度もだ。その間、私の思考は12月25日に向かって走りだしていて様々な想像をする。
25日、クリスマスマーケット。
それで何を思い浮かべるのか。私も浮き足立つ学生の一員になったのはいうまでもない。
「ねえ、さっきの話だけど……煉獄くん?」
しかし講義が終わると煉獄くんは早口に後で連絡すると言って、教室を飛び出していってしまった。
それからすぐ、通知を開いた私は驚くほど肩を落とす。煉獄くんが送ってきたのはゼミグループを通してのメッセージ。
—— 一緒にクリスマスマーケットに行かないか?
みんなで出かけるほうが楽しいから。理由はそんな感じだろうか。
返事を打とうとするとグループで一番のお調子者の男子が素早く先回りし、私が来ないと奇数になってしまうと脅してきた。一人の時間を持て余した男女は計6名。この件で唯一の朗報は、煉獄くんがまだ一人であることが知れたことかもしれない。
*
「すごい人だな! 迷子になりそうだ!」
その煉獄くんの声に友人たちはこぞって笑う。この企画の発起人の男子は煉獄くんの肩をぽんぽんと叩き、まるで長年の友人のような仕草で肩を抱いた。
「煉獄、お前は真っ先に見つけるから心配すんな。な?」
「それは頼もしいな!」
ははっと笑う煉獄くんに、一同も笑みを浮かべる。煉獄くんが見つからなくなるなんて誰も思っていないことがひと目でわかった。
数年ぶりのホワイトクリスマスを期待したが、東京の空は清々しいほどに晴れ渡っていてクリスマスマーケットはとても混んでいた。野外テントの下、早々に円卓を囲った私たちの目の前には先程買ったばかりのソーセージの盛り合わせやグリルチキンが並んでいる。「これじゃいつもの飲み会と変わんないよ〜。何かあると思って期待したのにさぁ?」と、女子の一人が笑いながらビールを豪快に飲み干す。私は相槌ともいえない角度で頷き、持っていたドリンクを一口含んだ。ふと、手を繋ぐ恋人たちがちらりと視界に入り、自分のそれに視線を落とす。それからそれとなく煉獄くんの手を追った。彼の手はペッパーソーセージを口に運んでいる。「うまい!」とお決まりのセリフにみんなが真似をした。そうすると一気に場は熱くなるのだ。
「君も食べてみるといい、美味しいぞ!」
「ほんと? じゃあ私も……アツっ、でもおいひっ」
私も同じように「うまい」と言ってみたけれど、様にならなくて恥ずかしかった。ソーセージの旨味が一気に弾け、飲み物、と手元を見る。
「君のそれは?」
煉獄くんと視線がかちあい、私は急いでそれを飲み込んだ。
「ホットワイン……だったもの」
どうりで体が熱いわけだ。一杯で十分だと思っていたが、いつの間にか底をつきそうになってる。本当は甘いチョコレートドリンクを飲んでみたかったけれど、この空気では場違いだ。
「煉獄くんは?」
「君と同じ。ホットワインだ」
煉獄くんもグイっと手元のそれを飲み干した。食べるのも飲むのもどちらもいける人のようだ。
「飲みものを買ってくる!」
煉獄くんは周りの音に負けないような大声で言った。かと思えば、
「君も来るだろう?」
囁くような声で私に言う。空のカップを見て、途端に踊りだした心臓が悩ましい。もしかしたら煉獄くんも酔っているのかもしれない。ちらりと様子を窺うと、髪束の隙間からほんのり赤くなった耳が覗いていた。そして視線が合うと煉獄くんは小さく広角を上げた。慌てて向かいに座る友人たちを見たが、彼女たちはこちらに気づくそぶりもみせず会場に流れるBGMと今年の思い出話に花を咲かせている。小さく頷いた私に何か言う者はいない。
「あの、行ってくるね?」
現実を確かめるように彼女たちへもう一度声をかけてみたが、まるで聞こえていないようだった。すると煉獄くんはダウンのフードを被り目立つかどうか訊いてきた。
「うーうん、そんなことないよ」
「本当か?」
「うん」
周囲にフードを被っている人はそう多くないけれど、黒色ということもあって特別に目立つこともない。すくなくともいつもの煉獄くんより控えめだ。
「ならば安心だな」
「安心?」
よし、と何かを決意した煉獄くんはじっくりを私を見つめ、
「少しだけ迷子になろう」
そう囁いて、私の手を引いて恋人たちに紛れたのだった。